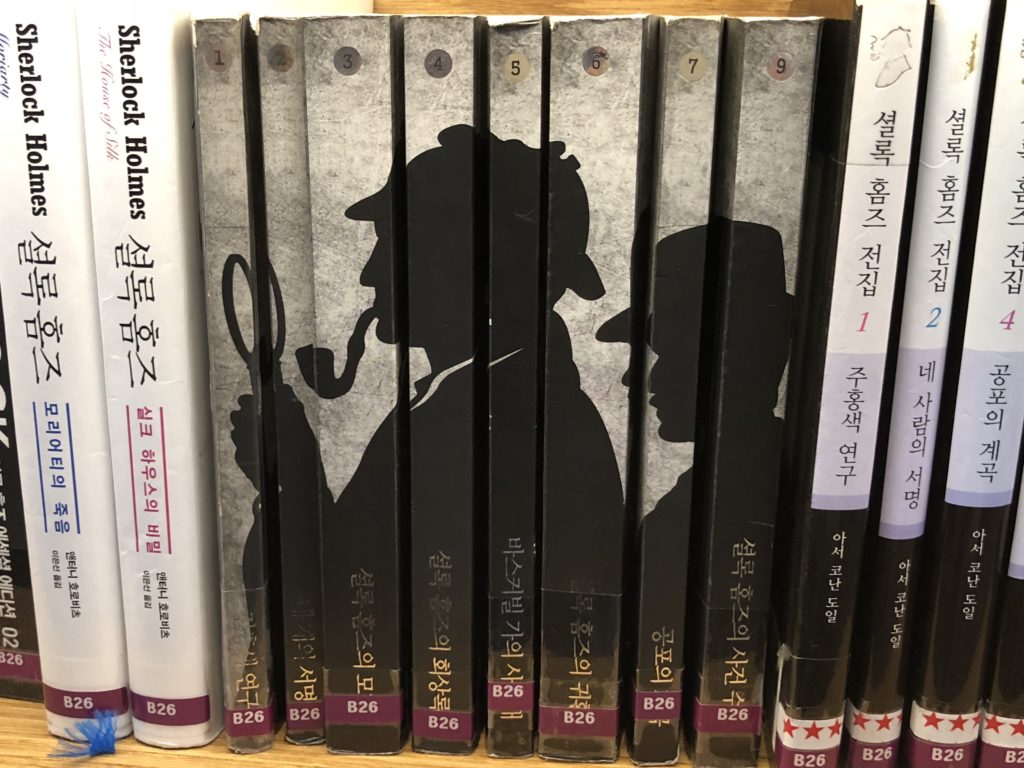小説はあらすじじゃない。描写にこそ面白さがある
このページではアーサー・コナン・ドイルの名作『ロスト・ワールド』について述べています。
小説はあらすじじゃない。描写にこそ面白さがあるという見本のような小説でした。
さすがシャーロックホームズの作者。ストーリーは推理小説のようにどんでん返しの連続です。
物語の面白さというのはあらすじにはないのだ、ということを見事に見せつけてくれます。
人間描写のおもしろさ、つまり小説力があれば、どんなあらすじだって面白く書けるし、それがなければ、どんなあらすじだってつまらない作品にしかならないのです。
【書評】『ロスト・ワールド』について
ひとことでいうならば「南米のテーブルマウンテンに、失われた太古の世界がそっくりそのまま残っていた」という話しです。小説が発表された当時は画期的なアイディアだったのだと思います。
絶滅したはずの恐竜が生き残っていて、それを調べるため学術調査という名の冒険に行くというのがストーリーの骨子なのですが、『ロスト・ワールド』の面白さは実はそこではありません。
作者の人間洞察力が、描写の端々に現れます。
さすが推理小説の作者だなあ、と思わせるストーリーは大どんでん返しの連続です。
語り部の主人公マローンは新聞記者。グラディスに恋をしているが「英雄と結婚したい」と言われてフラれます。
そこで発奮。チャレンジャー教授の主張する「失われた世界」を実証する学術調査隊に新聞記者の特派員として参加することになったのです。
チャレンジャー教授は自分の大発見が歴史に残るものだと確信しているが、それを認めようとしない世間に牙をむく人物。この人物を作者コナン・ドイルはシャーロックホームズよりも愛したそうです。
チャレンジャー教授シリーズという一連のSF作品が他にもあるのです。
恐竜が絶滅したという学者に対して、チャレンジャー教授は黙っていられません。大ブーイングを浴びても、恐竜は今も生きていると主張します。そして次から次へと毒舌でたくさんの敵をつくっていくのです。そこのところが面白い。作者が愛したのもうなずけます。
学術調査団は恐竜滅亡説のサマリー教授(60代)と、探検家のジョン・ロクストン(40代)、そして新聞記者のマローン(20代)が主要メンバーです。
ここで読者は「あれ、肝心のチャレンジャー教授は調査団に参加しないのか?」と驚きます。
次々と敵をつくっていく強烈なチャレンジャーの個性に興味をおぼえはじめたところだったのに、学術調査団に参加しないのでは、ここでサヨナラです。
残念。別れたくありません。
ロクストンはマローンが死を恐れないか勇気を試しますが、マローンは期待に応えました。
作者は書きます。勇気なしと思われるぐらいなら断崖から飛び降りた方がマシだ。もしそんな行動に出るとすればそれは実は勇気ではなく、プライドや惧れからなのだが……。
こういう何げない描写こそがストーリーに勝る面白さの秘訣だと思っています。
ロクストン「南米アマゾンにはわくわくする冒険につきものの危険が一マイルごとに待ち受けている。冒険の危険というやつはね、生存に必要な塩なんだ。そしてふたたび人生に価値を取り戻してくれるのさ。われわれの生活はあまりにやさしく、退屈で安楽すぎる」
渋い男です。人物造形が際立っています。
こうしてマローンはロストワールドを探す旅に出発しました。恐竜を見つければ英雄になって、グラディスと結婚できるかもしれません……。
読者を退屈させないために、アマゾンまでの船旅や、都市での滞在シーンは一切カットされます。
次のシーンではいきなりアマゾンでチャレンジャー教授の手紙を開封するところから始まります。そもそもどこに向かって進めばいいのか、言いだしっぺのチャレンジャー教授でないとわからないのです。
しかし手紙は白紙でした。
やはり騙されたと怒るサマリー教授の目の前に、なんと突然チャレンジャー教授が現れます!!
こういうところが推理小説っぽくて『ロスト・ワールド』は面白いのです。
チャレンジャー教授は、ロストワールドの場所を秘密にしておくためと、主にサマリー教授との不愉快な道中を一緒にしたくないから長い船旅を別にしたのでした。
そして現れるや否や「吾輩が探検隊の指揮をとる」と宣言します。
サマリー教授は面白くありません。サマリー教授を無学だとバカにするチャレンジャー教授の挑発に、サマリー教授も黙ってはいません。
マローンは頭脳の明晰さと高潔な人格とは全く別ものなのだとチャレンジャー教授から学ぶのでした。
年下のロクストンとマローンが、学識ゆたかで怒りっぽい二人の教授をなだめながら、旅はジャングル奥地へと分け入っていきます。ストーリー以上の面白さをコナン・ドイルは提供しています。
チャレンジャーとサマリーは学術的な議論をたたかわせます。遠くに見えた巨大な生き物をコウノトリだと主張するサマリー教授の目の前に、翼竜が現れて夕食を奪い去っていた時に、感動しつつ、自分が間違っていたとサマリー教授はチャレンジャー教授に詫びをいれます。二人が仲良くなったことにくらべれば、夕食を奪われたことなどちっとも惜しくありませんでした。
人が登れないテーブルマウンテンの上に木の橋をかけてようやく一行はロストワールドに上陸します。しかしロクストンに怨みをもつポーターに裏切られて、木の橋を落とされ、ロストワールド上に孤立してしまう。
主人公たちは目の前に魅力的な新世界(旧世界?)がある反面、文明社会に帰れなくなってしまいました。
そのジレンマに引き裂かれつつ一行は学術調査を続けます。
吸血ヒルひとつとっても新種です。ヒルですら貴重な種だと無学な君たちにはわからないとチャレンジャー教授は嘆きますが、自分が吸血されそうになると悲鳴をあげてヒルを追い払います。
恐竜イグアノドンがついに目の前に現れると、チャレンジャーとサマリーは興奮し、たがいに手を握り合いました。
サマリー「これを報告したらイギリス学会では何というだろうかね」
チャレンジャー「大ウソつき、科学界のペテン師といわれるよ。君が吾輩をそう呼んだようにね」
サマリーは閉口しました。
恐竜に襲われた人類という命があやうい刹那ですら、二人の教授は「有意義な情報が得られた」と人類史上初の体験をよろこんでいます。
チャレンジャーはもっと知りたくてロスト・ワールドの奥地へ進もうとしますが、サマリーはロンドンの学会で報告しないと意味がないと主張します。
ここではじめてサマリーはチャレンジャーに議論で勝ちました。一行は帰路を探しはじめます。
マローンは首長竜プレシオサウルスの住む湖を大陸中央に発見し、その湖にグラディス湖と名付けます。
ロストワールドには、剣竜ステゴサウルスもいれば、恐鳥フォルスラコス、顔がガマガエルのような肉食恐竜もいました。
この顔がガマガエルのような肉食恐竜に捕食される恐怖をマローンたちは味わいます。しかし恐竜に襲われるパニックで終わらないところがさすがコナン・ドイル『ロスト・ワールド』。
恐竜に襲われるのだろうな、と思っていたら、なんと猿人に襲われるのです。失われた世界の上にも未開人が住んでいて、未開人は猿人と戦争をしています。
猿人の捕虜となったイギリス人たち学術調査団一行でしたが、チャレンジャー教授だけは猿人から特別扱いされています。その理由は猿人のボスがチャレンジャー教授と兄弟のようにそっくりだからでした。そのためにサマリーたちのように殺害対象とはなっていません。
サマリーとチャレンジャーの大馬鹿コンビは、死刑間際にも、猿人のルーツがピテカントロプスかどうかで議論している始末です。
猿人に処刑される寸前に、銃撃戦をして逃げ出したイギリス人たち。
吾輩の命を救ったことはヨーロッパ近代動物学史を救ったことだとチャレンジャー教授は大げさに感謝するが、その顔は猿人の王にしか見えません。チャレンジャーはちょっと傷つきます。
チャレンジャー「未開な人種というのは、威厳があり人間性ゆたかなものを尊敬するものだが、ロクストンは実にばかげたことにこじつけている。猿人の王はじつにいい顔をしていて、知性も豊かなやつだった。そのようには見えなかったかね?」
チャレンジャーはマローンに自分が猿人の王とそっくりだったことは新聞に公開しないでくれと暗にたのむのでした。
イギリス人たちは、未開人と協力して、猿人と戦争をします。そして猿人を打ち倒すのです。こういうところが映画『ジュラシック・パーク』とは違います。
さて、ロストワールドのテーブルマウンテンからどうやって下に降りましょうか?
大木がないから橋をかけることもできないし、ツルクサでロープをつくって下降することもできません。
そこでチャレンジャーは気球のようなものを発明します。
動物の膜からつくった袋に、間欠泉から吹き上げるガスをつめこむと、宙に浮いたのです。
パラシュートのようにゆっくりと下降するチャレンジャーの計画でしたが、試作機は強力な浮遊力でチャレンジャーどころか三人の大人が空に浮かんでしまいました。つないだ紐が切れて、ギリギリのところで助かったのです。
浮遊ガスの量を調整して、このパラシュートでゆっくりとテーブルマウンテン下に降りるんだろうな、と思っていたら、違いました。
実は未開人たちは秘密の昇降ルートを知っていて、マーロンはそれをこっそり教えてもらうのです。
けっきょく、動物の皮でつくった気球はつかいません。
描かなくてもいいシーンをわざわざ書いたということは、作者はただチャレンジャー教授を宙に浮かせてびっくりさせたかっただけのようです。
こうしてイギリスに帰った一行が「恐竜の住むロストワールド」について学会で報告することになります。
しかし、恐竜の実在を信じない者たちの舌鋒するどく、場は荒れに荒れました。
しかしチャレンジャー教授は、奥の手を用意していました。
なんと生きた翼竜を持って帰ってきていたのです。
ガーゴイルのような翼竜が飛び立つと、学会は天地がひっくり返ったかのような大騒ぎとなりました。
翼竜は窓を割り、ロンドン上空に飛び去って行きました。(オチ1)
通常、この手の恐竜ものではティラノサウルスが主役を張るものですが、『ロスト・ワールド』で主役を張るのは巨大な蝙蝠のような翼竜です。ディモルフォドンやプテラノドンなどの恐鳥類でした。
作者は翼竜が大好きのようです。ラストシーンも翼竜で締めくくられます。
こうして学術調査隊は、英雄となりました。
マーロンがロンドンに戻っていちばんやりたかったことは、もちろんグラディスと会うことです。
恐竜の実在を証明し、世界中の注目を集めた自分ほどの英雄は滅多にいませんから、いよいよグラディスの心をものにすることができるかと思われました。
ところがグラディスは既に結婚していました。あれほど英雄と結婚したがっていたグラディスが誰と結婚を?
作者は書きます。人生とはなんとこっけいなものだろう。
マーロン「きみはなにをしてのけたのかな? 埋もれた秘宝を見つけたとか、極地探検とか、海賊とひと暴れしたとか——なにをなしとげたの? 愛を勝ち取る魔術はどこに? どうやってそいつを手に入れたんだい?」
「ちょっと立ち入りすぎでは?」グラディスの夫はいった。
「なら、ひとつだけ。きみは何者だ? 職業は?」
グラディスの夫は弁護士事務所の書記でした。ロンドンの小さな事務所で助手をつとめる人物でした。
これが『ロスト・ワールド』のオチ2です。
失われた世界を見つける冒険をしたマーロンは、英雄でも何でもないただの事務職に、恋というたたかいでは負けてしまったのです。わかります。それが人生だよね。
ロクストンには、もうひとつロストワールドから持ち帰ったものがありました。
ダイヤモンドです。テーブルマウンテン上にはダイヤモンド鉱床があったのです。
大金でした。しかしロクストンは生死をともにした仲間で、きっかり四等分するという。
ロクストン「もちろんこれはわれわれみんなで公平に分配すべきものです。それ以外の方法はいっさい受けつけられない。さてチャレンジャー教授、五万ポンドをどう使います?」
チャレンジャー「吾輩は、自分の博物館を立てたい」
ロクストン「サマリー教授は?」
サマリー「教職から身を引いて、白亜層化石の最終分類に生涯をおくりたいものです」
ロクストン「わたしは自分のために、装備の整った探検隊を組織して、もう一度あのなつかしい台地を訪れるつもりです。マローン君、きみはもちろん結婚の資金だな?」
マローン「いや、まだしません。ぼくはですね……もしよかったら、いっしょにつれていってほしいんですが」
ロクストンは何も言わなかったが。だが、テーブルの向こうから日焼けしたその手をさしのべてきた。
これが『ロスト・ワールド』の3番目の、そしてラストのオチである。(オチ3)
ここでようやくマローンはチャレンジャー教授を脇役に追いやって、ほんとうの英雄になったのでした。
仕事で成功した後に女性を口説こうという考え方は間違いだ
見てきたように『ロスト・ワールド』にはオチが三つも用意されています。
それぞれどこで終わっても結末が決まるのに、これでもか、これでもか、と三つもオチを用意してくれました。
中でも私は二番目のオチが気に入っています。
「いい男(=英雄)になって女性を口説こうとする男性」が古今東西どこの世界にもいますが、その手が通用しないことは『ロスト・ワールド』がはっきりと教えてくれます。
女性を口説きたかったら、今この瞬間に、なりふり構わず口説くことです。
仕事で成功したら、とか、冒険から帰ってきたら、とか考えていたら、その間に、他の男に取られてしまいますよ。マローンのように。
英雄になったらモテるだろうと思うのは男性側の幻想で、ほとんどの女性は自分の男に「英雄」なんて求めていないのではないでしょうか?
こういうオチは、大きなストーリーラインとは何の関係もありませんが、こういうところが小説を面白くしてくれているのです。