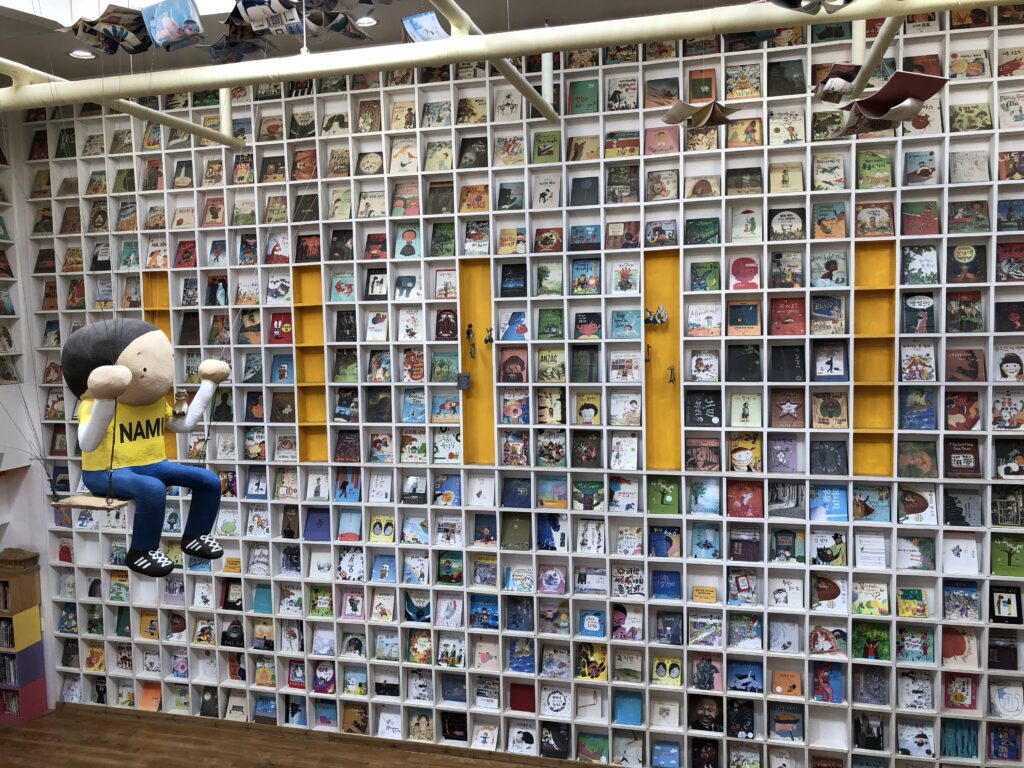旅先を舞台にした映画、小説を読む
海外旅行の前にはその国にゆかりの映画、小説などを読むことにしている。「その国」を旅先に選んだのは、配偶者に「その人」を選んだようなものだ。親は選べないが、夫や妻は選べる。生まれた国は選べないが、旅する国は選べる。
旅はまた「出会い」でもある。せっかく出会ったのだから、出会った人のことをよく知りたい。「その国」のことをよく知りたい。そうは思わないか?
これを機会に、その国を旅しなかったら出会うこともなかったはずの映画や小説を読んでみることをおすすめしたい。
辻仁成『サヨナライツカ』
タイを旅するにあたって選んだのは辻仁成『サヨナライツカ』。辻仁成は言わずと知れたロックバンド『ECHOES』のボーカリストにして芥川賞作家。そして女優の南果歩やアイドル中山美穂の元夫である。「こんな男になりたかった」と率直に思える憧れの人物だといっていい。
私が辻作品を読むのは『ピアニシモ』『冷静と情熱のあいだ』に次いで三作目だ。
前に読んだ二作の印象が非常によかったから、今回旅の友に選んだわけである。ただバンコクが舞台というだけで本作を選ぶことはなかっただろう。
|
新品価格 |
物語のあらすじ
※作品のあらすじ紹介に対する基本的なスタンスについてはこちらからどうぞ
(第一部)
タイのバンコクで、サラリーマンの主人公の豊は、杳子と出会う。杳子はザ・オリエンタル・バンコク・ホテルのサマーセットモーム・スイートで暮らすほどの大富豪にして謎の美女である。二人はタイの日本人社会を敵に回して愛し合うが、豊には創業者の未亡人が間に入った婚約者がいた。出世をとるか? 自分の気持ちに正直に生きるか? 豊は悩みながらも杳子との刺激的な性行為に溺れる。果たして体の相性のよさは愛と同じなのか? 死ぬ前に思い出すのは、人を愛したことか? それとも愛されたことか? 豊は杳子との関係に未練をもちながらも、結婚相手としては豪華すぎる杳子を選べず、二人はバンコクで別れる。
(第二部)
杳子との別れから二十五年が経過している。かつての婚約者と結婚し、出世し、専務になっている豊がバンコクに出張することになって、杳子と再会する。杳子は豊が忘れられずにずっと恋心をいだいたままで独り身でいた。二人は気持ちを確かめあうが、二十五年は何もかも遅すぎた。
(さらに4年が経過)
豊はもう六十近く副社長になっている。ゴージャスなデザートのような杳子を結婚相手に選ばなかったので家庭生活は平穏そのものだ。そこに杳子からの手紙が届いた。癌で余命いくばくもないことが知れると、豊は仕事を投げ出してバンコクに向かう。再会し、互いの気持ちを確かめ、人生に意味をつけて、杳子はこの世を去る。無謀で、大胆で、激しく瞬間に生きた、若かりし過去を思い出す豊。そのころの気持ちがずっと続くと思っていたのだ。杳子もずっと一緒にいてくれると思っていた。
|
新品価格 |
作者のいいたかったことは何?
人生のほんの一時しか一緒に過ごさなかったのに、一生忘れられない存在というものがある。
それが作者のいいたかったことの核心なのであろうと私は思う。
時は流れ去っていくが、人間の気持ちは一所にとどまる。
この考えに共鳴できそうならば、『サヨナライツカ』をご一読するといいと思う。
作品におけるバンコクの扱いは?
バンコク行きの飛行機の中でジントニックを飲みながら読了した。人生の至福の瞬間を演出してくれた一冊である。
そもそもバンコクが舞台の本なので読んだのだ。作中にはチャオプラヤ川やトゥクトゥクやパッポンやドンムアン空港が出てくる。
しかしバンコクはあくまでも舞台にすぎない。作者が書きたかったのは恋する二人の感情であり、バンコクの観光案内ではない。
この作品の舞台がバンコクである必然性はないと思う。恋に落ちた場所なんてどこだっていいのだ。クアラルンプールだってモスクワだってパリだって同じ作品が描けると思う。
それでもどうして舞台がバンコクだったのか。それは作者にしかわからないことだ。
激しい恋が熱帯地方のイメージだったのかもしれない。寒すぎるモスクワでは恋のことばかり考えていられないかもしれない。
読者はどうしても豊の顔は辻仁成に、杳子の顔は中山美穂を思い浮かべてしまうから、二人が暮らしたパリでは、ちょっと生々しすぎるのかもしれない。性行為の描写もたくさんでてくる。現実の印象が強すぎると、空想に飛躍するときの足枷になることもある。
バンコクあたりがちょうどよかったのかもしれない。
異国というのは恋の舞台として使いやすい。出会いが限定されるから。日本人同士というだけで特別な関係が築けるのだ。まわりが全員韓国人だったら、日本人だというだけであなたは私にとって特別な存在である。
異国の恋は不倫マジックを演出する
また、国内の恋愛ではなく異国での恋愛だったという設定が果たす役割は大きい。
「会いたいと心底思ってもそう簡単には会えない」という舞台が自然と出来上がるからだ。
「相手に妻がいるから心底会いたいのに会えない」という不倫と同じオアズケ状態に悩み、迷い、苦しむことができる。
これがご近所の独身同士ではそうはいかない。隣の町に住んでいて、会うのに何の障害もないのに、会いたいのに会わず、死ぬ前に死ぬほど後悔するんじゃ、ただのバカである。
愛し合っているのに、別れて、再び会えなかった。そういう設定が必要だった。だから異国の恋だったのであろう。
私の感想
恋愛の作品だから、仕事のことは、作中すっ飛ばされている。副社長までになった仕事のことはわずかに書き込まれているに過ぎない。主人公は航空会社の広報を仕事にしているのだが、航空会社の集客に豊がどれだけ成功しようと、読者にとっては「どうでもいい」「そんなの興味がない」情報にすぎない。読者はこの作品に恋のだいご味を求めているからだ。広報の仕事は誰か他に変わりがいるが、杳子の愛する人になれるのは豊しかいない。
だから作者は仕事のことは書き込まないのだが、そこをバッサリ切るのが作者の力量ともいえる。こういう作品ばかり読んでいると、恋愛至上主義者になってしまいそうである。
読み終えた本は安宿の本棚に寄贈する
こうして読み終わった『サヨナライツカ』をバンコクの安宿の本棚に置いてきた。そこには世界中の旅人が読み終わった本が捨てられてある。
本の墓場であり、本のプラットフォームでもある。英語のロンリープラネットが数冊積まれてある。バンコクの観光案内本が多いが、日本語の小説もたくさんあった。バンコクだから日本語の本がたくさんあるのだ。これがパリではこううはいくまい。辻仁成がバンコクを舞台にしたのはこういうところに意味があるのかもしれない。
本棚に檀一雄の『青春放浪』があった。バンコクの旅人が読んでここに置いていったものだ。いや、本の汚れ具合からすると世界を放浪した若者と一緒にすでに世界を一巡してここに身を休めていたのかもしれない。その本をもらっていくのと引き換えに『サヨナライツカ』を寄贈する。
しばしのお別れだ。サヨナライツカ。
いつか若く野心のある旅人の手に渡って、『サヨナライツカ』が世界中を旅していることを、おれは夢見た。
× × × × × ×
『ギルガメッシュ叙事詩』にも描かれなかった、人類最古の問いに対する本当の答え
(本文より)「エンキドゥが死ぬなら、自分もいずれ死ぬのだ」
ギルガメッシュは「死を超えた永遠の命」を探し求めて旅立ちますが、結局、それを見つけることはできませんでした。
「人間は死ぬように作られている」
そんなあたりまえのことを悟って、ギルガメッシュは帰ってくるのです。
しかし私の読書の旅で見つけた答えは、ギルガメッシュとはすこし違うものでした。
なぜ人は死ななければならないのか?
その答えは、個よりも種を優先させるように遺伝子にプログラムされている、というものでした。
子供のために犠牲になる母親の愛のようなものが、なぜ人(私)は死ななければならないのかの答えでした。
エウレーカ! とうとう見つけた。そんな気がしました。わたしはずっと答えが知りたかったのです。
× × × × × ×