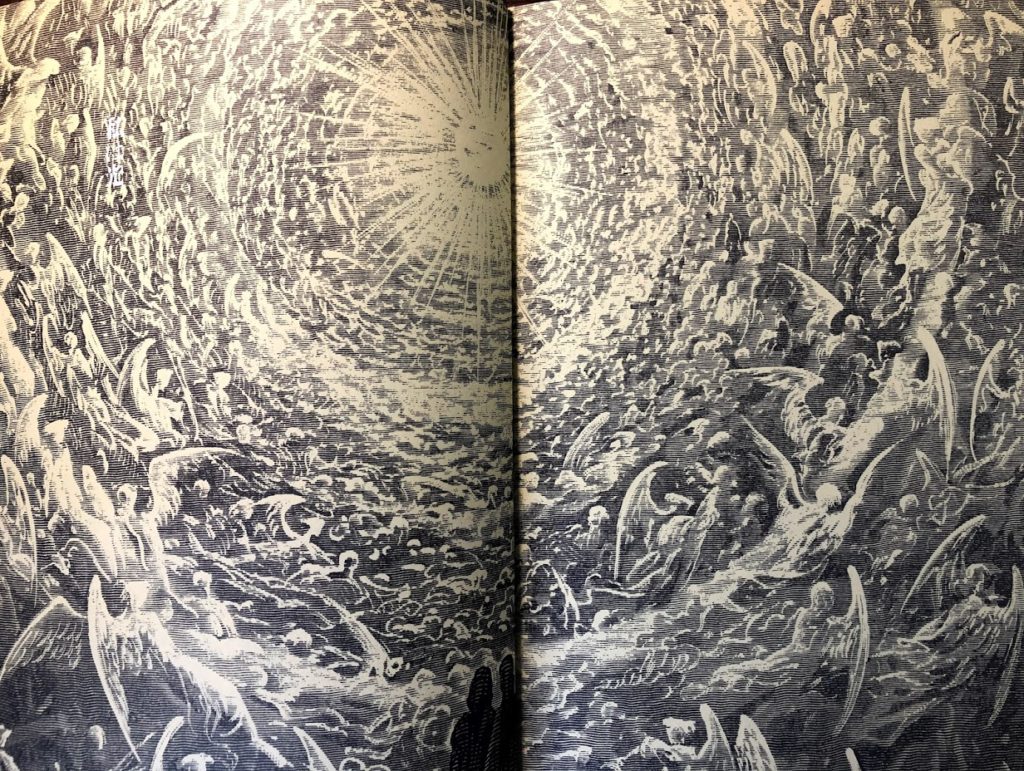作家であれば、誰しも一度はモチーフにしたいと思う状況設定
自分は死ぬ時に何を考えるのだろう。自分の死体は誰がどのように処理してくれるのだろうか。およそ作家であれば、誰しも一度は作品のモチーフにしたい状況です。「自分の死とどう向き合うか」は、作家の執筆動機の筆頭だといっても過言ではありません。
たとえばヴィクトル・ユーゴーも同様のモチーフで作品をものにしています。
『死刑囚最後の日』ヴィクトル・ユーゴー。死に臨む書、アンフェアな書物
でもあまり多くの作家がそれを書いていないのは、あまりにもベタな設定だし、先人が一度書いたことに新しく付け加えることが何もないから、みんな書かないのでしょう。けっきょく、死は死であって、おもしろいことも、変わったことも、神秘的なことも何もないからなのだと私は思います。
ところが、作家なら誰でも書きたい死ぬ直前という設定で、小説をまともに書いた人がいます。その人はロシアの文豪トルストイ。『イワン・イリッチの死』という作品がそれです。タイトルからして、そのまんま、な作品です。
人が死ぬ前にどう思うのか。これは人生の総括を描いた作品です。
トルストイ『イワン・イリッチの死』の書評。内容
短い作品です。作品冒頭から主人公のイワンは死んでいます。そして死んだイワンのことを、生き残った人たちがいろいろと噂しています。そのあたり黒澤明監督の映画『生きる』と似た構成です。もしかしたら黒沢明は構成を参考にしているかもしれません。
公務員はやりがいのある仕事か? 官製ワーキングプア問題を報道するマスコミの矛盾
「年金を即座に欲しがる未亡人。」が登場します。
「医者もはっきり診断ができなかったのさ。みんなまちまちなんだ。」
さてイワン・イリッチ(レフ・トルストイ)は死ぬ前に何を思うのでしょうか?
「カギカッコ。」の中は本書本編からの引用です。
自分はまだ生きている。死んだあいつよりは、自分のほうがまだマシだ
「死んだのはおれではなくあの男だ。といういつも変わらぬあの悦びの情を呼び覚ましたのである。」
「死んじまった。だが、おれはこの通りぴんぴんしてるぞ。」
「三昼夜の恐ろしい苦しみと死、それは今すぐにも、ほかならぬ、このおれのことになるかもしれぬのだ。」
日本でも、年末になると「その年に亡くなった有名人、芸能人」の特集があったりしますよね。テレビで取り上げられるのは栄耀栄華を極めたような人たちばかりですが、そういう人たちを見て「死ぬよりはマシだ、おれはまだ生きている」と思うことはありませんか? その点、ロシア人も、日本人も、同じ感覚のようです。
「イワン・イリッチが耐え忍んだおそろしい肉体的苦悶。」
「イワン・イリッチの最後の様子などを興味ありげな様子で、根掘り葉掘りききはじめた。それはまるで死というものが、イワン・イリッチのみに特有の変事であって、自分にはまるで関係がないというような風だった。」
私にはこの感覚がよくわかります。死は他人ごとであり、自分ごとではないという感覚。
この自分が死ぬなんて。そんなバカな。……みんなそう思っているのです。
ライバルみんな墓の中(徳川家康)。長生きするということは人生のひとつの勝利のかたちに違いありません。短命だということは不幸のひとつのかたちに違いありません。
もちろん例外はあります。それは理解できます。
しかしやはり自分より先に死んだ人に対して、このように感じて自分を慰めるということは、世界中の誰にでも起こる感情なんだなあ、と思わずにいられません。
「自分はまだ生きている。死んだあいつよりは、自分のほうがまだマシだ」
死の病床で、誰もが自分の死を信じられず、うろたえる。
「自分の身にそんなことが降りかかるなんて、とうていありうべからざる話だ。そんなことの起ころうはずがない。」
「吸収作用が起こり、排泄作用が起こって、規則正しい機能が復活されたように夢想する。」
誰しも病気になると全快することを夢想しますよね。この気持ちもよくわかります。
「もう今から気分が良くなったような気がする。ずっとよくなったようだ。……なんということだ。またしても。決してやまない痛み。もとは生命があった。それがいま逃げて行ってる。おれは死にかかっている。前には光があったが、今は闇だ。前にはおれはここにいたが、今はあちらに行ってしまう! いったいそれはどこだ?」
ド直球な叫びです。作家なら誰でもコレ書きたいよね。文学が人間を描くことだとすれば、この叫びこそ真実の叫びだもの。なのにそういう作品がすくないのは、トルストイに先にやられちゃったからかな。
「こうしておれはしだいに深い淵のほとりに近づいていったのだ。だんだん力がなくなってくる。眼の中には光がなくなってしまった。つまり、死なのだ。」
「ところが、これは死なんだ。それはあまりに恐ろしいことである。」
痛い。おそろしい。どうなっちゃうのかわからない。でもそれだけ。それが『イワン・イリッチの死』で描かれた死でした。そこから先はブラックボックスです。大文豪にもわからないのでした。
「人間であるカイウスは死すべきものである。しかしそれは彼自身にはぜんぜん関係のないことであった。彼は他のものと異なる特異の存在なのだ。かれはワーニャであった。愛され、歓喜、悲哀、感激、こういうものに満ちたワーニャなのである。いったいカイウスが母の手に接吻したろうか? 恋をしたろうか? カイウスと同じように死ななければならないとは。」
またしてもド直球な感想です。好感がもてます。人間は生まれたときから、自分の目を通して世界を見ています。真の意味で肉体的実存感があるのは自分自身だけであり、すべての感情を経験しているのは自分自身だけであり、他人とは違う真に特別な存在です。その自分がその他の人と同じように死ななければならないとは。。。
仏陀は「その自分も塵芥のようなもの。諸行無常」と観相したわけですが、普通の人は「そんなことありえない。この私が死ぬなんて不条理だ」と考えます。それは公平で、けっして不条理じゃないのですが、そう感じます。死に理由なんてないのですが、必死に理由を探そうとします。そうでなければ納得できないからです。
ちなみにこれまでに私が聞いた死の理由で、最も納得のできたものは、個体は種のために死ぬ、というものでした。長く生きていると遺伝子のコピーミスが起こる可能性が増えます。コピーミスした個体が延々と繁殖しつづけると種族全体にエラーのある細胞がはびこってしまいます。だからまだDNAのエラーの可能性の小さい若いうちに次の世代をつくってしまうことが種族繁栄の利益であり、コピーミスの可能性の大きい老体は消える道を選ぶほうが種族全体にとって合理的だ。これがつまり死であるというのです。
仏陀のいう悟りとは、富や名誉といった外的要因にも、よろこびや満足といった内的要因にも、いちいち影響されないこと
なんとか生きようと頑張る。奇跡を望む病人心理
「健康、力、活気、生命、こうしたものを他人から見せつけられるとき、イワン・イリッチに侮辱感をあたえずにおかなかった。」
健康は空気のようなもので、なくしてはじめてありがたみを痛感できるものです。
「たとえどんなことをしてみても、さらに悩ましい苦痛と死のほかには、結局、どうもなりようはないのである。」
「阿片をお飲みなさいな。」
療養中もよくなる兆しがあれば耐えられますが、療養しても悪くなっていく一方だと心が折れてしまいます。
「早く落ちるところまで落ちてしまおうと思う。」
「もうこれ以上我慢しようとも思わず、子どものように声を上げて泣き出した。彼は自分の頼りなさを想い、自分の恐ろしい孤独を思い、人間の残酷さを思い、神の残酷さを思い、神の存在しないことを思って泣いた。」
「なんだってこんな恐ろしいいじめ方をするのです? 答えはない。あるはずがないのだ。再び痛みが襲ってきた。」
イワンは神に対して問いかけます。この問いに答えられるのは神しかいません。だからこそ神は「必要」だともいえます。
「さあ、もっと打ってください。しかしいったい何の罪なのです。いったい私がなにをしたというのです? なんのためです?」
「何を望むのか? 今まで生きてきたように、気持ちよく愉快に。」
生きのびたとしてどうなるのか? 何をするのか? 何のために生きるのか? そういうド直球なことをイワンは考えます。でも「気持ちよく愉快に」としか答えようがありません。「偉大な使命を成し遂げるため」とかではありませんでした。人間ってのは何かを成し遂げるために生まれてきたというのは幻想で、本当はただ生きのびるだけでいいのです。
子供のいない女性は無意味なのか? 生きること。人生の意味を問う格好の命題
人生の黄金期は幼年時代なのか。人間は無意味に耐えられない
「幼年時代。その時代が帰ってきたら、それを楽しみに生きていけそうな気がした。しかし、この愉快さを経験した人間はすでにない。それは誰か別な人間の追憶みたいなものであった。幼年時代から遠ざかって今の彼がつくりあげた時代に喜びと思われたものが、今の彼から見ると、その多くは汚らわしいものにさえ思われた。すべては依然として同じである。先へ進めば進むほど、いよいよ生気がなくなってくる。自分は山に登っているのだと思いこみながら、規則正しく坂を下っていたようなものだ。命が自分の足元から逃れていた。こうしていよいよ終わりが来た。もう死ぬばかりだ。」
「そんなことがあるはずはない。人生がこんなに無意味で、こんなに汚らわしいものだなんて。人生が無意味なものであるにせよ、いったいなぜ死ななければならないのだ? なぜ苦しみながら死ななければならないのだ? なにか間違ったところがあるに違いない。」
人間は人生の無意味さに耐えられないのです。
「その恐ろしい墜落と、ショックと、崩壊を待っていた。」
「逆らうわけにはいかない。しかし、なぜこんなことになったのか、せめてそれだけでもわかればいいのだが、それすらだめだ。」
悲痛です。それをカイウスやイワンのみの他人ごとととらえるか、自分ごとにとらえられるかで「あなた」の成熟度がわかります。
「自分の生活は作法に外れていなかった。それなのになぜ? 説明のしようはない。苦痛、死、……いったい何のためだ?」
「悩ましい肉体の苦痛。あっちへ行け。うっちゃっといてくれ!」
「なんともいえないほど恐ろしい叫び声。」
「彼はもうだめだと悟った。もう取り返しはつかない。最後がきたのだ。本当の最後が来たのだ。しょせん助からぬと知りながら暴れまわった。」
「自分の苦しみはこの暗い穴の中へ押し込まれることであるが、それと同時に、ひと思いにこの穴へ滑り込めないことにより多くの苦痛がふくまれている。生の肯定が彼を捕らえて先へ行かせまいとするために、彼を苦しめるのであった。」
ひと思いに死ねれば苦痛はなくなるとわかっていても死ねない、それが人間なのでした。
死ぬ前に気づけたことは、たわいもないことだった。
「つきそう家族。そうだ、おれはこの人たちを苦しめている。かわいそうだ。しかし、おれが死んだら、みんな楽になるんだ。」
「今まで彼を悩まして、彼の体から出て行こうとしなかったものが、一時にすっかり出て行くのであった。妻子をこの苦痛から救って、自分も逃れねばならない。」
「なんていい気持だ。そして、なんという造作のないことだ。」
「死の代わりに光があった。ああ、そうだったのか。もう死はおしまいだ。もう死はなくなったのだ。」
同時期に読んでいたヴィクトール・フランクル博士の書いた『死と愛』という書物にはこう書かれています。
「人間は最期の瞬間、内的な偉大さに達する。人生の意味を死によって得ることができる。今までの全人生をある意味に満ちたものにまで高める。自らの人生を犠牲にすることが人生に意義をあたえるばかりでなく、人生は失敗においてすら充たされうる。」
イワンがたどり着いたのは、家族に迷惑をかけている、かわいそうだ、自分が死ねば彼らの重荷が減る、という気持ちでした。
たったそれだけ?
そう思うでしょう。
たったそれだけです。それが大文豪トルストイの書いたことでした。ドストエフスキーだったらキリスト教の王国に救いを求めたと思います。
ドストエフスキーは今日の日本人にとっても本当に名作といえるのか?
そのぐらいしかないんですよ、きっと。
死ぬ直前の文豪にしかわかりえない人生の秘儀、そんなものは「ない」のです。
文豪にしか書けない「命の結論」「人間の生き方の隠された秘密」みたいなものは何もありません。
そのことはたくさん読書をしてきた今だからこそわかることです。
それを知るために、私は自分が死ぬ前に著名な書物をすべて読んでおきたいと思うのです。
自分の死に自分が納得するために。