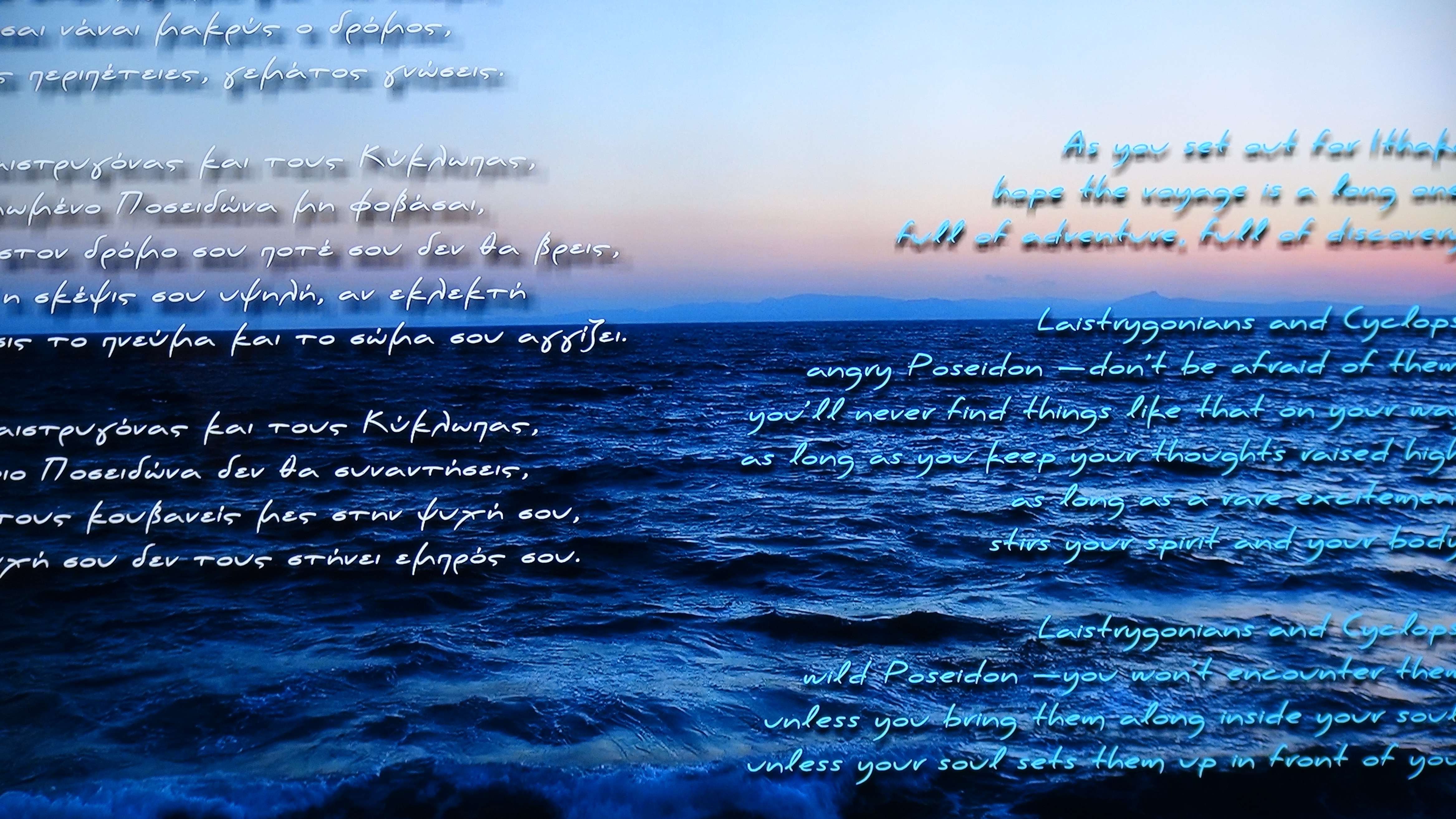第一章
天上から降りそそぐようにウェディングマーチが鳴り響いている。白いタキシード姿のツバサは赤い絨緞の上でアスカを待っていた。扉が開いて人の気配がした。カメラはすかさずそちらにパンした。白いウェディングドレス姿の女が現れた。
黒燕尾服の父親の腕をとって女はゆっくりと歩いてきた。一歩ごとに若さを発散させる肉体、清楚なウェディングドレスは奔放な人の心を抑圧するために存在しているのかもしれない。世の中を秩序づけ人の心を縛りつけるために。
キリヤがビデオカメラを構えてすっと脇に寄ってきた。白髪のきれいな男だった。キリヤがどんなカメラワークをするかツバサにはよくわかっていた。ツバサ目線のカメラワークで、じっとアスカの表情を追っている。伏せた睫毛が頬に落とした淡い影を、雪山の頂のような白い鼻を、果実のような唇を。
決められた段取り通りにツバサは父親の腕からアスカを受け取った。二人は足並みを揃えて待ち受ける牧師のもとへゆっくりと歩いていった。
通常照明がゆっくりと落とされていき、特殊照明ブラックライトに照らされる。ウェディングドレスがぼうっと暗闇に浮かびあがった。まるで海の底にいるかのような錯覚をおぼえた。二人は自ら発光する深海魚のようだ。二匹の深海魚は泳ぐように祭壇へと向かった。人間よりもはるかに古い生き物だと聞く深海魚もこのように結婚するだろうか。
結婚――その言葉を聞くとツバサの心は乱れた。幼い頃のことが思い出される。闇はそれにふさわしい舞台だった。脳裏に思い描かれた病室での心を病んだ母親の顔……愛する人と結婚さえしていたのなら母は死ぬこともなかったのだろうか。
昔、見た母の結婚写真、そこにまったく笑顔はなかった。やがて心を病み壊れてしまう自分自身のことを、そのとき母は予感していたのかもしれない。人形のように無表情だった母とは対照的に新郎だけがむじゃきな笑顔だった。その日の幸せゆえにのちに母を激しく憎むようになった男だった。
通常照明が灯ると、深海は再び地上の結婚式場へと姿を変えていた。まぶしさにわずかにツバサは目を細めた。現実へと引き戻される。
エメラルド色の瞳をした白人牧師が壇上からにっこりと微笑みかけた。やさしい目尻の皺、袖の大きな白い服を着て胸には黄色い十字架がさがっていた。カタコトの日本語で自分が結婚式をとりおこなうことを宣言した。荘厳な和音をかき鳴らすオルガンにあわせて式場専属の合唱隊が賛美歌を歌った。
「愛は辛抱強く親切です。愛はねたまず自慢せず思い上がらず……すべてのことに耐え、すべてのことを信じ、すべてのことを希望し、すべてのことを忍耐します……」
牧師がふたりに語りかけた。何度も聞いたこの一節をツバサはそらんじることができる。
「健やかなるときも、病めるときも、あなたはこの人を愛し、敬い、添い遂げることを誓いますか」
「誓います」
しずかにツバサは言った。その横顔をとらえていたキリヤのカメラ。フレームがアスカに移動すると、同じ言葉をアスカも誓った。
結婚。これが幸せとの契約だろうか。
寒い小さな北国の漁港、ツバサはそこで生まれ育った。荒れた海、降り積もる白雪、噛みしめた苦い思い出たち。腐った魚の死骸のようにあの町を捨てたはずなのに、何でこんな時に思い出すのだろうか。
ビデオカメラの前のヴァーチャルな世界、ツバサは虚構の中の自分に今でも違和感をぬぐい去れないことがある。街に出てきたときには、まさか自分がこんなことをやっているとは想像もしていなかった。しかし今では目に見えない何かの力に導かれてここにいるんじゃないかと思うことがある。何かの「流れ」が自分をここに導いたのではないか、と。
付添人に促されて、結婚証明書に万年筆で筆記体のサインをした。黒い文字。キリヤのカメラがぐっと手元に寄ってそれを撮った。ツバサが使ったペンを受けとり、今度はアスカがサインをした。細く優雅なサインだった。アスカはかつて精神科医になりたいと言ってツバサを驚かせたことがあった。
精神科医というものをツバサはよくは知らないけれど、どんなに学問を積んだって自分の経験していないことがらの真の境地を本当の意味において「わかる」などということは決してないだろうと知っていた。けれども導くことは可能だろうと思う。抱えた苦悩の真の境地はうかがい知れなくても、知らないならではの感受性で未知の世界へと導くことは可能だろうと思うのだ。
たとえば傷ついた者を救うのは同じ傷を負った者だとは思わない。人には状況に対する「反応」みたいなクセがあって、同じ場所に傷を持っていると同じ状況に同じ反応を無意識に繰りかえしてしてしまい、境地に広がりが足りないと思うのだ。病んだ心の真の境地を理解することはできなくても、傷つきやすい人の反応とは違った別の世界、可能性をさし示すことはできる。閉じられた一人ぼっちの世界とは異なった世界に他者を案内することはできる……それが信じられなければ、芝居などとうてい続けていくことはできない。
こんど公演される芝居を、ツバサはどうしても成功したかった。いいせりふを仕上げることができたと自分では思っている。
薄絹のベールをあげた。頬を染め、羞じらうアスカ。真珠のような肌、その頬にそっと口づけた。たとえ芝居とはいえ、あたたかいものが心にひろがっていった。プラチナのリングを白く細い指にはめた。アスカが手を戻したとき、夜空を流れる星のようにリングが白い光芒を描いた。
「カット!」
式場を切り裂くようなキリヤの声にツバサの思考は中断された。いつも稽古場で聞かされている声と同じ鋭さだった。緊張を吐き出すような吐息をついてアスカが笑顔を見せた。これで撮影は終わりだ。ツバサも緊張をといて大きく息を吐きだした。
「いい撮影だったぞ、ツバサ」
キリヤがツバサの肩を叩いた。家族や友人役を演じた役者たちが大きな拍手をしてくれた。
撮影されたビデオは、この結婚式場のPRのために、本当にここで結婚式を挙げるカップルたちにイメージビデオとして繰り返し披露されることになる予定だった。
「おつかれさま。また後でね、ツバサ」
アスカは耳元で囁いて控え室へと消えていった。その後を追いかけるようにツバサもゆっくりと控え室へと歩いて行く。芝居とはいえアスカと挙げた結婚式の余韻が体のどこかに残っていた。
控え室でタキシードを脱いで、Tシャツとジーンズに着替えた。撮影に使ったものはすべて式場の備品だった。私服に着替え、勢いよく控え室を飛び出した。ツバサはまだ駆け出しの役者だった。二十五歳になったばかりだった。ツバサはキリヤが主宰する劇団『ハート・ビート』の主要な役者のひとりである。
第二章
波のさざめきが、転がるようなピアノの音と重なったとき、ふたりは軽くキスをした。
膨れた雲をかかえた空色が、水平線にふりそそぎ、紫色に変わる。
やがて、あたりは朱に染まる……
女は男のTシャツに顔をうずめた。男の胸が奏でる切ないホルンを聴くために。
シャツからは今日の潮の香りがした。
女は男の髪をそっととかす。
地球が月を愛するように、満ちゆく波に応えながら、白く照らし出された指で、静かに彼を弾くために……
全身を汗で濡らしたアスカが、疲れ果てたようにかすかな寝息をたてて眠っている。しなやかな白い肩が布団から露わになっていた。
きみが望むならあげるよ。海の底の珊瑚の白い花束を。
ぼくのからだの一部だけど、きみが欲しいならあげる。
波は見つめあい、惹かれあい、次くる波へとその身をよせる。
きみの吐息で揺らしておくれ。
黄金色に輝く無数の光のかけらが、藍の闇に降り落ちていくと、きみとぼくもひとつになって、はじけて波間に溶けていった。
泡が笑う。
秘密だよ秘密だよ。
つられてぼくらも笑い出す。
愛してる愛してるよ。
月に照らされた海、エメラルドの星は瞬き、人魚の群と乱舞する。
銀の夜の、黄金の波。
あふれていくよ、あふれていく……
第三章
波打ち際に向かってツバサは砂浜を歩いていた。肩にかけた革ジャンの中にまで潮風が吹きこんできて体を冷やした。海辺の町に住んでいた。アスカはまだ部屋で眠っているはずだった。
朝の散歩が好きだった。空に鳥が舞うのを見上げるのが好きだった。雲が流れるのを見るのが好きだった。海のまぶしさに眼を細めてツバサは大きく深呼吸する。拳を何度か握ったり開いたりすると体の活力が呼び覚まされるような気になった。
幼い頃からいつも海を眺めていた。海を眺めていたときにだけ不思議と安らげた。
この海はあの故郷の漁港ともつながっている。水平線を眺めながらツバサは幼いころに思いをはせた。そしてこの海は南国の楽園の海ともつながっているのだ。
ツバサが敬愛した作家・ミナトセイイチロウが作品の舞台とした南洋の海。悠久の時の流れを語る珊瑚の白い化石。白い砂浜によせる透明に輝く海。熱帯の木々をゆらすさわやかな海風。
海の色はいったいどこで変わってしまうのだろうか。
ツバサの故郷では太陽を奪いあうように、人は人のぬくもりを奪いあっていた。互いに暖めあう、そんな誰もが「いい」と思えることを、人の集団はどうしてできないんだろう。
海岸の砂をすくって風に流した。まとまりのつかない思いのように、砂は散らばって流れていった。
潮の香りを充分に吸い込むと、心やすらぐことができた。
第四章
昔は倉庫として利用されていたという地下室。そこが劇団『ハート・ビート』の稽古場だった。パイプが剥き出しになった天井、雑然と置いてある大道具、小道具。照明や音響の装置。椅子や衣装。床にはガムテープが貼ってあり舞台と客席をわける仮想のラインになっていた。立ち位置や大道具の置き場所にもテープで目印がつけてある。年4回の公演は劇場を借りて行うが、舞台感覚をつかむため、借りる舞台の大きさに合わせてガムテープで稽古場を仕切って使っていた。本番の間合いをつかむためである。
本番さながらの通し稽古に入っていた。練習しているのは劇団のオリジナル・レパートリーだった。この芝居の成否にツバサはすくなからぬ責任を負っていた。芝居の台詞の一部を彼自身が書いていたからだ。
台詞が受け入れてもらえるかどうかはわからない。他人のセンスと合うかどうかは賭けだった。芸術というのは賭に似ている。同時代の同国人に受け入れてもらえなくても、外国や、未来の人に受け入れられることだってあるのだ。たとえ賭けでも、悔いのないもので勝負したい。ツバサは思う。いつわりのない魂を作品に込めよう。そうでなければ人の心を動かすなどできないのだから。
中央で椅子に座ってキリヤが役者の動きをじっと見つめていた。足を組み台本を二つに折り曲げて眺めながら、ときおり何かを書き込んでいる。
稽古場のすみで、ツバサは演技に備えていた。化粧衣装はお芝居の世界という非日常世界へと心を切り替える重要な装置だった。役者はメイクをしていくうちに役柄になりきっていく。ベレー帽を目深にかぶった。そして静かに出番を待った。
ガムテープで仕切られた舞台側ではアスカが田舎のお金持ち農夫の夫人役を演じていた。ふわりとした大きな帽子をかぶっている。白すぎる肌は夫人が健康でないこと、夫の仕事を手伝えないほど病弱なことを表現していた。濡れた声と潤んだまなざし。
出番が来た。ツバサは舞台に上がった。
画家『あの時期、ぼくは流れに同化しやすい感覚にあった。真実の恋に惹かれ、世界を翔けていきたいと願い、鋭敏な感覚に憧れ、極端な美に凝った。眼に見える世界の裏側には、見えない本質が何か隠れているのではないか、そういった感覚にとりつかれていた時期だった。眼に見えるものは急に何かに変化するんじゃないか。その実体の裏側には表裏一体、対極のものが潜んでいて、ふとした拍子にそれが垣間見えるのではないか。そんなイメージにとても凝っていた時期だったんだ。
何も持たなかったぼくが、君の感性は芸術だよ、と皆に褒めそやされ、自分自身もそんな感覚に酔っていた。ベールを被せた間引きされた上品さよりも、雑然とした、それでも人生に対する恋が肌で感じられるような色っぽさが好きだった。ある意味、人生を大事に思うけれど、ある意味、自分を大切にしない生き方、嗜好だったように思う』
自閉症の子供の家庭教師をする画家をツバサは演じた。子供の自閉にアスカが演じる夫人は悩んでいた。夫人はやがて画家に心惹かれていくようになる……。劇団の主宰者キリヤマサキのオリジナル作品だった。『画家と少年』という地味なタイトルだったが、内容は地味ではなかった。はじめツバサは画家の台詞の言いまわしを自分が言いやすいように変えさせてもらった。しかし何度かキリヤと話しあっているうちに「せりふの全部をおまえにやる。好きなように書きかえてみろ」と言われたのだ。だからツバサのセリフの部分だけはツバサが書いていた。
画家『人生には迷いの時期が必要だとぼくは思っている。迷いのない人は人間としての幅に欠けると思うし、その迷いは将来、役に立つとさえ思っている。
だけどあまりにも長い迷いは、ただ逃げているだけのような気がするんだ。もちろん長く迷いつづけた人たちの中から、将来の大物が出てくるかもしれないのだから、一概には言えないのかもしれないけれど。
確かにそういう時期はあると思う。でも年単位でやっている人って、ヒマ人というか、愚かというか、そんなことしてるうちにハッピーな人はもっと更にどんどんハッピーになっていってるというのに、どうして決断をしないんだろう。そんなにボンヤリできるほど人生は長くはないはずなのに。たくさん愛しあって、たくさん楽しんで、たくさんわかちあって、たくさん感動して、たくさん自分を謳歌して、たくさん自分を向上させなきゃならないのに。ハッピーな人達はそういうことを、同じ時間の中でどんどん積み重ねていっているのに、なんでわざわざ大切な時間を暗いもので覆うかな。
なんだかものの見方が逆さまじゃないか。どうして幸せなものを、わざわざ世間はそんなにあまくないと苦しくとらえ、わざわざ楽しめない生き方を選ばなきゃならないんだろう。しあわせの努力をしないで世間を厳しく見るだけなんて、眼を向けるところが違っているんじゃないか。しあわせの努力をして、そして実際しあわせになれば、世間なんて勝手に徐々にいい風景になるんだ。ぼくはそう信じている』
「おまえのセリフをおまえにやる。やってみろ」キリヤの言葉にツバサは勇み立った。うれしかった。期待に応えたかった。夜遅くまでせりふと格闘する日々が続いた。何度も何度も推敲した。せりふを自分でつくることがどんなにたいへんかを思い知る日々だった。台本をもらったときにはサラサラと書き流してあるように見えたせりふ。だがほんの数行のせりふを書き上げるためだけにまる一日を費やしていたこともあった。
画家が過ごしたはずの状況や場所、風景を脳芯が熱くなるほど思い浮かべ、経験したであろう思いや葛藤をできる限り想像し、自分自身の心に刻まれた似たような感情を想起してそれを再現する。役者はそうやって仮面をかぶる。劇中人物の心を魂で表現できるように。
役者が芝居を演じるためのそのやり方は、台詞を書く場合にも役に立った。
そうした役作りの課程で、人間の心というものの多くは状況や習慣が作り上げているものなのだとツバサは知った。どんな人物も心だけが独立して自律的であることはないのだ。
第五章
「ミカコは自分の中に湧いてくる予感とか流れとか、予知にも似たものを感じる人?」
ツバサの問いかけをミカコは不思議そうな顔をして聞いた。クラブを出て、朝までやっているワイン・バーに入った。むっとする熱気が部屋中にあふれかえっている。ワインレッドのテーブルクロス、同じ色の内装。血塗られたような真っ赤な世界。酔った頭がくらくらする。
「おれはそうだ。ときどき大きな流れの中に自分がいることを感じることがある」
ツバサの呂律はあやしくなっていた。ミカコは沖縄出身で単身上京して暮らしていた。もともとは劇団のファンのひとりで、今ではときどき劇団の手伝いをしてくれている。「それなら何か沖縄の海の話しを聞かせて」劇団の打ち上げで会話がはずみ、打ち解けた。それから仲のいい友だちとしてつきあっている。
「子どものころは雪なんて見たことがなかった。私たちまるで外国人同士みたいだね」
ツバサの故郷の海の話しを聞いた時、目をまるくしてミカコは驚いていた。荒れた灰色の海に降る白い吹雪。それがツバサの原風景だった。あれを知らない人もいるんだ……。
ツバサが憧れた作家、ミナトセイイチロウ。太陽と情熱の南洋の島々を、ツバサはまだ直接見たことはなかった。夢の場所、憧れだけの存在だった。いつかそこにたどりつけるだろうか。
「望みや決断ってその時々にはこれでよしと思ってするものだけれど、それが結果的によいことかは、運・不運というか、そのときの自分にはわからないよね。
そのときは望んでいないことが起きて思うようにいかずとても悲しんでいても、大きな流れの中では、それはそうなるべきことがらであって、結果的にはよい方向への布石だったりすることがある。そのとき自分が必死にその結果に反するものを望んでも、事態に否決されて、どんどん大きな力に自分が流されているなあと感じるときがあるんだ」
ツバサの生まれ育った家にはなぜか本があった。イラストのたくさん入ったミナトセイイチロウの海洋冒険小説。あれを手にしたのは単なる偶然だったのか。もしかしたらあれも流れの上での必然だったといえるのではないだろうか。
ミナトは海洋冒険作家といわれていた。海のロマンを描いた冒険小説をたくさんものにしていた。旅路の果ての歓喜と哀愁、そして海への果てしない憧れ……ミナトの小説の舞台はいつも海だった。それがどれほど幼いツバサに夢をあたえ、どれほど辛い現実を忘れさせてくれただろうか。故郷を旅立つ勇気をくれただろうか。
「幼い頃、よくひとりで海に降る雪を黙って眺めていた。ここから逃げ出したい、どこか遠くの誰も知らない場所へ行きたいといつもおれは願っていたんだ。
肌を焼く太陽と白い砂浜、まぶしいほどの海と熱帯魚が泳ぐ楽園を思い浮かべて現実からおれは逃避していた。おだやかな波音、肌を撫でる風、人々が水着で横たわる浜、おれにとってしあわせのイメージは南国の海とつながっている」
かじりつくようにして見た楽園の写真。同じ海だというのに目の前の海とはどうしてこんなにも違うのか不思議でならなかった。海の色はいったいどこで変わるんだろう。どうして自分は幸せから隔てられているのだろう。
「今だってそうだ。自分では意識しないのに、何だか周囲がどんどん変化してゆく。これまでの経験からも、きっと今がおれの人生の転換期なのかなと思うんだ」
自分を信じることができない人間が、この世界にいったいどんな希望をいだけるだろう。ありのままの自分を受け入れることができない崖っぷちの自我は、ときに爆発的に泣きだして周囲の人たちを傷つけた。
「いろいろな出会いと別れがあった。そんな中でおれは人にそった生き方だけではなく、自分自身の道を見つけだしたいなと願ったんだ」
将来に対する不安――隣でカクテルを飲んでいる気負いのないミカコをふっとツバサはうらやましくなることがある。ミカコはインターネットのウェブページ・デザイナーをしていた。企業のウェブサイトをつくる仕事だ。
「ウェブサイトづくりは、クライアントの要望を満たさなければならないので自由にならないことも多いんだけど、とてもやりがいのある仕事なの」
いつかミカコはそう言っていたことがある。彼女のつくったウェブサイトはとてもわかりやすく、色彩もレイアウトもそのデザイナーならではのセンスを感じさせた。コンピューターの知識があるというだけではつくれない、プラスアルファの感性が光っていた。クリーム色を主体にした目の疲れないフロントページ、ほんのちょっとしたアイコンの配置、枠取りが他のウェブページとはどこか違って気配りのセンスに満ちていた。同じ服でも実用の服とアートの服があるように、ミカコのはアート志向のウェブページだった。カネを貰ってこういう仕事ができるのか、とツバサはじっとパソコンの画面を見入ったものだった。センスで秀でる、というところは芸能の世界と同じだと思う。
「こうして南国の風の中で生きてきたミカコとも出会い、いろんな話しを聞けたことも偶然ではないのかもしれない」
夏の輝きをやどした黒真珠のような瞳。ミカコのようになりたい、出会った頃からツバサは心のどこかでそう感じていた。北海の荒波しか映さなかったおれの目には、きっと太陽のやさしさが足りないのだろう。
ミカコは収入の不安に煽られてはいない。その安定もとても憧れる要素としてあった。
「夢を追い、自分の道を見つけている人でもギスギスしていて、少しも幸せそうに見えない人がいるよね。いくら夢を追いかけるといっても、そのために苦しみ抜いたりするのでは駄目だ。夢とは自分が今以上に幸せになれるものでなければならない。しあわせを伝え、人と分かち合えるようなものでなければ駄目だ」
ミカコの顔を眺めながら、おさない頃の無邪気な空想をもう一度ツバサは思い出そうとしていた。そのおさな心がこれからの自分を助けてくれる、そんな予感がする。
「人生をマイナスから出発したおれは、これからもっともっとしあわせにならなければいけないんだ。いつか自由をつかむ、芝居で食っていけるならばそれが一番いい。けれど夢はひとつとは限らないだろう」
ミカコはツバサを見つめながらだまって頷いた。聞き上手な人だった。
「おれとは何者なのか。この世界でおれがなすべきことは何なのか? こうしてミカコとも出会えた。そして触発された。いろいろな出来事が身の回りに起きたけれど、結局、自分自身とは何なのか、何をすれば自分が一番気持ちがいいのか、一番大切なことはそれだけだという気がする。
そしておれはおれ自身になりたいな、と強く願った。人に憧れたりするのはもうやめよう、自分を憧れにしよう、自分で自分を実現しよう、と。
自分の本当に好きなモノは何か、自分が何を続けたら心から夢中になれるのか、そして思い出したんだ。太陽と海の楽園のことを……ミナトセイイチロウの小説を」
目と耳をじっと傾けてミカコは話を聞いていた。彼女に喋らされているように感じることがある。
「おれには自分の世界を夢として実現し、人生の上にのせたいという希望があったんだ。期待、かな。
人に誇れる仕事がしたい、それはたぶんおれにとっては勇気や愛を人に伝える感動をともなうものだ。流れる世界観の中で自分を表現してみたいんだよ。おれの好きな世界とは何だろう。ずっと何が好きだったんだろう。そして思い出したんだよ。海、それも南国の海だって――」
夢とロマン、それをビジネスを結びつけられたら最高だ。 芝居以外の収入をもつことで、芝居の世界でもより自由になれるのではないだろうか。仕事だけでない自分がほしい。
「本当に、何かができないかな……」
頭の中で考えながら、ツバサは呟いた。どうせ人はその人なりの感性で生きていくしかないのだ。だからおれはおれの感性を信じる。
「どうしておれはスキーに惹かれなかったのかな。やろうと思えばいくらでもやれた環境だったのに。
雪よりも太陽をおれは愛した。珊瑚礁の海、巨大なクジラ、体をくすぐる可憐な熱帯魚、海に溶け込むダイビングの浮遊感も、ミナトセイイチロウの海洋冒険小説も……」
そういえば好きになった女もどこか太陽の香りがする人ばかりだった気がする。
「けれどおれは、海が好きといっても、サーフィンをやるわけじゃない、泳ぐのが得意なわけでもない、イルカの調教師になりたいわけでもない、海の絵が描きたいわけでもない。
でも、海が好きだ。それを一生、どこかで感じて生きていられたら幸せだ。海、それはおれに幸福をもたらしてくれる予感がする。海、それも太陽に愛された海、それを感じると、おれの気持ちは解放されるんだ。
ただ波と夏の日射しと風を感じるだけでいいんだ。どこかで毎日、海を感じていたい」
本当に何かできないだろうか。海のようなロマンにあふれた仕事が。
ミカコと話しながらもツバサの考えは続いていた。頭の奧がむずがゆいような、何かが生まれるような予感がしていた。
第六章
ミカコは業務で会社のPR用のウェブサイトをつくるかたわら、自分の趣味のページをインターネット上に公開していた。『百円ショップでアイデア生活』という内容のページで、アクセス数を数えるカウンターは、驚くほどの人数がそのウェブサイトを訪れていることを示していた。
「お金にはならないんだけどね」
ミカコは笑った。だが本当にそうなのだろうか。それは儲けようという気持ちでやっていないからだけのことではないだろうか。
特定の場所に店舗を構えず、インターネット上で物品を売買し商売をしている人たちがいる。資本金が少なくても始められるサイバーショップという架空の店舗で、今後はこのような商売のあり方がますます発展していくだろうと予想されていた。そういう人たちが金を儲け夢を叶えた成功例をミカコからたくさん聞いていた。昔ながらの流通経路をもつ老舗の企業も今やこの販売ルートを無視できなくなっているという。
おれもなにか同じようなことができないだろうか。ミカコからその話しを聞いたときにツバサの血は騒いだ。夢をかなえた人たちの物語に、嫉妬のような感情がわきあがってきたのだ。自分にもできると思わなければ嫉妬という感情は湧き上がってはこないはずだろう。おれにだってやれる、と心が沸きあがった。だがおれに人に売るような何かがあるだろうか。あるとすればそれは物理的なモノではありえない。ロマンや夢、海への憧れとかアートとか、そういったものでしかありえないだろう。
またしてもツバサの心にミナトセイイチロウの小説が甦ってきた。ある日、海辺にすむ貧しい少年が、ボトルに入ったメッセージを浜で拾い上げる。書かれていた文字はどこかの外国の文字で読むこともできないが、少年は海の彼方の世界に夢をはせながら成長していく。やがて大人になった彼は憧れた海の彼方への冒険へと旅立ってゆくのだ……。
思い返すと、誰かに似ているなあ、と思った。誰だろうか。しばらく考えて、わかった。そうか。おれだ、おれに似ているんだ。
故郷を離れたときのことが、思い出された。
あのミナトの海洋冒険小説のような、人をロマンの冒険へと誘う夢、そういうものを売りものにすることはできないだろうか。夢とロマンが人の心にひろがっていくということは、苦労してでもやりがいのあることではないだろうか。それこそが自分ならではのオリジナリティあふれる商品といえるのではないか。
ワインバーでミカコと飲みながら、始発電車を待っていた。白いぶどう酒で下を濡らしながらツバサは考え続けた。
どんなイメージも結局はモノに託さなければならない。たとえば画家が画布に、作曲家が五線紙に、役者がおのれの肉体にそれを託すように。モノ、グッズ、ギフト……そこで自分が抱いた海への憧れを表現するにはどうすればいいのか。ただ商品を販売するだけでなく夢を売りたい。モノそのものではなく、あくまでもロマンを売るという意味では、商品販売というよりもむしろ芝居に似ているといえるかもしれない。芝居のチケットが売っているのは夢や感動だ、ブツではない。
やれるだろうか? ミカコと出会って海の話を聞いて、ミナトの小説を思い出して、おぼろげに見えてきた。やれるかもしれない、そんな気がする。何故、そんなことを考えさせる出会いだったのか。おれの人生という流れの中で、それは何か意味があることなのではないか。やれる。そんな予感が強烈にした。何かから背中を押されているような気がする。自由に羽ばたく夢を、めいっぱいに生きてみたい。ツバサの心に希望が躍った。
第七章
「やれるだろうか。どう思う?」
思いついたばかりのサイバーショップの構想を、ツバサはミカコに話して聞かせた。朝の街を駅へと歩きながら隣を歩く人に話しかける。この夢を最初に相談する相手としてミカコほどふさわしい人はいなかった。南国の島の出身で、ウェブページの専門家。むしろミカコと話していたからこそ思いついたのかもしれないのだ。
「南の島によせるおだやかな白い波のようなイメージがいいな……」
まぶしいほど星が輝く故郷の夜空。人の魂を屹立させるようなあの透明な夜風。南洋の島々でも夜空は同じだろうか。一度でいいからツバサは自分の目でそれを見てみたいと思った。楽園の夜空も星の色は同じなんじゃないだろうか。
「おれにはカネも技術もない。費やせるのはアイディアとセンスだけだ。資本はロマンしかない。最小の投資で最大の利益をあげるには頭を使わなきゃ。お金も決して借金はしない。騙したり、友人知人を頼ったひとりよがりのものではいけない。そして人に喜ばれるものでなくては。やることで自分が今以上の場所にステップアップしていけるようなものでなくてはだめだ。そして自分ならではのアイデンティティがなければ。
そして仕事というからには収入がなければ。趣味では続かない。収益があるからこそ真剣に考えるし、真剣に考えるからこそ本当に喜ばれ、関わった人に納得してもらえるものができるはずだ。多くの人に受け入れてもらうためには、表現方法も工夫しなければ。ときには自分を捨ててかからなければいけないこともあるだろう。そのひとつひとつが仕事とともに成長していくことだと思うんだ」
ツバサの言葉にミカコは何度も肯いた。
「おれは、根底に『こうなりたい』とか『こう生きたい』とか、前に進んでいく姿勢がない人とは話していても面白くないんだ。何故ってそういう人でないと、おれの本当の望みや、話したいこと、本音を理解してはもらえないから。
賭けてみようと思うんだ。たぶんきっとうまくいく。不思議なんだけど、そんな予感がする。ミカコはおれのことを楽天家すぎるって笑うかな」
あわててミカコは首を横に振った。だが心配する気持ちが目からのぞいていた。気持ちが手に取るようにわかってツバサは思わずふき出してしまった。
「そうだね……そうかもしれない。失敗を危惧するのは当然だろう。でも見ていて。きっとうまくいく。たぶんおれはいろいろな人に助けられる。そして大きくなれる。そんな予感がする。なぜだかわからないんだけど、すごくそんな気がするんだ。そのかわり本当に頑張らないと。本当に本当に頑張らないと。生半可で得られるものなど何もないからね。
こうしてきみに会えたのも、運命だと思うんだ。きみと知り合わなければ、サイバーショップなんて思いつきもしなかっただろう。やっぱり何かをうまくいかせるのって、決して一人ではできないことだから。自分の中のきれいな世界を仕事にしたいんだ。これがもう本当に最後のチャンスだという気がする。そして今、そういう流れが来ている気がする。
何で急にこんなことを思いついたのかな。流れが来ているということ以外、説明のしようがない。自分では意識しないのに、何だか周囲がどんどん変化してゆく。最近、事態が一定化しない。ものすごい速さで変わっていく。今までは流れがよどんでいて、何かの時期が満ちるのを待機していたみたいだ。
その大きな流れを見ていると、なぜか最終的に自分をいい場所に連れてゆく、その過程といった感じがするんだ。
こんなことそう度々あることじゃない。おれの人生の一コマしか見ていないミカコには想像しがたいことかもしれない。おれだって自分が体験していなければ感覚として実感できず、こんな話、いよいよ宗教めいてきたなあと思うよ。
でもきっと全てが上手く行くまでこの流れは止まらないって気がするんだ。何かの力が、おれを、おれが望んだ、おれの満足のゆく安泰の土俵に乗せようと大きな流れを作っている、そんな感じがするんだ」
ふたたびミカコの表情を覗きこんだ。そこにもう戸惑いや困惑はなかった。伝わった、と思った。
「やってみるよ。賭けてみる。たぶんうまくいく。不思議なんだけど、そんな予感がする」
危機本能がサイレンのように鳴り響いていた。もっとも大切なことは、たとえ片翼でも飛ぼうとすることだ。ここで飛ばなければもう飛べない。全てにおいて、やるなら今しかない。生まれ変わるのならば。
第八章
ツバサとミカコは駅のホームで電車を待っていた。こうして高い場所から朝の街を眺めるのがツバサは好きだった。夜の街とは違って人々がこれから活動をはじめようとする朝の街には、まだ消費されていないエネルギーがそこかしこにただよっているように思える。
「夢は明るく人をよろこばすものでなければならない。知恵をこねくり回したものではだめだ」
朝の気配の街を眺めながら、ツバサは頭の中のイメージを言葉にしようとしていた。
「そうね。いくら魅力的なものでも、感情が疲れるものはいつか面倒くさいなあと思っちゃうもの」
ミカコが小さくうなずいた。
「たぶん苦労するのは最初だけだ。軌道に乗れば、たいして時間も手間もかからずに済むはずのものなんだ。演劇人としても両立できる健全で幸福な仕事になるはずだ」
ツバサの顔を下から見上げて、ミカコは微笑みかけた。
「すごいね、ツバサは。さすがわたしが認めた人だけのことはある。あなたは曲がらずにしなやかに自分の世界を未来に向けて広げていける人だね。そしてひとりよがりでない真っ当な優しさを持っていて、それが自分を護る盾になることを心のどこかできっと知っているのよ」
遠くから電車がやってくるのが見えた。
「みずみずしくて繊細なツバサと、逞しくて本能的なツバサ。その対極の取り合わせが好き。圧倒されながらも見ていてドキドキするの。やっぱり人間も動物、本能が大事だもの。それは生命力であるし、統率力にも繋がると思うの。本能だけじゃなくクレバーだし、人とは違う何かをあなたは持っている」
ときどき自分のもっている自分のイメージとはまったく正反対のことを人に言われてツバサは戸惑うことがある。人の目に映る自分と自分の知っている自分、どちらが本当だろうか。どちらを信じればいいのだろうか。迷い、戸惑う。だが、おれはおれのままでやるしかない。
「楽しい、うれしい、といった人間の明るい感情を掘り起こして、その「先」に到達させてあげるんだ。その到達を手伝う仕事なんだよ。やりがいのあることじゃないか」
可能性という未来がツバサの胸に白く眩しい光を投げかけて踊った。
「つくづく思うよ、まだおれの終着点は見えてはいないんだなあ、まだ流れの途中なんだなあって。でもこの流れの実感が確かならば、一年後、二年後のおれは、きっと今よりもいい場所にいるはず。その先で今までの自分を超えて新しい何かに到達できる気がする。
いろいろな成功、いろいろな幸福があると思う。でも、こうして自分の手を離れたところから大きな流れを見ていると、なんとなくおれにはすべてがやがては調和し、融合していくような予感がするよ」
自分の夢でも見るかのようにミカコはじっとツバサの言葉に耳を傾けていた。そんな彼女にいつまでもツバサは自分の夢を語り続けた。
第八章
「ツバサ、次の新しいシナリオをいっそ全部おまえが書いてみろ」
稽古場でキリヤに突然そう言われた。想像もしていなかったことだったので、ツバサは頭が真っ白になった。脚本会議で次のシナリオのプロットは決まっていた。主人公は妊娠した女だった。
「なあツバサ、書くってことは自分の中の感情を呼び覚ましてしまうってことでもあるんだよ。おまえならわかるだろう」キリヤはツバサに語った。「創作するっていうのは、ときに危険なことなんだ。せっかく忘れていられた感情を書くためにむりやり呼び覚ますことで、安定していられた心をわざわざ葛藤の渦に放り込むことにもなりかねない。そしてそのことが時に実生活や対人関係をおかしくしてしまうことがあるんだよ。今度のシナリオの設定はおれには辛いんだ」
キリヤが言わんとしていることは何となくわかった。演技のメソッドとして、自分の過去の類似感情を呼び覚まして芝居に再現させるという方法がある。たとえば飼い犬が死んだときのことを思い出しながら、祖母が死んだときの芝居をしたりするのだ。自分が実生活で泣いたり怒ったりしたことを思いだして演技をする、そうすると迫真の演技となり観客の共感を得ることができる。
ところが呼び覚ましたリアルな感情が濃密であればあるほど、心が当時の錯乱した思いに戻って掻き乱されてしまうのだ。愛犬をなくした当時の感覚に今の現実がかき乱されてしまうことがある。ツバサのようなキャリアでさえもそのようなことが過去に何度か起こったのだ。役者のメソッドと同じことが作家の身に起こったとしても何ら不思議なことではないだろう。
「おまえを買う。失敗してもいい。やってみろ」
ツバサの決意や自信を確かめるように、キリヤはじっとツバサの目を見つめた。まるで本当の父親のようにいつでもキリヤはツバサの背中を押してくれた。この人の期待に応えたい。そう思ったからやってみることにした。自分にできるかどうかはわからない。でもやるだけやってみよう。
脚本を書いたことはない。何かを表現するという意識でツバサは身の回りを眺めてみた。すると突然、世界が別のものになったように思えてくるから不思議だ。
第九章
カプチーノを淹れよう。きみが待っているから。
カプチーノを淹れよう。明るい陽差しの中、きみが微笑むから。
ぼくの人生のスケッチは、まだ未完成だけど。
裏の畑の麦の穂は、まだまだ蒼いままだけど。
大地に立っているこの存在を、実感していたいんだ。
カプチーノを淹れよう。きみとぼくのために。
カプチーノを淹れよう。きみの巻き毛の黒髪が四月の風に揺れるから。
「こっちを見ないで。鏡の中の私を見て」
汗をかいた裸の背中が言った。
「会いたかったよ」
「会うだけでいいの?」
アスカは髪をとかしている。
「キスしたいよ」
「キスだけでいいんだ」
ツバサは笑った。
金色の波をすべるあなたは、まるで海に浮かぶ星のよう。
夕日を背に浴び、きれいな軌跡をえがいて還ってくるの。
夢みるように何度も何度も、波を泳いでわたしのもとへ。