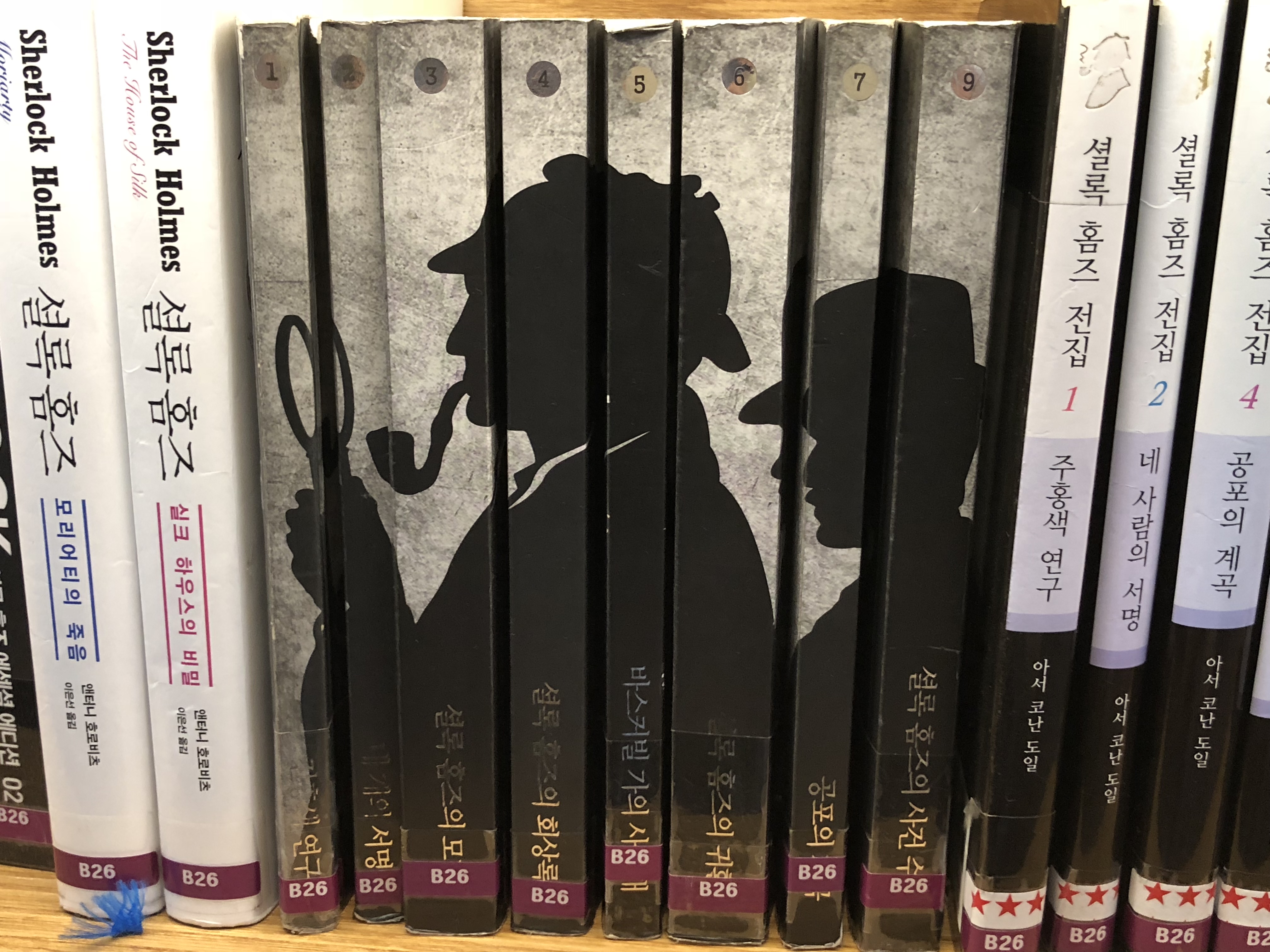わたしのドストエフスキー読書履歴
しつこく、ドストエフスキーを読み進めています。
ドストエフスキー『死の家の記録』シベリア獄中記のあらすじと感想
ドストエフスキー『貧しき人びと』どのへんが名作なのか? あらすじと感想
ドストエフスキー作品の読み方(『カラマーゾフの兄弟』の評価)
ドストエフスキー『罪と罰』の低評価。小説界のモダンアートだったのではないか?
カラマーゾフの兄弟『大審問官』。神は存在するのか? 前提を疑え!
人とうまくやっていけないために地下室に逃げ込んでいる主人公の自意識過剰
この小説はタイトルの通り、世を捨てたポーズをとって地下室で暮らしている男のヒネた自我を描いた小説です。隠者のようなのはポーズだけであり、実際には人とうまくやっていけないために地下室に逃げ込んでいるような人間です。地下室人は人と関わることを極度に恐れる対人恐怖症です。19世紀のロシア版オタクです。
鴨長明や吉田兼好のような隠者とはまるで違ったことが書いてあります。
ガンつけ合戦。おまえはヤンキーか!?
主人公(地下室人)は、学校を出ると学校友達と速攻で絶交してしまいます。みんなから毛嫌いされているのではないかという疑心暗鬼からでした。
役所で小役人の仕事をしていたのですが、同僚のことを軽蔑しています。職場の連中は、羊の群れのようにお互い同士そっくりでした。鈍感で、話題といえば税金のこと、仕事のこと、給料のこと、昇進のこと、上司の噂、出世の方法のことといったところでした。
同僚を憎み、軽蔑し、同時に恐れて、崇めていました。そんな臆病な自分に地下室人は虚勢をはります。人と目があっても目を伏せてしまう自分が嫌いで、先に目をそらさないようにケンカ腰にさえなります。ガンつけ合戦です。おまえはヤンキーか?
小役人が地下室人になった経緯。自意識過剰
そんな地下室人のことだから、付き合いは仲つづきしません。地下室人にとって愛するとは暴君のように振る舞い、精神的優位を確保することでした。愛を闘争以外のものとして考えたことはありませんでした。
だから友人ができても、彼が自分の支配下にはいると、たちまち彼を憎みはじめ、彼を突き放すようになります。地下室人が必要とするのは、他人に勝利し、屈服させるためだけであるかのようです。
地下室人は、同じ集団の中にいても、自分だけが臆病者で奴隷のような存在だと感じています。自分だけが特別と思いつつ、強烈な劣等感ももっています。それゆえ周囲に無関心の態度をとります。他人に対し嫌悪の情を見せるのです。
仲間に入る勇気も才覚もないので、自分から先に他者を見限ります。彼らと一緒にいたくない、ひと思いに縁を切ってしまいたい、と。
役所の人たちは、人を知性や感受性ではなく、服装で判断するようです。服が汚れているだけで、品位の十分の九は吹っ飛んでしまうのです。そんな同僚を俗物と軽蔑しつつ、おのれの心のいやしさに気づかれまいとし、外面を飾りたてようとするような人物でした。
周囲を憎み、絶縁し、人一倍敏感でおびえやすい男でした。傷つけられた自尊心の殻の中に、すなわち地下室に、地下室人は閉じこもってしまいました。友人たちと絶交し、あいさつすることもやめてしまいます。いつもひとりでした。たいてい本を読んでいました。読書以外には、尊敬できるもの、心を惹かれるものが何もなかったからです。
すれちがいざま、どちらが先によけるかというチキンレース
自意識過剰な地下室人は、道で人とすれ違う時に、いつも自分が道をよけてばかりだと感じていました。だからせめて見下していた友人には道を譲るまいと精いっぱい肩ひじを張ります。すれちがいざま、どちらが先によけるかというチキンレースです。おまえはヤンキーか!?
そして友人と肩がぶつかるまで我慢すると、向こうは何とも思っていないのに、チキンレースに負けなかったことに満足するような卑小な人間でした。
昔の友人を無理やり訪ねてバカにされる
地下室人は臆病者と思われるのが嫌だったので、無理やり昔の友人の出世お祝いパーティーに出席することにします。しかし自意識過剰な彼はすなおに祝意を表明できません。かっこつけて、滑稽なほど嫌われてしまいます。
まずは開会時間が変更になっていたのに、地下室人は教えてもらえませんでした。それに恨みの気持ちをいだきます。さらに「なんであいつが来るんだ」と言われます。それに対して地下室人も負けていません。逆に友人たちに冷笑を浴びせかけます。現実世界を理解していた友人たちは世間的な成功だけに目がくらんでいました。普遍的な正義などは認めません。世論に辱められ、虐げられている人物には、迎合して冷酷な嘲笑を浴びせるような俗物でした。浅薄で、ばかばかしい会話。理解がなく、感動がなく、驚嘆がなく、関心がない彼らを自分より一段下の人間だと地下室人は見下します。
地下室人が学校にいた頃、彼が彼らの誰にも似ていないという理由から、意地の悪い容赦ない嘲笑を浴びせられたという恨みをもっています。自意識過剰なので、仲良くなるタイミングが来ても、安っぽくうまをあわしていくこともできず、友情関係を構築できませんでした。
お呼びじゃないのに、そんなところにわざわざ出かけたことを後悔します。友人たちも同じ仕打ちで地下室人にむくいて、嫌悪をかくそうともしませんでした。
帰るそぶりを見せると邪魔者がいなくなったとばかりに喜ばれます。だからなおさら帰るまいとするのでした。
友人の門出のスピーチに、地下室人は侮辱の言葉をぶつけます。友人たちは逆上しました。
「畜生。たたきだせ」「こんな男を仲間に入れちまって恥ずかしいよ」
総スカンをくらって徹底的に無視されます。それに対して平然としたポーズをとりつつ、友人たちが先に話しかけてくるのをじりじりしながら待っていました。ひたすら壁際を三時間も歩き回って。しかし最後まで相手にされませんでした。
自分からケンカを吹っかけたのに、仲直りを熱望しているのでした。
地下室人はそんな矛盾した存在でした。
どうして自分が憎まれ、友人が愛されるのか、わからない
出世していく友だちはみんなから好かれているようでした。
<どうして。どうしてだろう?>
自分が嫌いな友人たちが周囲から好かれている理由が地下室人にはわかりません。そのことは四十年前からずっと変わりませんでした。
<ぼくがどんなに知的に発達した人間か思い知らせてやれたらなあ>
いまさら自分を認めさせようと意地をはります。自意識過剰から、好かれている友人にケンカを吹っかけることを妄想します。
彼の妄想が現実になったら、役所勤務どころではありません。逮捕され、裁判にかけられ、勤めを追われ、監獄に入れられて、シベリア流刑になるでしょう。ところが地下室人はひそかにそんな屈辱を受けることをのぞんでいたのでした。
売春婦を説教して自分に惚れさせようというオッサンのような真似をする。
友人たちに受け入れられなかったので、売春宿で女を買います。そこで売春婦を説教して自分に惚れさせようというオッサンのような真似をします。
「こんなことしてていいと思っているのか? 自分を大切にしろよ」というやつです。だったら女を買うなっつーの。
「世界なんか破滅したって、僕がお茶を飲めればそれでいいのさ」
英雄を気取って、地下室人は売春婦にいいはなちます。しかし実際の地下室人は貧しく、下男にすらバカにされています。英雄どころか乞食も同然でした。
その姿を売春婦に見られてしまいます。虚栄心がズタボロでした。ぼろぼろの部屋着姿を見られたことを一生根に持つのです。他人に涙を見られたことを許す気になれません。
生々しい真実の告白も聞かれてしまいました。そのことが許せないのです。彼女に跪くことで、彼女を憎むようになるのです。虚栄心が傷つくからです。
それが地下室人という男でした。醜悪で、こっけいで、嫉妬深い虫けら。そして生涯、しらみ同然の奴らから小突き回されているのです。
賢さを自負し、地下室で読書に励んでいましたが、なにを尊敬し、なにを軽蔑すべきかも、わからなくなってしまっているのでした。
遭難した人に「どうして遭難してしまったのですか?」と聞くようなもの
これほどの卑屈なクズ男を私はこれまでに小説で読んだことがありません。しかしまったく未知の生物かというとそうではありません。正直、身の回りに、こういう人物がいます。みなさんのまわりにも一人ぐらい、地下室人のような人物がいるのではないでしょうか。
目をそらしたくなるようなそんな人物のことを、日の光の下にさらけ出しているのがドストエフスキー『地下室の手記』です。
英雄の心を解き明かそうとする物書きはたくさんいますが、ドストエフスキーがやろうとしたのは正反対のことでした。
身の回りで見たことがある、嫌われ者の一典型である人物のことを、地下室人に託して、ドストエフスキーは描いてみせたのでした。
それは遭難した人に「どうして遭難してしまったのですか?」と聞くようなものです。それが答えられるのなら遭難なんかしていません。「どうして君は人に嫌われるような行動ばかりとるんだい?」そう聞いてみたくなるような人がいますが、この問いは無意味でしょう。彼らには答えられません。なぜなら、人に好かれようとして、愛されようとして、そんな行動をとっている可能性すらあるからです。わかっていないから、そうなってしまうのです。そうとしか行動できないのです。落とし物をした人に「どこで落としたんですか?」と聞くようなものです。それがわかっていたら、その場で拾っているはずではありませんか?
『地下室の手記』はそんなことを考えさせられる小説です。