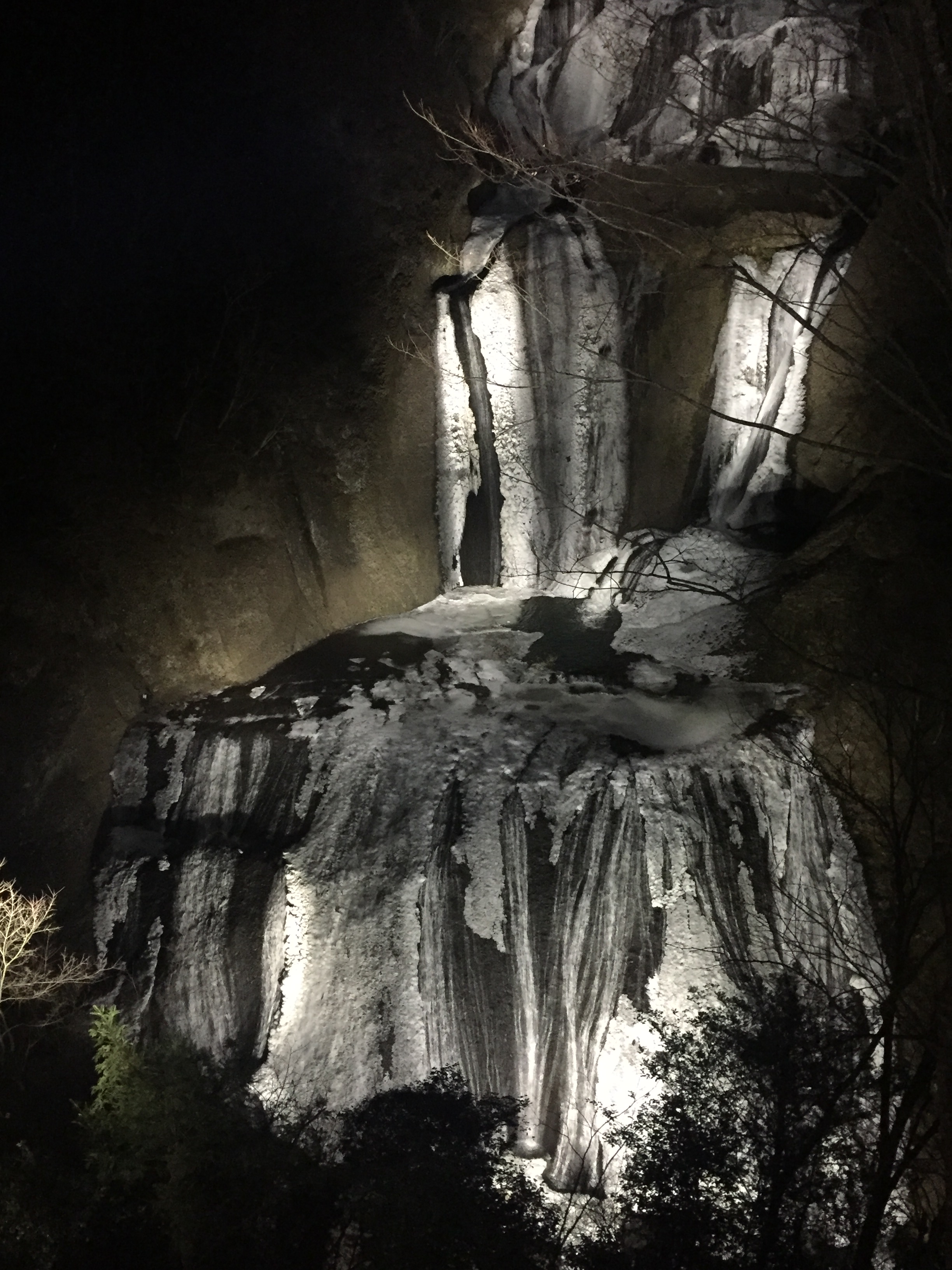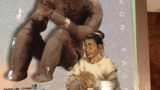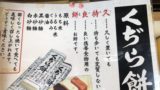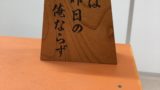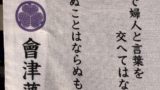このページでは平成が令和に変わる平成31年4月26日から令和元年5月6日にかけてのゴールデンウィークに桜前線を追いかけて東北地方桜旅を車中泊大遠征10泊11日した時の記録をまとめたものです。
(結論)「桜前線なんてものはテレビの中にしか存在しない」
みなさんもこの記事で同じ体感をしてもらえたらと思い、たくさんの桜写真をアップしています。
また、車中泊の長期遠征というものがどういうものなのか。参考になればと思っています。
読んでいただきたいネタは、
・ゴールデンウィークの大渋滞に巻き込まれない方法
・上杉謙信の関東遠征に雑兵が従ったのは豪雪・避寒のため(新説)
・五能線ミステリー。お岩木山は二度あらわれる。
・三内丸山縄文遺跡は世界遺産間違いなし。
・玉川温泉はもっと世界的に有名な場所になることができる。
などでございます。
さあ、出発しましょう。忘れ物はありませんか?

桜を追いかけて車中泊大遠征1日目。冬と春の境界線を越えて
昭和の終焉にも立ち会った私ですが、いよいよ平成が終わろうとしています。
ゴールデンウィークの車中泊大遠征は3年連続です。
ずっと続けてきたゴールデンウィークの海外旅行をこのところずっとしていません。
それほどこの車中泊の旅が面白いということです。
ある意味、海外旅行以上に面白いと感じます。
いいね。車中泊。
1年目は山陽地方。2年目は山陰地方でした。
今年は桜前線を追いかけて東北地方を北上していきます。
旅先で本ブログをリアルタイムに更新していきます。
その後、家に戻ってから詳細を書き込んで完成させる手はずです。
しかし今回は国内です。auが圏内である限り問題ありません。
平成31年4月26日(金)車中泊1日目
明日から史上初の10連休で心をときめかせていると思いますが、私たち夫婦(ハルトとイロハ)は有給休暇をいただいて、一日お先に出発です。
一日早く出発するのはもちろん連休の渋滞を避けるためです。
大都市圏さえ抜けてしまえばゴールデンウィークGWといえどもさほど渋滞しないのは過去2年の経験から感じているところです。
ゴールデンウィークの大渋滞に巻き込まれない方法=登山のノウハウを活用する
千葉県の自宅を午前3時に出発します。
渋滞に巻き込まれたらそこで時間を取られてしまいますので、出発と帰宅の朝は思い切り早起きして行動しましょう。
快適なGW旅のためにはここが踏ん張りどころです。
ゴールデンウィークの車の大渋滞を避けるためには、登山のノウハウを活用します。
たとえば北アルプスの山々を縦走するとき、ほとんどの人は休暇日が同じで、同じ早朝バスでアクセスポイントに移動して、同じルートを同じペースで登るため、自然を味わいに来たのに周囲には同じ人ばかりということがあります。
山小屋などは大渋滞。いびきのうるさいオッサンと肩が触れ合うようにして寝ないとならないことも珍しくありません。
GWの大渋滞と実は同じ状況です。
これを避けるコツは初日に大多数の人が行けない『次の山小屋』まで登ってしまうことです。
早朝のバスが上高地のようなアクセスポイントにたどり着いたら、ヨーイドンでスタートダッシュをかけて大多数の人の泊まる山小屋の『次の山小屋』まで行ってしまうのです。
みんながトイレに行ったりストレッチしたりしているすきに、予め準備をすませて先に先にと登ってしまいましょう。どんな人間の集団も先頭は空いています。
みんなが泊まる山小屋よりも先にある『次の山小屋』まで歩いてしまいましょう。
『次の山小屋』は空いています。
頑張るのは初日だけ。
次の日からはみんなと同じペースで歩いて構いません。
みんなが同じペースで移動すれば、混んでいる人はずっと混んでいるし、空いている人はずっと空いているのです。
ゴールデンウィークの旅も同じです。
朝にスタートダッシュをかけて大都市圏を抜けてしまえば、後はずっと空いているのです。
登山の縦走の場合は健脚にものを言わせて渋滞を抜けるのですが、車の場合は早起き早立ちがものをいいます。
登山用のザックは車中泊の旅に向いていない

後部座席の様子。乱雑に積んであります。寝るときは前のシートに移動させます
今回の車中泊の装備はこちらです。
左下に見えるのは登山用のアタックザックです。
これは大失敗でした。寸胴の登山用ザックはずっと背負っていることを前提に設計されています。
重たい荷物を長時間快適に背負うための設計なので、それ以外のことは犠牲にされているのです。
具体的には「荷物の中身が見えない」「必要なものが取り出しにくい」という大欠点があります。
車中泊の旅のザックはボストンバックのような開いて中身が確認できるタイプのカバンが向いています。
ボストンバックは登山には全く使えませんが、車中泊の旅では鞄を持ち上げる場面はほとんどありませんし、むしろ荷物の中身が見えるため取り出しやすいメリットの方が大です。
登山用ザックは必要なものがザックの最下部に入っていたりすると、取り出すために中身を全部ぶちまけなければならないことがあります。非常に不便です。車泊には向いていません。