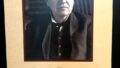葬儀代行会社は遺族の足元を見て儲けすぎだと思う。

昔、祖父が死んだときの話しです。もちろん、お葬式がありました。大手の葬儀会社と契約して、すべてを取り仕切ってもらいました。結婚式なら時間をとれるから自分で調べて自分で取り仕切ることができますが、葬式はそうはいきません。遺体は腐るし、火葬場の予約はあるしで、日程はたいていタイトです。ほとんどの人が葬儀会社に頼むのではないでしょうか。
遺族は自分の配偶者、父親、祖父をなくしているわけですから、悲しみにくれています。肉親の死という大きな事実を前にして途方に暮れています。
だから葬式を取り仕切ってくれる業者がいるということは、理にかなったシステムだと思います。
ただ儲けすぎだという気はします。冷静に考えると、葬儀代行業者の値段は高すぎると思いませんか?
遺族側の足元を見ているとしか思えません。
葬式というのはし「しきたり」があり、それを逸脱すると「なんだあの家は」と悪い評判を立てられます。だから「しきたり」に従うのが無難なのですが、そのノウハウが遺族にはたいていありません。「しきたり」を学んでいる時間もありません。遺体は、腐ります。時間勝負です。
そこへきてどうせ費用は死んだ人の財布から出るとなると、お金なんていくらかかってもいいというのが、葬儀業者のつけいりどころなんではないでしょうか。なかなか葬式で、適正価格に値切ろうという気にならないですよね?
死んだ人が、自分のために自分のお金を使える最後の機会ですから、いっそ全財産をつかってもいいぐらいの感覚になりがちです。
いずれにしても人の死はばく大なお金が動きます。
「花入れの儀」。しきたりにこだわりすぎると形式主義におちいる。
 その祖父の葬儀でのことです。長年つれそった祖母は生きていて、祖父の死を悲しんでいました。とはいっても祖母ももう高齢です。
その祖父の葬儀でのことです。長年つれそった祖母は生きていて、祖父の死を悲しんでいました。とはいっても祖母ももう高齢です。
老婆ですから、悲しんでいるといっても、そんなに感情表現するわけでもなく、ただ疲れ切っているという感じでした。
名目上の喪主ですが、ほとんど何もできない、という格好でした。娘であるうちの母が実質的な喪主代行をつとめていました。
さて、いよいよ出棺です。最後のおわかれです。家族は遺体と対面し、最後のお別れをします。
そのときに、これまで感情をあらわにしなかった祖母が顔をくしゃくしゃにして泣きだしました。驚きました。その顔を見てわたしもグッとくるものがありました。
自分たちの若い頃のことや、これまでのふたりの思い出などを、思い出していたのだと思います。
今生の別れに、祖父の顔を眺めて、泣いている祖母。
その祖母の肩を、葬儀社の人が叩きます。
「これで最後だからたくさん花で飾ってあげなさい」
そういって花を手渡しました。
祖母は見知らぬ他人に声をかけられて、泣いていたのがフッと我に返りました。泣き止んで、指示されたとおりに、花を棺に入れます。そりゃあ他人様に声をかけられたら、われを忘れて泣いているわけにもいきません。
出棺のときには遺体を花で飾るというのが葬儀のしきたりのようです。「花入れの儀」というそうです。
祖母は祖父の遺体に花を手向けると、またさっきの続きとばかりに、祖父の顔を見て泣き始めました。
するとまた泣いているタイミングで、葬儀社の人が花を持ってきて、喪主である祖母に声をかけます。この人は遺体を花で飾ることが、何よりも大切だと考えているようでした。
〈ああ、邪魔しないで、思うぞんぶん泣かしてやればいいのに〉
わたしは、思いました。
最後の別れです。今まで感情を表にしなかった祖母が最後の別れに泣こうとしているのに、いちいち葬儀社の人間が花を渡しに来るために、そのたびに気持ちが中断されて、とうとう祖母は泣くに泣けませんでした。
残された遺族が、故人を花で飾るというのが「しきたり」なんでしょうが、それほど重要なことでしょうか。祖母が、遺族が、思い出にひたり泣こうとしているのを邪魔するほど大切なこととはわたしには思えませんでした。
「しきたり」にあまりにもこだわることは、形式主義におちいります。
出棺の時、遺族がしたいのは、遺体を花で飾ることではなく、最後の別れを告げること。

花で飾るのは、葬儀社の人がやればすむことです。やりたい遺族がやればいいのです。
あるいは最初から遺体を花で飾っておけばいいではありませんか。
出棺のとき、最後の別れをする瞬間、遺族がしたいのは遺体を花で飾ることではなく、顔をみて最後の別れを告げることではないでしょうか。
祖母には思い出にひたって、思う存分泣かしてやりたかった。
わたしはそう思いました。
しかし葬儀社の人は、用意した花をすべて棺に入れることを義務と思っているのか、執拗に祖母のところに花をもってきて、花入れの儀をやらせようとするのです。
祖母が泣こうとするたびに、葬儀屋が花を持ってきて〈泣く行為〉が中断されてしまいます。
「たくさん花で飾ってあげなさい、最後ですよ」と理屈はわかりますが、次から次へと花を祖母のところに持ってくるのです。その行為に中断されて祖母は泣くことができません。
とうとう祖母は泣き止んでしまいました。
知らない人に何度も声をかけられて花入れのノルマを課せられては、思い出にひたる暇なんかありません。だれだって涙をひっこめてしまうでしょう。
ああ。こういうところが大手の葬儀会社の駄目なところだよなあ。形式主義、流れ作業になってしまって、人が悲しんでいることが(あまりに慣れ過ぎて)わからないんだなあ、とわたしは思いました。
すこしでも故人の顔を見ていたいと願う気持ちを、花入れの儀が邪魔をする。

花入れの儀、の花は葬儀社が用意したものです。もちろん葬儀費用の中に入っています。花はやがては枯れてしまうので、一緒に燃やす以外に他に使い道はありません。そのために用意した花だからすべての花を棺に入れないかぎり、セレモニーは終わりません。
ところがウチの遺族たちは、みんな故人の顔を見て語りかけるばかりで、花を入れるという行為にはあまり協力しませんでした。そんなにどうでもよかったわけです。花は遺体からちょっと離れた場所にあり、それを取りに行くには、故人から目を離さなければならないからです。
最期の瞬間に、すこしでも故人の顔を見ていたいと願うのが遺族の切なる願いです。だから花を取りに行かなかったんだと思います。
ところがそれでは葬儀は終わりません。だから葬儀社の人はいちばん目につく喪主に花をジャンジャン渡して、花入れの儀を終わらせようとしたのかもしれません。
でもわたしはその葬儀社の行為を非常にマイナスに評価しました。
喪主が忙しすぎて悲しんでいる暇がない日本の葬式。
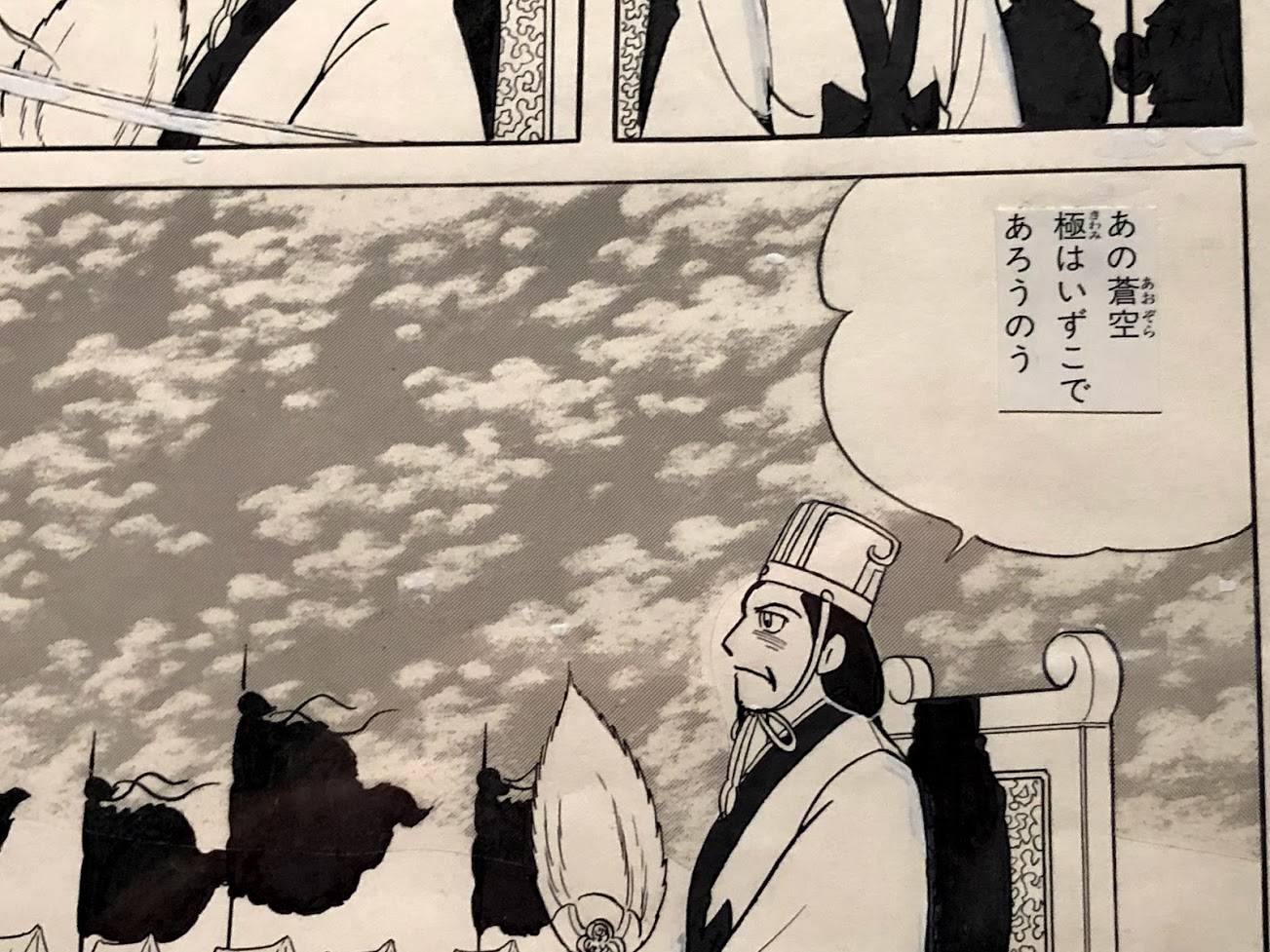
ところで「日本の葬式では喪主が忙しくて悲しんでいる暇がない」とよく聞きます。その言葉は、たいてい悪い意味ではなく、いい意味で使われているようです。
つまりあまり悲しむと体に毒ですし、あまりにも死者との思い出に寄り添うと、死者に引かれて後追い自殺ということもありえるからです。
だから忙しくしていると悲しい気持ちもまぎれるという意味で、喪主が忙しい「しきたり」をマイナスではなくプラスだと評価する人がいるのです。
いちばん悲しいときに、忙しくて悲しみ過ぎないことが、いい意味で語られるのならば、もっとも祖母が感情をあらわにした「最後の別れ」のシーンで、花を渡しまくって泣くのを邪魔しまくった大手葬儀社のアレは、ひょっとしてプロの気遣いだったのかしら? なんて思ったりすることもあります。
あれは悲しみに引かれて死者との思い出によりそい、自殺しないための心づかいだったのかな、と今では思うのです。
過ぎ去ったことはいいようにとらえるという人間の通弊で、よく捉えすぎでしょうか?
あのとき、泣こうとして泣き切れなかった祖母も、今ではもうこの世にいません。