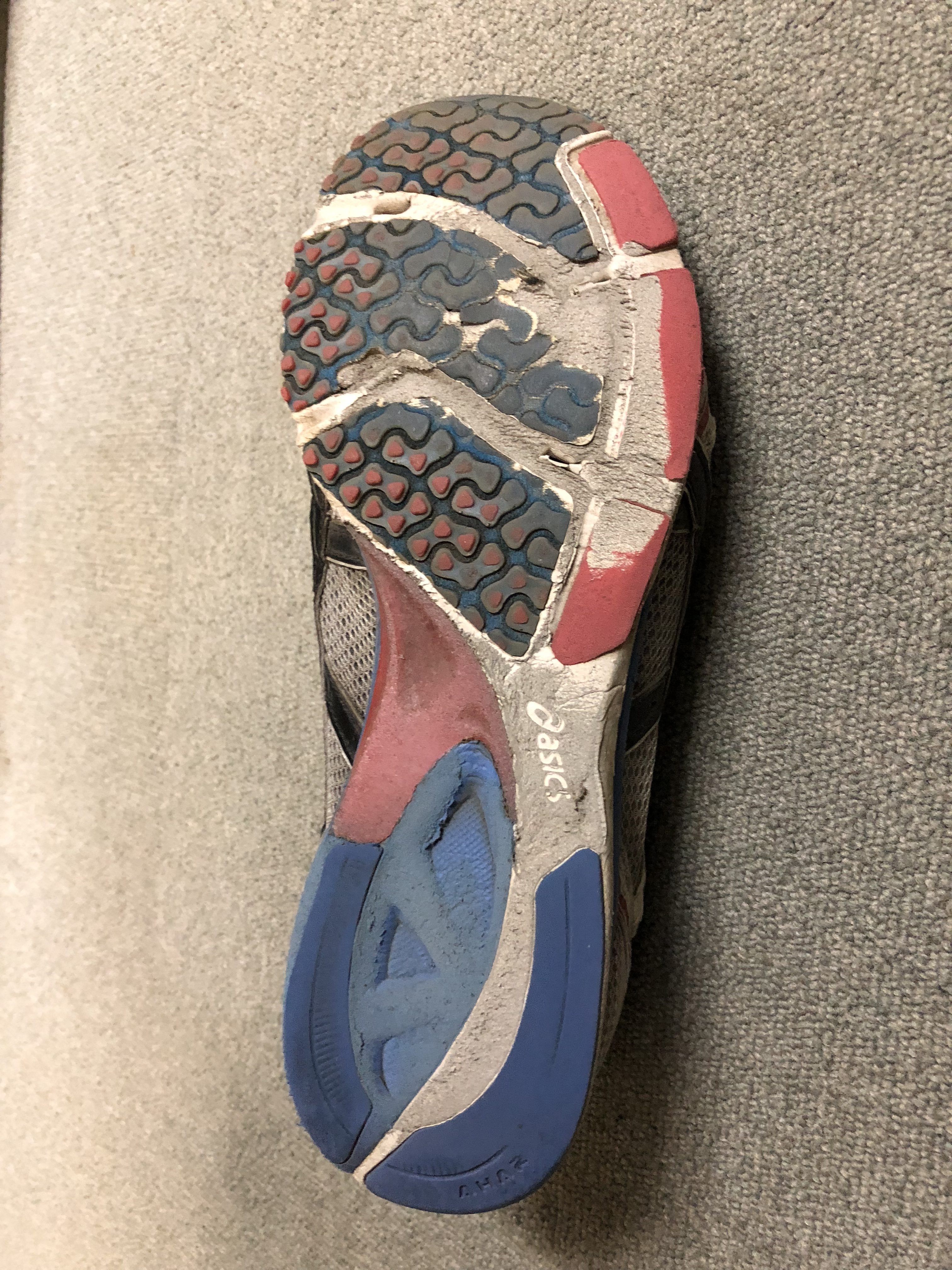どうもハルトです。みなさん、今日も元気に走っていますか?
ここではランニングにおける脱力の重要性。そして脱力は技術で習得できるということを書いています。
× × × × × ×
※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?
いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。
●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」「かかと落としを効果的に決める走法」
●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?
●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。
●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。
●腹圧をかける走法。呼吸の限界がスピードの限界。背の低い、太った人のように走る。
●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?
●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」
本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。
あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。
× × × × × ×
どんなレースに出ても自分よりも速くて強いランナーがいます。それが市民ランナーの現実です。勝てないのになお走るのはなぜでしょうか? どうせいつか死んでしまうからといって、今すぐに生きることを諦めるわけにはいきません。未完成で勝負して、未完成で引退して、未完成のまま死んでいくのが人生ではありませんか? あなたはどうして走るのですか?
星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。
× × × × × ×
※※※YouTube動画はじめました※※※
書籍『市民ランナーという走り方(マラソンサブスリー・グランドスラム養成講座)』の内容をYouTubeにて公開しています。言葉のイメージ喚起力でランニングフォームを最適化して、同じ練習量でも速く走れるようになるランニング新メソッドについて解説しています。
『マラソンの走り方・サブスリー養成講座』
気に入っていただけましたら、チャンネル登録をお願いします。
ハーフマラソンのベストタイムはフルマラソンのハーフ地点の人
ところでランナーのみなさんの中に「ハーフマラソンのベストタイムはフルマラソンのハーフ地点」という人はいませんか?
時々います。実は私もその中の一人です。
ハーフ地点を通過するときに、ラストスパートもかけていないのに、どうしてこんな「ありえない」ことが起きるのでしょうか?
私は「脱力」のせいだと思っています。リラックスして走ったおかげではないでしょうか。
10kmぐらいなら、りきんだ全力の走りが続けられるかな? といつも思うのですが(結局無理なんですけど)、さすがに42.195kmのマラソンをりきんだまま走り続けるのは無理です。「どうせ無理だ、もたない」と諦めがつくんですね。そこでフッと力が抜けます。この脱力がポイントです。
りきむと自分で自分の力を殺しながら走るようなことになってしまうのです。筋トレしながら走るような羽目になります。アクセルとブレーキを同時に踏み込んだような状態になります。「どうせもたない」とりきみが消えることがいい効果をもたらすのです。
運動とは、骨という棒を筋肉が収縮させて動かしていることは誰でも知っていると思います。ところでこの筋肉というものは主動筋と拮抗筋で吊りあって成り立っています。対になっているのです。対になっていないと「行ったきりで、戻ってくることができません」。
筋肉は対になっている
たとえば大腿骨で言えば、前に振り上げる筋肉と、後ろに振り戻す筋肉が対になって存在しています。
主動筋というのは「本人の意識の問題」であって、定義があるわけではありません。脚を前に振り上げたい時の主動筋と、脚を振り戻したい時の主動筋は真逆になります。
理想的なのは主動筋だけに力が入って、拮抗筋は完全に脱力していることです。アスリートが「リラックス」というのはこういう状態を理想とするからです。
たとえ話をしましょう。
脱力がどれだけ重要か、たとえば柔軟運動でもよくわかります。
柔軟運動で体を曲げるとき、曲げる筋肉を引っ張るよりも、伸びる方の筋肉をゆるめる方が、より体を柔軟に曲げることができませんか?
まさしくこれが脱力のもつ効力なのです。力んでいるというのは、主動筋、拮抗筋ともに力が入っている状態のことです。脚を上げようとしながら下げようとしているようなものです。ブレーキを踏みながらアクセルをふかしているようなものです。
これではいいパフォーマンスができるわけがありません。自分で自分の力を殺しながら走るようなことになるというのは、こういう意味です。
脱力する技術。主動筋にだけ力を込めて、拮抗筋の力を抜くのがリラックスの本当の意味
普段の練習から「脱力」した「りきまない走り」が意識的にできるようにしておきましょう。
練習のうちは「筋トレしながら走る」筋トレランニングもアリですが、そればかりやっていると、いざというときに脱力できません。

力の抜き方を知っておくことも重要です。脱力も技術のうちなのです。
力を込めて速く走ることは簡単です。しかしそれだと長くはもちません。
力を抜いて速く走ることはとても難しいことです。
主動筋にだけ力を込めて、拮抗筋の力を抜くのは、難しいのです。
そしてそれができれば長く走り続けることができます。だから脱力は速く走るための技術だというのです。
人間、普段やっていることがどうしても出てしまいます。
無意識にいつものフォームになってしまいます。
だから普段から脱力したフォームを習慣づけておきましょう。
腰で走る。背中をゆるめると腰が使える
大きなストライドを確保するためには腰を使う必要があります。
腰を使って走るためには、胸を開いて肩の力を抜くことです。
具体的には、背中の肩甲骨を寄せて肩をさげます。すると背中がゆるみます。
背中がピンと張っていると腰をダイナミックに使えません。
背中がゆるめば、腰を動かしてダイナミックに走ることができます。
おまけに背中がゆるんで胸が開けば呼吸が楽になるという一石二鳥のフォームです。
Time is what I am そのタイムはフルマラソンのタイム

「Time is what I am」というCMがありましたが、初対面のランナーの間では「名刺代わり」にベストタイムを聞いたりしますよね?
そのときのタイムっていうのは、たいていマラソンのタイムだと思います。これまでに名刺代わりに「ハーフマラソンのタイム」をもらったことはありません。
ハーフマラソンというのはあくまでも目指すゴール地点ではなく、フルマラソンのための指標にすぎないというのが私の認識です。
だからハーフマラソンに向けてピーキングをしたことは一度もありません。
このピーキングがどれだけすごい効果を生み出すかも、ハーフマラソンのベストタイムがフルマラソンのハーフ地点の人はよーく知っています。

りきみをなくして、ピーキングしたからこそ、そんな「ありえない」ことができたのです。
× × × × × ×
※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?
いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。
●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」「かかと落としを効果的に決める走法」
●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?
●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。
●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。
●腹圧をかける走法。呼吸の限界がスピードの限界。背の低い、太った人のように走る。
●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?
●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」
本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。
あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。
× × × × × ×
どんなレースに出ても自分よりも速くて強いランナーがいます。それが市民ランナーの現実です。勝てないのになお走るのはなぜでしょうか? どうせいつか死んでしまうからといって、今すぐに生きることを諦めるわけにはいきません。未完成で勝負して、未完成で引退して、未完成のまま死んでいくのが人生ではありませんか? あなたはどうして走るのですか?
星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。
× × × × × ×