ドストエフスキー作品『白痴』のあらすじ、読書感想文
ここではドストエフスキー『白痴』の書評をしています。主人公は「てんかん」の病のために、またロシアを知らないために、相手の言うことを言葉通りに受け取るほど無垢なために白痴と呼ばれるムイシュキン伯爵です。
作者ドストエフスキーはムイシュキンを「現代のキリスト」「無条件に美しい人間」として描こうとしたらしいのですが、どのあたりが無垢な殉教者なのか、私にはさっぱりわかりませんでした。
× × × × × ×
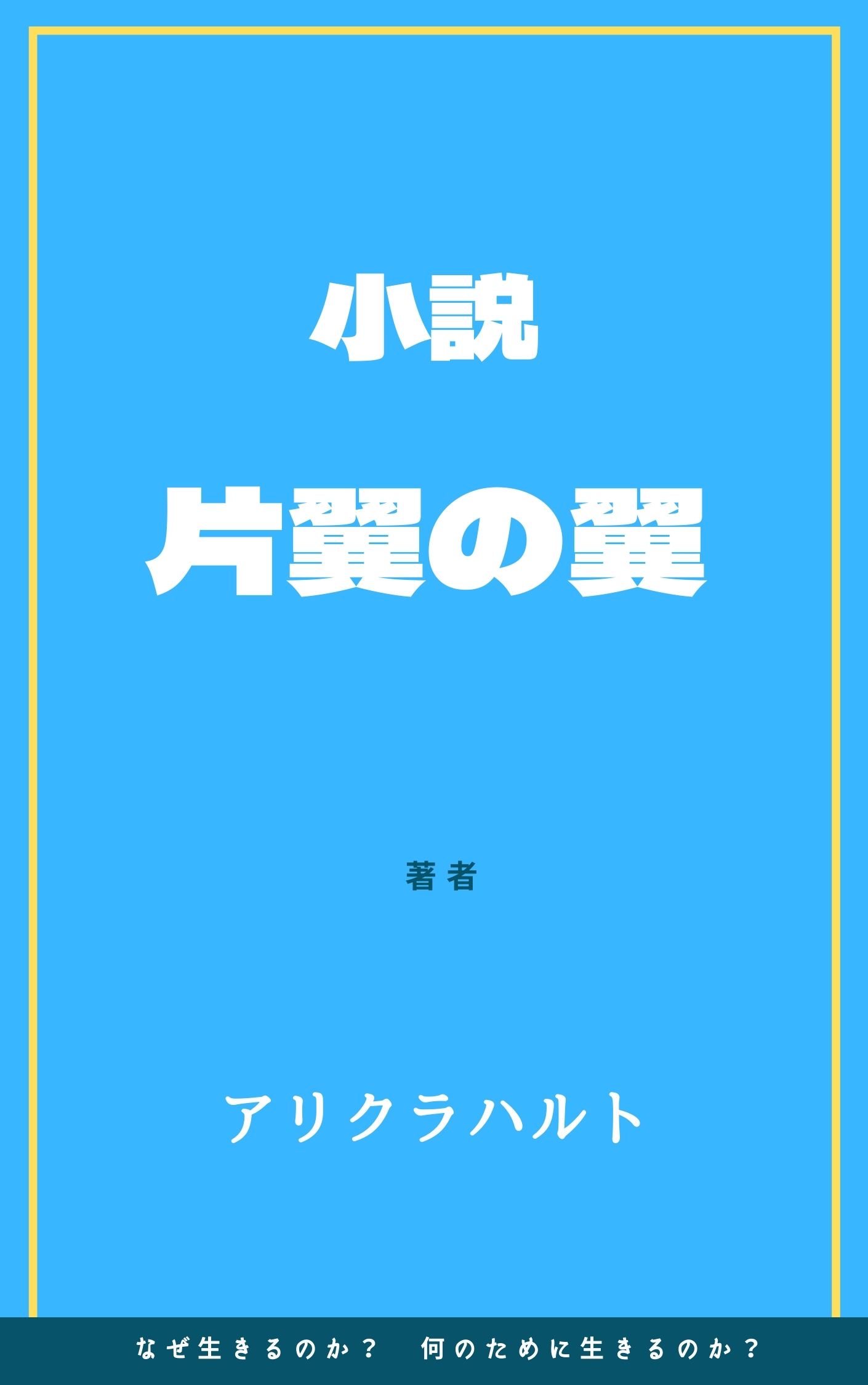
このブログの著者が執筆した「なぜ生きるのか? 何のために生きるのか?」を追求した純文学小説です。
「きみが望むならあげるよ。海の底の珊瑚の白い花束を。ぼくのからだの一部だけど、きみが欲しいならあげる。」
「金色の波をすべるあなたは、まるで海に浮かぶ星のよう。夕日を背に浴び、きれいな軌跡をえがいて還ってくるの。夢みるように何度も何度も、波を泳いでわたしのもとへ。」
※本作は小説『ツバサ』の前編部分に相当するものです。
アマゾン、楽天で無料公開しています。ぜひお読みください。
× × × × × ×
癲癇とはどんな病気? てんかんで白痴ってどういうこと?
作者ドストエフスキーも「てんかん」持ちだったことで知られています。癲癇もちで白痴というのはどういう意味なんでしょうか?
癲癇とはどんな病気なのでしょうか?
てんかんは、突然、けいれんしたり、意識を失って倒れるなどの病気です。これを「てんかん発作」といいます。原因は脳の電気信号の異常によるとされています。その信号の強弱によって人によって「てんかん発作」もさまざまなのだそうです。突然目の前でぶっ倒れてヒクヒクと痙攣されたら、たしかにヤベエ奴には見えるかもしれませんね。白痴には見えないかもしれないけれど。その異常信号のせいで、症状の悪い人は脳機能障害にまで行ってしまう人もわずかながらいるそうです。しかし実際に癲癇もちのドストエフスキーは、史上最大の文豪と評価されることもあるのです。私はそうは思わんけど。
ドストエフ好き? うんにゃ。嫌い。
イエスが子供に慕われる描写はない。

ギロチンになる死刑囚の会話内エピソードから冒頭スタートします。
子どもに慕われるムイシュキン。子どもに愛される子どものような男。
私は聖書を精読していますが、イエスが子供に慕われる描写はなかったのではないかと思います。なぜなら奇跡を奇跡と感じることができるのは常識ある大人だけであり、何も知らない子供にとっては奇跡もあたりまえのことになってしまうからです。
汽車の中でたばこを社外に投げ捨てられ、おかえしに子犬を車外に投げ捨てるエピソードがあります。この犬を投げ捨てるエピソードは妙に印象に残りました。持参金目当てのガーニャ。おおっぴらに「金のため」に「人の思いもの(老人トーツキィの情婦)=ナスターシャ」と結婚しようとする。
卑劣漢ですな。ドストエフスキー作品には、こういう「典型的な」「あからさまな」「恥を知れといいたくなる」人物がよく登場します。
ドストエフスキーは今日の日本人にとっても本当に名作といえるのか?
嘲笑しようとわざわざ近寄ってくる女。こういう嫌味な人間を登場させるのが、ドストエフスキーの真骨頂なのです。書き手としては普通はここまで露骨なのは書きたくないんですけどね。典型的な嫌な奴とか、典型的な嫌味とか、絵に描いたような典型的な悪人が本作でも登場します。
呼ばれてもいないナスターシャのパーティーに行く侯爵。そこで「生涯一の悪い行いを告白するゴッコ」を行います。トーツキイの情婦であったことと、お金にがめついことで、男に軽蔑され捨てられると思っているナスターシャ。「幸福になれないなら、いっそ別れましょう」などという。こういう反応を現代精神科では「防衛機制(反復脅迫)」といいます。いじめられてきた犬が、やさしい人にも、おびえて噛みつこうとするようなものです。
人名を理解するのに苦労するロシア文学。和訳版は人名を統一した方がメリットが大きいのではないか?
ガーニャに火中から取れば10万ルーブリあげると試すが、意気地がなく取れない。
ちなみにガーニャというのは男です。ワーニャというのは女です。わからんっちゅーの。日本語のようにタケシは男で、シズカは女だというように、名前から日本人は性別などが連想できません。あだ名で読んだり、フルネームで読んだり、ドストエフスキー作品は人名を理解するのに苦労します。
ロシア人が読む場合、呼びかけ方で「親しみ」「関係性」を表現しているわけで、原書ではそれを表現するために使い分けて表現されているわけですが、和訳された書物の場合、名前は統一した方がいいんじゃないでしょうか。どうせ日本人が読むものですから、ロシア本国の繊細な呼びかけによる関係性なんて日本人にははかりしれませんし、それをとるメリットよりも、誰が誰だかわからなくなるデメリットの方がずっと大きいと思います。
同じ人物の名前を三通りぐらい覚えなければなりません。ただでさえおぼえられないというのに……。
日本人感覚だと「キチガイ」ばかり登場する。だから「白痴」なのか?
ラゴージンは、恋によって現在うけている苦しみのために、ナスターシャを憎み、女が女房になったら腹いせしようと考えている。女房にならなかったら殺そうと決めている。
どういう変態なんでしょうか? かなり屈折した変態ですね。
ナスターシャは金めあてでなく、背後に白刃があるから、ラゴージンが気になっている。
女の方もかなりの変態です。精神的マゾっぽいところがあります。
時計のために長年の友だちを刺し殺す男のエピソード。時計を見せびらかすスネ夫をのび太が殺しちゃうみたいなエピソードです。日本人の感覚だとキチガイだと思うんですけど、こういうあからさまなのを臆面もなく出してくるのがドストエフスキーという作家です。日本人は温和で暮らしやすいけど、ドラマがあるのはロシア人かもしれません。
エリツィンのように「ソ連とロシアは違うのだ」と五木寛之は予言した
赤ん坊の笑顔を見た母親のうれしさは、罪びとが真心こめてお祈りするのを見た神のうれしさと同じ。これがキリストの最も重要な思想なんだ。
私はそうじゃないとおもいます。キリスト教の本質は、この肉体この意識のまま死者が復活すること、そして永遠の命を得ることができるということです。
十字架を交換して義兄弟の契りを結ぶムイシュキンとラゴージン。いくらキリスト教思想で意気投合したからって、いきなり義兄弟はムチャじゃないかな。義兄弟の契りが唐突な気がします。元々ふたりはナスターシャをめぐる相いれないライバル同士だったのです。
前世の約束なら、ナスターシャはおめえがとるがいい。あれはおめえのもんだ。おれはおめえに譲った! ラゴージンをわすれないでくんな。
ナスターシャはたえまなく自分の穢れを自覚するのが、ちょうど誰かに復讐でもするような快楽なんです。マゾですねえ。なんだか分裂症の人のように見えます。あるいは作者は分裂症の人を描きたかったのだとすれば成功していますね。
『告白』を読むイッポリート。拳銃をこめかみに当てて撃つが、銃弾が出ない。不発か。未装填か。恥じて泣くイッポリート。大声で笑うもの。雷管を入れ忘れた。ぼくには廉恥心がある。永久に恥辱を受けた。意識を失って倒れた。自殺しかけたのは『告白』をアグラーヤに読んでもらいためか。ほめてもらいたかった。われわれはあなたを愛しかつ尊敬しています。どうぞ生き残ってくださいといってほしかった。自殺未遂か、狂言自殺か、はっきりしないエピソードです。このように本筋と関係のない小エピソードが『白痴』では妙に印象に残りました。
うそをつくときに、まるで類のないようなことを、ちょっと上手に挟むと、その嘘がたいへんほうとうらしくなるものよ。
嘘つき、多いんだよなあ。ドストエフスキー作品。
ムイシュキンとラゴージンとナスターシャの経緯は、会話の中で語られる場合も多く臨場感がありません。
ムイシュキンがナスターシャにプロポースしたこと。しかしナスターシャはラゴージンと駆け落ちしたこと。それをムイシュキンが取り返したこと。ムイシュキンとナスターシャは一所に暮らしたこと。ストーリーの上で、ひじょうに重要な要素であるはずの、これらのことが、説明ゼリフと呼ばれる会話の中で説明されるだけなのです。非常におくれた演出法ですね。
シャーロック・ホームズが過去に起きた事件を、いま目の前で現在進行しているかのように演出した手法をぜひ見習ってほしいものです。
ホームズ・ワトソン・スタイル。シャーロックホームズ60編の読むべき順番
死臭にこだわり。死臭が好きなのか?
じゃあ自首しないんだね。あれをかつぎ出さないんだね
どうしてどうして。
ひとつ心配なのは、においが出やしないかってことなんだ。おめえ、においがするかい?
死臭にここまでこだわる人も珍しいのではないでしょうか?
死臭といえば『カラマーゾフの兄弟』ゾシマ長老の死臭を思い出します。
ドストエフスキー作品の読み方(『カラマーゾフの兄弟』の評価)
これほど死臭を執拗に描写する作者はヘンタイなんじゃないかと思います。
カラマーゾフの兄弟『大審問官』。神は存在するのか? 前提を疑え!
ナスターシャ殺しの犯人ラゴージンは喪心と熱病の状態に。ムイシュキンは白痴に。
なんで? 過剰な精神ストレスが原因でしょうか?
こういうのを女脳というんでしょうか。とりとめのないことをひたすら饒舌だな。ドストエフスキー。
実際のドストエフスキーはギャンブル狂で、賭ケグルイの果てに、出版社からお金を借りたのが『白痴』誕生の背景だそうです。身を亡ぼすほど賭博に狂った人間が「無条件に美しい人間」を描こうってそれは無理じゃないですかね? まず自分が斎戒沐浴してから……というのが日本人の発想だと思います。「それとこれとは別」というのが大文豪なんですかね。女を抱きながら悟りの世界に達してしまうような人が世の中にはいます。ドストエフスキーもそのような「常人でない人」だということでしょうか。
「唐突」「分裂症」「気持ち悪い」「キチガイ」
人間の感情は一筋縄ではなく、瞬間瞬間でコロコロ変わるものだ、ということをドストエフスキー本人は描きたいんでしょうが、小説でそれをやろうとするから「唐突」「分裂症」「気持ち悪い」「キチガイ」に見えるのです。
ドストエフスキーは今日の日本人にとっても本当に名作といえるのか?
このドストエフスキー作品の傾向をわたしは「モダンアートみたいなものだ。わかる人とわからない人がいて当然だ」と評しました。
『白痴』に登場するヒロインたちにも同じことが言えます。そして私はこの人たちの描き方が「好きになれない」「理解できない」のです。
白痴の内容
ムイシュキン公爵の二つの愛。不可解にして謎
よくわからないのでチャットGPTに聞いてみた。
chatGPT「ドストエフスキーの小説『白痴』において、ムイシュキン公爵の二つの愛は、ナスターシャ(アレクサンドラ・エヴゲーニエヴナ)への愛と、アグラーヤ(エリザヴェータ・プロコフィエヴナ)への愛です。まず、ムイシュキン公爵のナスターシャへの愛は、純粋で理想的な愛として描かれています。彼はナスターシャに深い感情を抱き、彼女の美徳や純粋さに魅了されます。ナスターシャは物語の中で彼の心の支えとなり、彼の内なる善を引き出す存在です。ムイシュキン公爵はナスターシャを救いの手と見なし、彼女に対して献身的な愛情を注ぎます。
一方、ムイシュキン公爵のアグラーヤへの愛は、情熱的で身体的な要素を含んだ愛として描かれています。アグラーヤは美しい女性であり、彼女に対して公爵は強い性的魅力を感じます。しかし、この愛はより複雑で混乱しており、彼の心の中で罪深い欲望や破滅的な要素も含まれています。公爵はアグラーヤへの愛に引き寄せられる一方で、その愛によって苦悩し、内なる葛藤に直面します。
つまり、ナスターシャへの愛は精神的な次元での救済や純粋な善を象徴しており、公爵の魂を浄化する力を持っています。一方、アグラーヤへの愛は情熱的で身体的な要素が強く、公爵の内なる葛藤や欲望を露呈させます。
これらの愛の対比は、人間の心の中に存在する善と悪、純粋と欲望、理想と現実の相克を描き出すために用いられています。ムイシュキン公爵の二つの愛は、彼のキャラクターや小説全体のテーマの一部として、複雑で深い人間の心理を探求する上で重要な要素となっています。
ムイシュキン公爵のナスターシャへの愛は、彼にとって精神的な救済と癒しをもたらします。ナスターシャは彼にとって純粋さと善の象徴であり、彼女の存在は公爵が自身の内なる葛藤や社会の不条理に直面する中で、彼の心を安定させる要素となります。公爵はナスターシャへの愛を通じて、自己犠牲や慈愛の美徳を具現化しようとします。
一方、ムイシュキン公爵のアグラーヤへの愛は、より複雑で破壊的な要素を含んでいます。アグラーヤは魅力的な女性であり、公爵は彼女の魅力に引き寄せられますが、同時にその愛に苦悩し、内なる闘争を抱えます。アグラーヤへの情熱は欲望や肉体的な要素に基づいており、公爵の心には罪深い感情や堕落の欲望が渦巻いています。
ナスターシャへの愛とアグラーヤへの愛の違いは、愛の対象への公爵の感情や心理的な状態によって明確に示されます。ナスターシャへの愛は彼に喜びと救済をもたらし、彼を高尚な精神的な存在へと導きます。一方、アグラーヤへの愛は快楽と苦悩を伴い、公爵を誘惑と罪の狭間に引きずり込みます。
この対比は、ドストエフスキーの『白痴』において善と悪、理想と現実、純粋と欲望といったテーマを探求する上で重要な要素です。公爵の二つの愛は、人間の心の中に存在する相反する要素を浮き彫りにし、人間の複雑な本性や善悪の闘争を描写しています。」
こんなもっともらしい答えを返してきたのですが、ぜんぜん納得できません。
精読したつもりですが、どの描写をもってナスターシャへの愛は、純粋で理想的な愛といっているのか? どこらへんが物語の中で彼の心の支えとなっているのか、まったくわかりませんでした。chatGPTも具体的に教えてくんろ。
風俗嬢に説教して自分のものにするタイプの男?



