ダーウィンはDNAを、始祖鳥を、地球の年齢を、大陸移動説を知らなかった
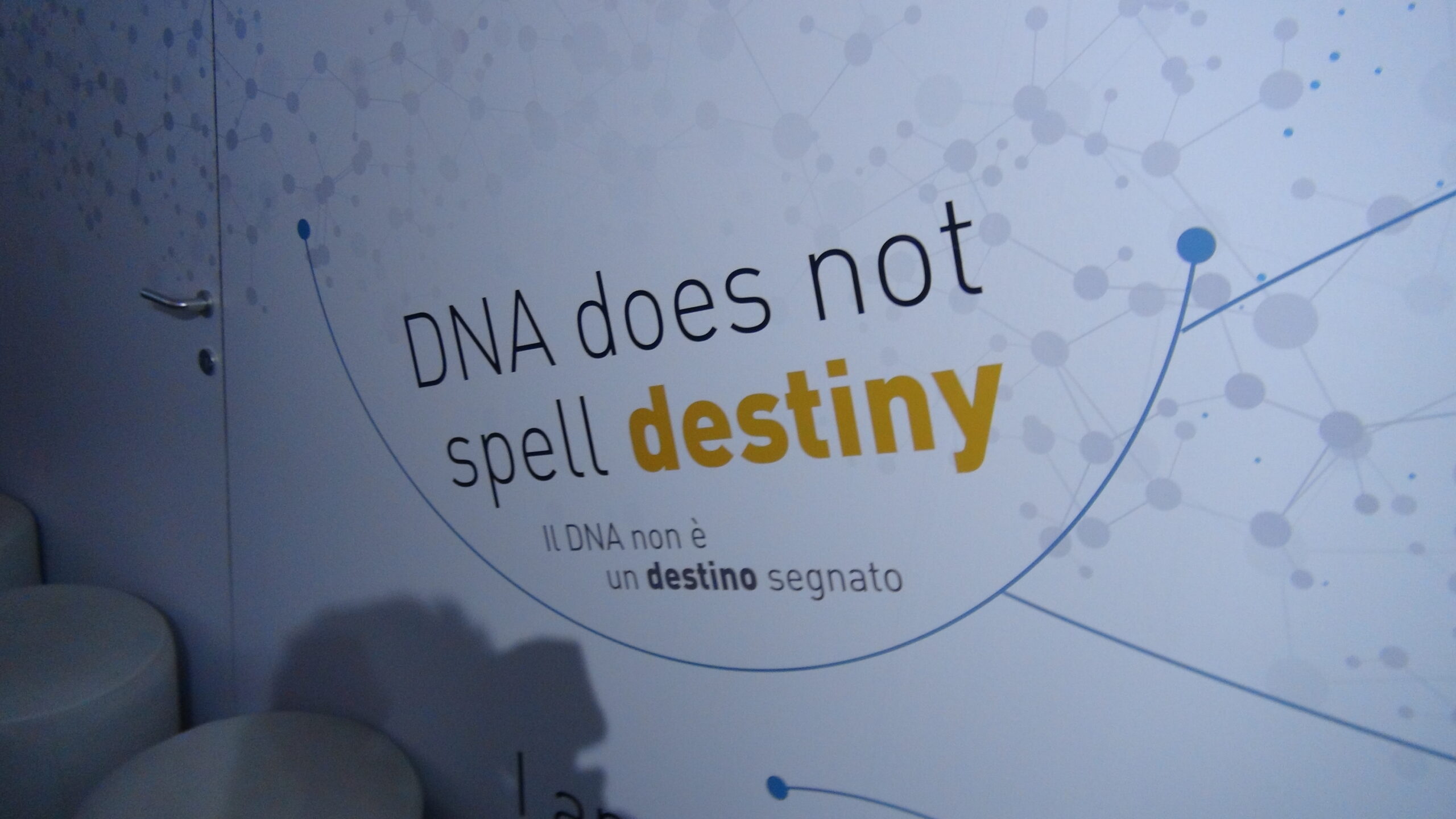
世界を変えた一冊であるダーウィンの『種の起源』を読みました。具体的な内容はほとんど知っていることばかりでした。進化論はもはや現代人の教養です。
むしろ私が驚いたのはこういったことです。「この人(ダーウィン)、現代人の教養を何も知らずに死んだんだな」と。
ダーウィンは、メンデル遺伝の法則を知りませんでした。染色体も、遺伝子DNAも知りませんでした。
爬虫類的な鳥類である始祖鳥も知りませんでした。オーパーツがなかったのに、類推によって始祖鳥の出現を預言したのです。化石は一部しか見つかっていないと『種の起源』ではくどいほど説明しています。
地球の正確な年齢が46憶年であることも、生物の全史が40億年であることも、小惑星衝突による恐竜たちの大量絶滅も知りませんでした。
ウェゲナーの大陸移動説も知りませんでした。知っていたらもっと簡単に自然選択による変異が説明できたでしょうに。
そこが面白くてしょうがなかったです。推理小説にたとえると、決定的な証拠のほとんどが入手できていないのに、プロファイリングだけで犯人を探し当ててしまう名探偵のようなものです。スリリングな読書体験でした。
もちろんニュートンだってそんなことは知りませんでした。でも計算で引力を求めたニュートンを天才だと今でも私たちが思うように、ダーウィンも「近代の決定的な知識を何も知らない人」ですが、おそろしく博学で、当時も今も天才と呼んでいいような存在でした。
おそろしく博学なのですが、それでも知らないことが圧倒的に多いのです。近代人の知性・常識をもっていないのです。それでも『種の起源』を読むと知の巨人ぶりを感じます。著書を読むとその矛盾を感じます。
現代人の教養というべき決定的な知識が欠けているくせに(19世紀の人物です)、博物学者として現存生物にはやたらと詳しいのです。そこから次々と名探偵のように仮説をたてて推理していきます。
無人島にどうして生物が出現するのか? この謎に対し、鳥の足に付着した土から繁茂する植物や、海に漂った種子が漂着したら島で繁殖するか? 鳥の排泄物内の未消化種子の発芽確率など、当時できる実験は自分でこなしています。その結論は、無人島の生物は外から流れ着いた、というものでした。神の創造ではありません。
× × × × × ×

このブログの著者が執筆した「なぜ生きるのか? 何のために生きるのか?」を追求した純文学小説です。
「きみが望むならあげるよ。海の底の珊瑚の白い花束を。ぼくのからだの一部だけど、きみが欲しいならあげる。」
「金色の波をすべるあなたは、まるで海に浮かぶ星のよう。夕日を背に浴び、きれいな軌跡をえがいて還ってくるの。夢みるように何度も何度も、波を泳いでわたしのもとへ。」
※本作は小説『ツバサ』の前編部分に相当するものです。
アマゾン、楽天で無料公開しています。ぜひお読みください。
× × × × × ×
小さな変異が蓄積し、亜種になり別種(変種)になるという自然選択理論
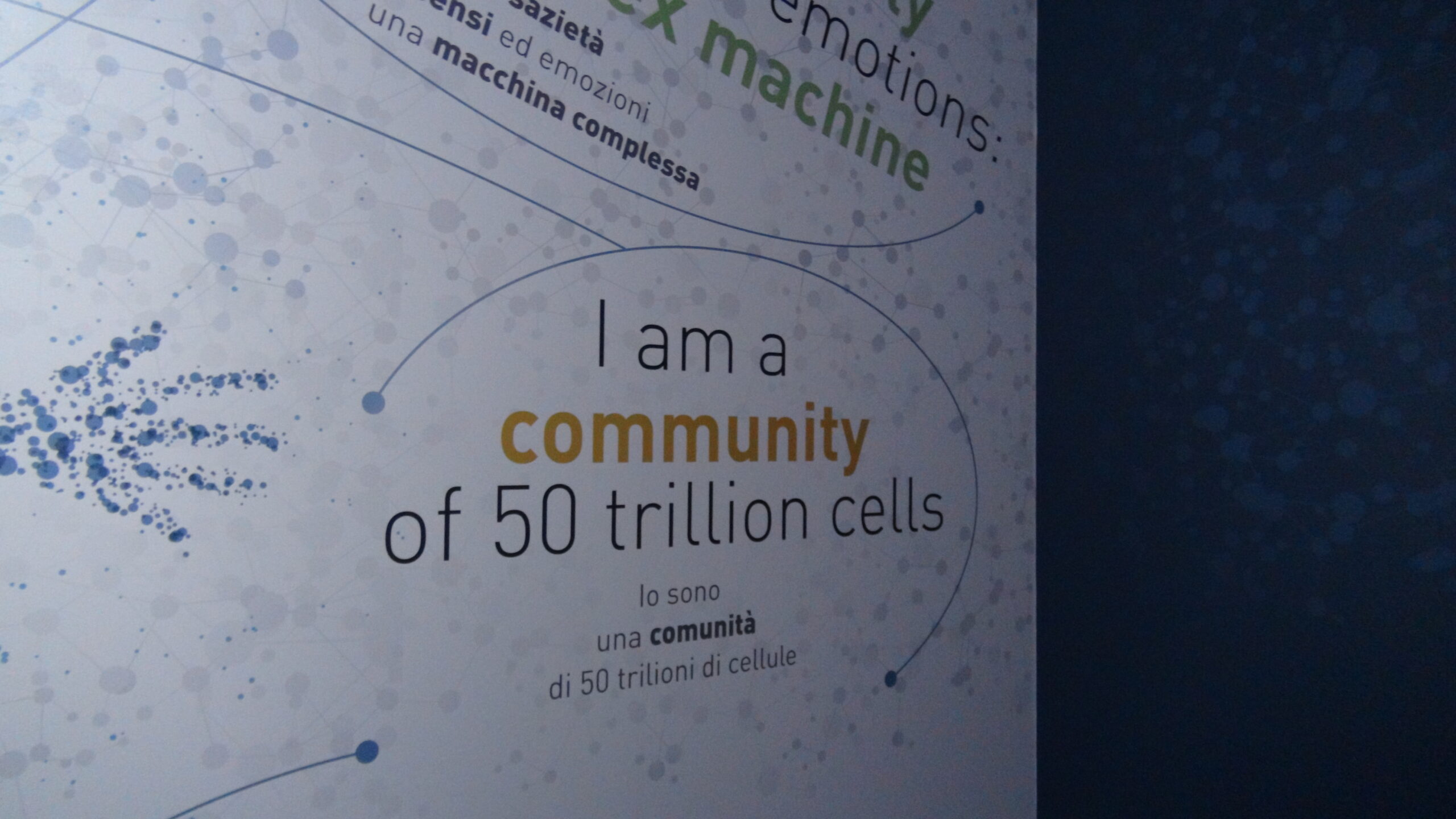
ダーウィンの理論はこういうことです。
細胞には変異が起こり、やがてそれが亜種になり、亜種はやがて別種(変種)になる。
その仮説からすべての生物はたったひとつの細胞から生まれた、と推理しました。
そして自然に適応した別種は、原種とモロ被りの生活圏で競争し、やがて原種を絶滅させる、という理論でした。
ダーウィンは時代の先駆者であり、時代に恵まれたところもありました。
現代日本では「外来種」といって人間が外の世界から持ち込んだ生物が反映して、もとの生態系を壊してしまうことが問題になっていますが、ダーウィンの頃はまだそういう問題はありませんでした。
誰もが飛び交うような時代ではなかったからです。海外旅行や移住、移民などがちいさかったので、昔ながらの生態系が残されていました。そのことがダーウィンの研究の資した部分もあります。人間の持ち込んだ外来生物というのが、まだほとんどない時代だったのです。そのおかげで証明できたこともありました。
ダーウィンの理論では、海などによって隔てられていることで、元は同じ生物が長い時間の別環境での生存のあいだに別種になるということが説明されています。
今だったら外来生物と従来生物が混在していて、環境適応(自然選択)理論が説明しにくかったかもしれません。中国にも日本にもキョンやハクビシンがいますからね。生みに隔てられているのに。
『種の起源』の言外に匂うおそろしい結論「人類は絶滅する」

おそろしく長い地球の歴史の中で、おそらく現在生存している種のほとんどは絶滅するとダーウィンに予言されています。それはこれまでの地球生物の歴史からダーウィンが論理的に導き出した確率的な結論です。
このおそろしい結論は『種の起源』に直接、具体的には書かれてはいません。しかしそう読めるのです。
たとえばこういうことです。

やがてライオンは絶滅するだろう。やがてキリンは絶滅するだろう。数百万年後には種として絶滅している確率はほぼ100%。万が一、生き残っていたとしてもまったく小型の別種になっているだろう。ラプトルもサーベルタイガーも絶滅した。ライオンだってやがて絶滅する。
なんとなくそれは想像できると思う。
そして同じようにホモ・サピエンスも絶滅する。かつてネアンデルタール人やクロマニヨン人が絶滅したように、ホモサピエンスも絶滅している可能性が圧倒的に高い。その確率はほとんど100%。『種の起源』には直接そう書いてはありませんが、そう読めるのです。
ぜいぜい千年単位でしかものごとを見ることができない人にとって人間やライオンやキリンが絶滅するなんてことは想像もできないかもしれないが、この地上での生物種の絶滅の歴史(たえず別種が発生して、古代種は絶滅するのが地上生物のならい)を見れば、まずほぼ人間は滅び去ります。
直接的には書いていないが、暗にそう書いてあるのです。『種の起源』はそんなおそろしい本でした。
『種の起源』は創造神話だけでなく、死者復活・永遠の命まで否定した

ニュートンは万有引力を発見してもなお神の存在を信じていましたが、ダーウィンはもはや信じてはいませんでした。科学者ですが、アリストテレスの仕事を洗いなおしたような思想家、哲学者、宗教家のようでもあります。
『種の起源』がキリスト教世界から嫌われたのは、神がすべての種を一度に創造したという創造神話を否定したからだと理解されているが、それだけではないと思います。
死者は復活し、神の王国で永遠に生きることができる、というキリスト教の根幹の教義までも、暗に人類も他の動物と同じように絶滅すると示すことで否定してしまっているのです。
その恐怖によって、悪魔の書のような扱いを受けました。

自分が復活して永遠に生きられないばかりか、子孫も残らない、人間(ホモ・サピエンス)という種まで絶滅する。『種の起源』にはそう書いてある。いわばキリスト教の根幹(死者復活)を揺るがす本なのだ。
人間が生き残るとしてももはや別種になっている。人類は滅び去るのだ。何の希望もない。
自分を犠牲にして人類の未来の夢をつないだところで、絶滅という結末は変わらない……だったら生き方を変えるしかない。
それが「キリスト教世界をぐらつかせた本」と呼ばれる本当の意味なのです。
キリスト教の本質は、この肉体この意識のまま死者が復活すること、そして永遠の命を得ることができるということ
証拠がないのに犯人を探し当てる名探偵。『種の起源』は探偵小説のように読める
『種の起源』はものすごくよくできた探偵小説のように読むことができます。
ダーウィンは、メンデル遺伝の法則も、始祖鳥の化石も、大陸移動説も、決定的な証拠を何ひとつ発見できていないのに、それでも犯人を探し当ててしまう名探偵のようです。
普通、学術書はこれほど面白くは読めませんが、『種の起源』は、ものすごく面白く読むことができます。
人間が人知を超えていく。ヒトがヒトを超えていく。ヒトが神に近づいていく。そんな体験をすることができます。
× × × × × ×
※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?
いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。
●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?
●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?
●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。
●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。
●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?
●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」
本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。
※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。
星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。
× × × × × ×
※関連記事。バカ論文について


