ロバート・ハリス『地図のない国から』放浪の魂を読む。
ここではロバートハリス著『地図のない国から』の書評をしています。
ロバート・ハリスの作品は自分の放浪体験をベースにしたエッセイ集が多いのですが、本作はめずらしく小説です。それだけに特筆すべき作品だと思います。
黄色は『地図のない国から』から。赤字はわたしの感想です。
作品の概要(あらすじ)
ドロップアウトした奴らを駆け足で取材する。これじゃアリがキリギリスをインタビューするようなもんだ。でも本当はアリは過労死している。ああ、思いついた奴に会ってみたい。
放浪者の魂を学ぶことは、自由な時間をどうすごすか学ぶことにつながります。チルできない日本人にはあまり放浪は向いていないかもしれません。
死ぬ権利とは何かに命を賭ける権利のこと。死ぬ自由がなければ人間の他の自由は死んでしまう。
セッ●スとドラッグとロックンロール、ウォーターパイプ、ヒッピー、バックパッカー、サーファー、白人の女の子、楽しくてしょうがない。周りの連中が何をしようと知ったこっちゃないが、オレはオレの生き方を通しているつもりだ。
バリ島のサーフボーイ(ジゴロ)の述懐です。ロバート・ハリスの文章はちょっとした小物がイカスんですが、それは本文を読んでもらうしかありません。イビサのような地名、ジタンやウォーターパイプのような文物、モームのような小説、レニークラヴィッツのような音楽。そういう風俗描写がカッコいいのが特徴です。ケルアックなどのビート文学の伝統を継いでいるのです。
ザ・ダルマ・バムズ(禅ヒッピー)。生きる意味をもとめてさまよう
そしてここのことを忘れてしまう。オレのこともね。
死んだような目で、何も残さないで、誰にも惜しまれないで。一生、あの埃だらけの道を見ながら、遠い夢の世界を見て過ごす……絶対に嫌だね。
放浪者の特徴として「親の生き方に対する不満」があげられます。親のようになりたいと思ったら、人は放浪の旅人にはなりません。世の中にはいろいろな職業がありますが、子どもが親の仕事を継ぎたいと思うような職業は、とても「おいしい仕事」なのだと思います。芸能人、医者などは子供が親の仕事を継ぐことが多いですよね。公務員なんかも親も子もという人が多いので「おいしい仕事」なんでしょう。
饒舌で話し好きな親父の心を、本質を、ぼくはまったく知らない。彼が何を夢見、何を恐れ、何を追い求め、何を支えに生きてきたのか。彼の人間としての、男としての存在感のようなものを、いまだに感じ取ることができないのだ。感情や精神面に関わる深い話しには不愉快な顔をして言葉を濁した。彼がその時何を思い何を感じたかということはストーリーからすべて省略されていた。心のどこかに大きな傷を負った子供がそのまま大人になり、一度も自分の心の闇と向かい合うことなく、ごく表面的な意識のところで生きてきた。
なぜおれの元から去っていくんだ。なぜおれのことをそんなに嫌うんだ。そう言っているように思えてならなかった。喪失にささくれだった気持ちをいっそう搔きむしった。今、日本を出ていかないと死んでしまいそうな気がするんだ。自分がどんな人間であるべきか、探しに出なければならない。親父からは得ることができなかった人間としてのあり方を模索しなければならない。
ロバート・ハリスは父親のタレント英語講師作家という職に反発して海外に旅立ち、けっきょく、タレントDJ作家になります。対人関係などに関する考え方は違っても、結局は似たようなところに落ち着きます。だからこの本は父親に捧げられています。
仕事があったら仕事をして、なかったらなかったで、バイクを飛ばして友達に会って、またここに帰ってくる。人生はシンプルだ。自分をリスペクトして、人もリスペクトする。ハートでつながろうとする、それがリスペクトさ。良い日もあれば悪い日もある。リスペクトさえあれば何とかやっていける。
 赤の他人に心を開いて、おのれの歌をうたってくれたのだ。頭がスッキリして、裸になったような気分だった。
赤の他人に心を開いて、おのれの歌をうたってくれたのだ。頭がスッキリして、裸になったような気分だった。
人が己の歌を歌い、心を開けなくなるのは、それをするとバカにされたり結果責任を負わされたりするからです。夢をあきらめる人が多すぎるために、夢追い人は足を引っ張られます。なぜならもしも彼が夢をかなえてしまったら、夢をあきらめた自分が惨めで後悔にまみれるからです。だから他人の夢をつぶしにかかってくるのです。
放浪はそういう世界から旅立つことです。
彼の静かに狂っているところ。繊細で、残酷なところ。苦しみも憎しみも狂気も人間の原点にあるものでしょ。
きみが美しくて、おれが男だから。きみがほしい。でも、怖い。
彼女の眼が少しづつ笑い始めた。一瞬、部屋の中を乾いた風が吹き抜けていったような気がした。親父にもお袋にも似てないね。ぼくが本や映画や女や車の話しをし、彼が静かに聞く、そんな関係だった。
おれたちはそうだった。おれがガキだったんだよ。彼には借りがあることもわかっていた。でも、その一言が当時のぼくからは出てこなかったのだ。
 パリがそんなに嫌いなら、なぜ出ていかないんだ。十七年という歳月は、彼女から若さだけではなく、芳子という人間そのものを奪い去っていた。性格が底抜けに明るい女はどこにもいなかった。いたのは人生に疲れて、苦々しさを全身から漂わせている中年女だった。長い間ふしあわせな人生を歩んでいると顔が下品になるものなんだ。彼女の憎しみに歪んだ顔が恐ろしくだらしなく見えた。
パリがそんなに嫌いなら、なぜ出ていかないんだ。十七年という歳月は、彼女から若さだけではなく、芳子という人間そのものを奪い去っていた。性格が底抜けに明るい女はどこにもいなかった。いたのは人生に疲れて、苦々しさを全身から漂わせている中年女だった。長い間ふしあわせな人生を歩んでいると顔が下品になるものなんだ。彼女の憎しみに歪んだ顔が恐ろしくだらしなく見えた。
昔と全然変わっていなかった。今、その二人が心の中に帰ってきたような気がした。
今日は誰とも話しをしたくないと思った。ヘミングウェイの研ぎ澄まされた文章と、雨のかすかな音。今日はそんな音楽に一日、身を浸していたかった。
今ここに存在しているという実感のようなものだ。その何かの本質はいまだにつかむことができない。いくつもの断層に埋もれた過去の記憶、人を愛したり憎んだり、受け入れたり拒絶したりする心、他者や状況によって変化する人格、光と闇を行き来する意識、そういったものの集合体としての自分は、いまだに謎に包まれている。この謎の中からあるときは弱くて卑劣な自分が、あるときは暖かくて包容力のある人間が現れる。それだけのことだ。人を愛することは簡単。愛そうとしないことの方がよっぽど複雑で大変なこと。
子どものようにほころんでいく。

男たちだけの夜。鼻血がでるぐらい濃いコーヒー。
プロットのほうはすんなり書き進めていけたのだが、女の謎のところで暗礁に乗り上げてしまった。彼女の物語なくしてはこれはただのB級アクション映画に過ぎない。ただのアイディアじゃない。ぜんぜんストーリーとして見えないわ。第一、ドラマティック・テンションがどこにもないじゃない。そんなに慌ててどうするんだよ。せっかくのチャンスを台なしにしただけじゃないか。
女に謎なんてないわ。本能に忠実なだけじゃない。本当の謎は男の頭の中にある迷宮じゃない。自然とか本能から離れて宇宙を漂うロゴス。存在の孤独を真に感じるのは男だけよ。何かを得たものより、得られなかったものにやってくる反動の方が強いからな。こいつは勝者の余韻にひたっているが、敗者のおれは心の闇と闘っている。どうみてもおれの話しの方が面白い。

まずこの男がどんな人生を歩んできたか、彼がどんな男だったのか、それを考えるね。バックグラウンド・ストーリーってやつだ。ぼくだったら彼を、意志の弱い、平凡な男にするね。
理性とは関係のない、熱くて危険な世界。今まで感じたことのない、心のいちばん深いところで感じる疼きだった。このまますべてを捨てて彼女とどこか遠くへ行ってしまいたい。今まで死んだように静かな海に浸っていたところに急に大きな波がやってきて、昨日までの生活が他人ごとのように脳裏をかすめた。毎日の動作を繰り返しながら、そうする自分をどこか遠いところから眺めている、そんな人間になっていた。
どっからああいうイメージが湧いてきたんだろう。

オデュッセウスがセイレーンの甘い声に惑わされた伝説で知られるこの島。何も起こらない毎日が心地よく感じられるようになった。このタベルナは夜になると島民たちが酒を飲みにやってくる唯一のたまり場だった。暗い無意識の中、ぼくは誰でもなくなっていた。ほとんど聞き取れない英語で説明してくれた。きみの話しを聞かせてくれよ。彼と昨日のゲームの続きをやっているような気がした。
ここではいつもの自分を演じたくないからだ。嫌いじゃないが、飽きるときがある。
もし君がよければの話しだけれど……どうだろう? これも君がよければの話しだけど。

ムチャとしかいいようのないリスクを冒し、まるで手負いの野獣のようにがむしゃらに襲い掛かってきた。彼の目的は勝つというよりはゲームをより危険なものに、よりドラマティックなものにすることのようだった。素人の殴り合いのような乱打戦を繰り広げた。勝ち負けなどどうでもよくなってきた。気風のよさ、度胸、したたかさ、笑みをたたえて破滅へと突っ込んでいく潔さ、まるでいちばん素直で元気でムチャクチャだった頃の自分と勝負しているような感じだった。
安定した生活はすぐぶち壊したくなる。目をつぶると、夜道をバイクで思い切りぶっ飛ばしている映像とか、自分の家をハンマーでぶっ壊しているイメージが浮かんでくる。大声を出して暴れたくなる。
「本音を言うやつはいないのか?」
「煩悩を捨てたふりをするのはやめろ」
「お前らは羊か」
そんなことを叫びたくなる。体がブルブルッと、反射的に震えた。
アウトサイダーの反逆はまずは平凡な日常生活への憎悪といったかたちで現れます。彼は政治家や法律家ではありません。世の中の平安、安寧、ルールとか「みんながおまえみたいだったらどうなるんだ?」といった道徳的なことは一切考えません。とにかく自分が嫌だから嫌なのです。我慢がならないから我慢しないのです。そして衝動に身をまかせます。それが生きることだから。
心は子供のままなんだ。思いきり遊ぶために生まれてきた。だからどんなクレイジーな行動をとってもおれは自分のことも人間のことも人生のことも嫌いにならなかった。

まったく何も聞こえない。すべてが静寂に包まれている。恐ろしくなって大声で悲鳴を上げるんだけどそれも聞こえない。
これからまた新しい旅が始まるのかもしれない。またいつか、どこかで逢おう。
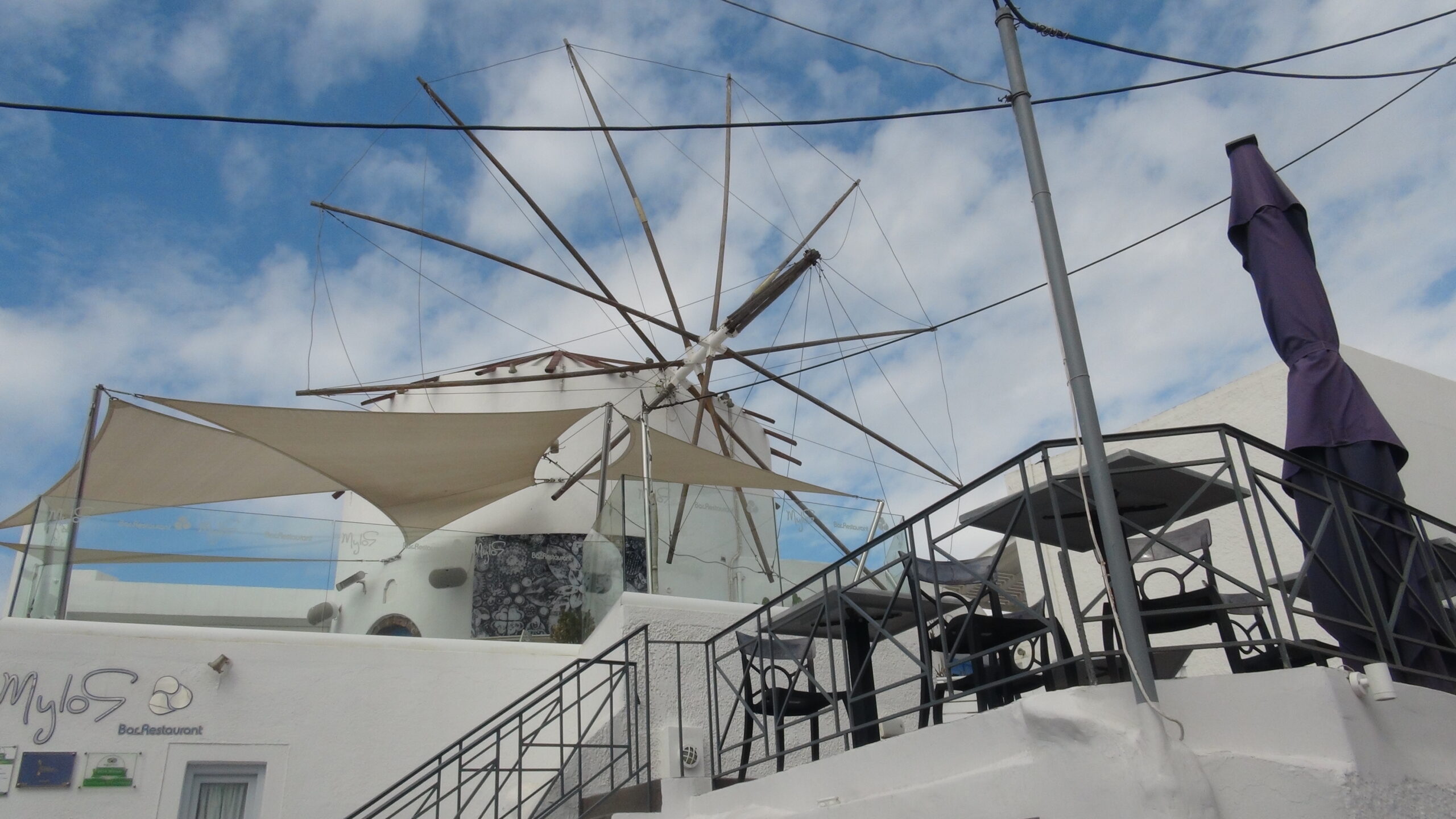
すべてのビジネスから手を引き、長い旅に出る。おれの胸の中にひろがりつつある「何か」をもっと強く感じたいんだ。無。何事にも意味をつけようとするおれたちの頭の外に存在する静けさのようなものだ。それがおれの中ですこしづつひろがっているんだ。
ワイルドで、ちょっとクレイジーで、いつも何かを追い求めている、そんな感じの女だ。

人を殺す夢。処刑される夢。闇に吞み込まれる夢。裏切りの夢。殺戮と破壊の夢。獣に成り下がった夢。嫉妬に狂う夢。
ドラッグのディーラーやストリップ・クラブのおやじをやっているよりはずっと高貴な道を選んだように思えた。
親愛なる友よ。旅は始まった。これから北へと向かう。
死神がやってくるのを待った。怒りと、いいようのない悲しみに全身を震わせながら、ぼくは両手を高く上げ、死を迎え入れようとする。

救いを求めていない人間。魂とは救いを必要としているものではない。
素晴らしいパーティーを覗いた後、また独りで夜道を歩いているようなわびしさだ。コカインをやって何時間もセクシャルファンタジーに浸るんだ。自分でも狂っていると思うぐらいにハマる。快楽はすくなくとも我々に生きている実感を与えてくれる。
今はタブッキとともに魂の旅をするムードでもなかった。何かが一瞬のうちに体の中で目を覚ました、そんな感じだった。オーケー。快楽はオレのビジネスだ。
考えていることを見透かされている……そんな気がしてならない。
集団陶酔は苦手だ。人格を放棄して魂をむきだしにする——そういうことはプライベートでするものだ。皮をはがされ、身もだえる体。人格を放棄して、魂が剥き出しになる。
また旅に出たくなった、ただそれだけのことだ。理由など、もうどうでもいい気がする。
何か新しいものを発見するためには、今の自分を演じるのをやめて、自分が他人になっていくような、そんなプロセスが必要だと思うんだ。

ワルザザードのガスパ。旅はいい。日を追うごとに、オレの中に静寂がひろがっていく。
目が輝いていて、まるで子供が宝物を見せているような、そんな顔だ。
それでも眠れないときは、その中のひとつの場所を選んで旅に出るという空想ゲームをした。ぼくが辺境の地へと送り出した分身たちは、まるで読みかけのまま閉じてしまった本の主人公のように、生も目的もまっとうしないまま、アクションの途中で置き去りにされてきた。
身ぶるいするようなエキゾチックな場所を想像し、その景色の中へ自分を送り込み、ストーリーのきっかけをあたえる。現実感が強くなればなるほど、ロマンが消えていった。可能性としての自分は、現実の自分となるべくかけはなれた存在であることが重要だった。
彼女との闇の中にいるかぎり、自分の中にひろがる闇を感じないでいられる。
笑い声はジェットの轟音に搔き消されるまで、ぼくの頭の中で響き渡っていた。

独りで旅をしていると、剝き出しになった自分に戻る。自分という存在の孤独をあらためて噛みしめ、あとは気の向くままに旅をし、運の流れに身をまかせていけばいいのだ。
人生に疲れた男の話し。悪戯っぽい、子どものような目をした男だった。快楽の追及には金も時間も惜しまなかった。
さっきの少年のような顔をした男はどこへ行ってしまったのだろう。ぼくの目の前に今いるのは、ただの疲れた老人だった。
気を悪くしたなら許してくれ。あれは独り言だ。わたしが自分に向かって発した言葉だ。そう思ってくれ。
演出に追われているうちに、本当の自分が誰なんだかわからなくなってしまった。素の自分の声をもう一度じっくり聞いてみようと思ったんだ。
思い出が私の心をしめつけた。欲望が目を覚ました。狂気が頭をもたげたんだ。快楽の熱から逃れることができなくなった。無視しようとしても、一時的に解消しようとしても、熱は一向に冷めなかった。性的妄想に取りつかれた状態にいた。
二度と、昔のローランという男を演じる気持ちもない。すべてはインシャラーそんなところだ。

砂漠の偉大な静寂の中に、身を置いてみたくなったのだ。
人間の孤独について考えさせられた。神の光から遠ざかってしまった人間がまず感じるのは、孤独に違いない。何かの一部であった状態から分離してしまったときに覚える喪失感のようなものなのだろうか。
「すべてのものからとても遠いところにきてしまった」今という瞬間に酔いしれている彼。虚無の時間と、欲望に溺れる状態とを、行ったり来たりしているのだろうか。数年間、心の闇と闘った結果、自ら命を絶ったのだ。
夜、焚き火を囲み、物語を交換する宴を開く。すべての話しを寓話として受け止め、記憶の中へとしまい込む。一人の人間の物語は人から人へと受け継がれ、波紋をおこし、心をうるおし、手放されていく。そして最後には砂漠の静寂の中に消えていく。

ものを書きたいという気持ちといまだに何も書けない現実。心の中のものを手放す術を知った。弟はもうそこにはいなかった。代わりに最後の光を放ちながら太陽が砂丘と砂丘の谷間へゆっくりと飲み込まれていく光景が目に飛び込んできた。
旅を長くしているものはおのれの感情に無防備な状態になる。自分の中の魔物たちが顔をもたげ、意識の表面へとはい出てくる。このままどこかで肉欲に溺れたい。あの時も自分を救い出してくれたのは砂漠の静寂だった。軽い足取りで、前へ進んでいけばいいのだ。何が起ころうと、風に身をまかせ、心を裸にして旅を続けていけばいいのだ。
旅人の魂が何となく伝わったでしょうか? この本を読んでみなさんが旅に出て、何かをつかむことを祈念しています。


