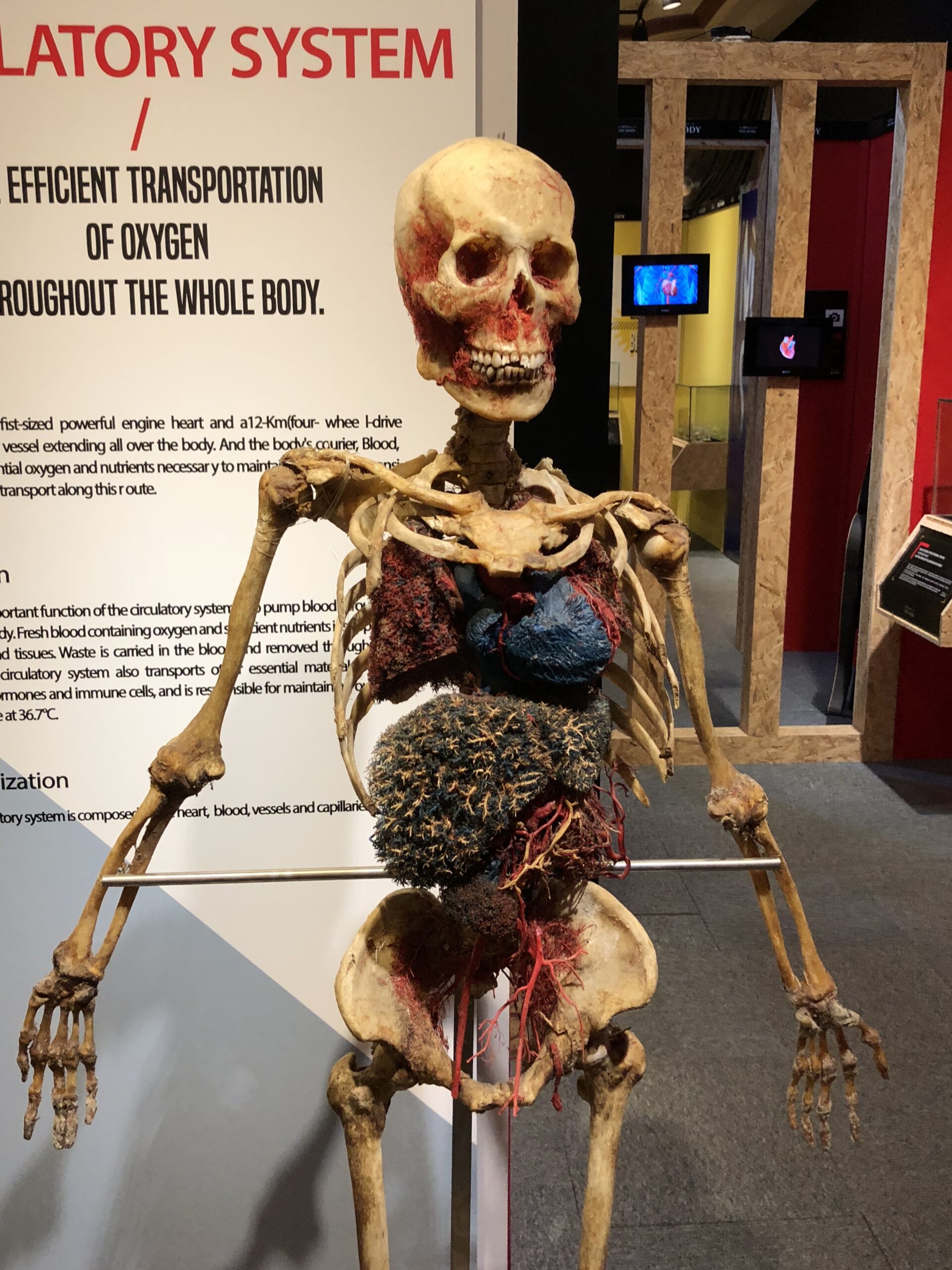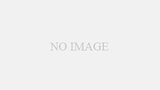死者蘇生の錬金術を現代医学は手に入れたのか?
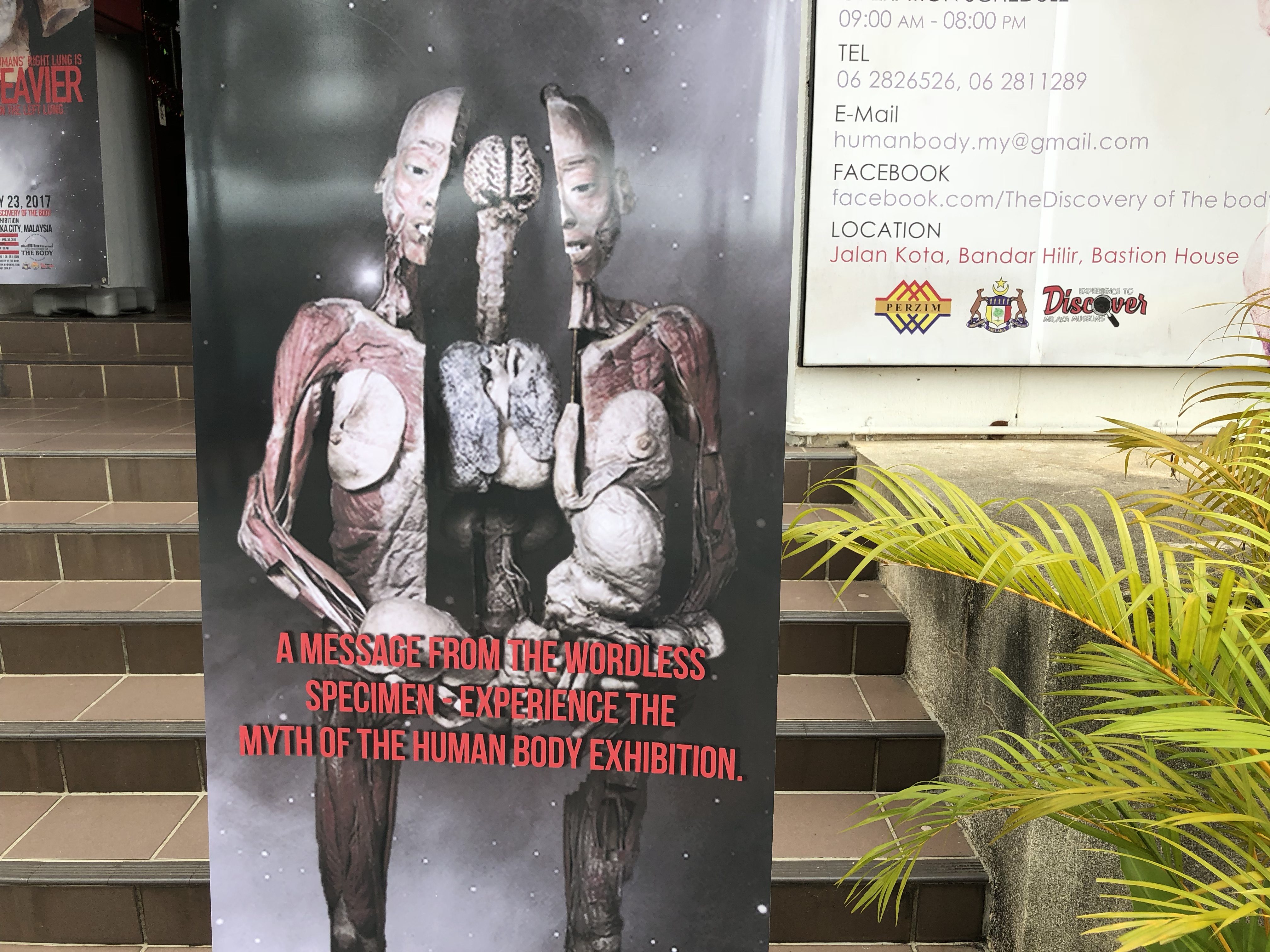
父の大動脈弁狭窄症はいよいよ重篤となり、大動脈弁置換術の手術の日が決まった。
担当医師が手術の説明をするというので家族として長男の私が呼ばれ、説明を受けた。
聞きたいことはただ一つだけ。
「どうして止まった心臓が再び動き出すのか?」
これのみである。
「死者蘇生の錬金術を現代医学は手に入れたのですか?」
それを聞くために都内の病院まで出かけて行った。
これはその顛末を書き記したものである。
人為的に心臓を止める仕組み
担当医師が説明した「止まった心臓が再び動き出すマジック」は、こういうことであった。
担当医師の説明は専門用語を駆使して詳細で、わかりにくいものであった。それをわかりやすく書くのが当ブログの使命である。
簡略化して、わかりやすく説明すること、その能力は医者よりもモノカキの分野だ。池上彰さんがやっていることはこれである。
以下、簡略化して書く。
心臓は筋肉である。ふくらはぎのようなものだ。マラソンランナーがレース後半に、自分の意思とは関係なくふくらはぎが痙攣することがあるが、心臓というのは、あのふくらはぎの痙攣が延々と続いているようなものだ。
× × × × × ×
※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?
いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。
●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?
●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?
●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。
●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。
●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?
●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」
本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。
※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。
星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。
× × × × × ×
「動け」という電気信号なしに筋肉は動くことはないが、その信号を伝達するには「伝達物質(電位差)」が必要である。筋肉細胞は、その電位差に反応して収縮する。
だから、特殊な液に浸して人為的にその電位差をなくしてしまうと、心臓は止まるというのだ。
医師の話しを聞いていて、カエルの坐骨神経ヒクヒク実験のことを思い出した。死んだカエルの脚に人為的に電位差を生じさせると筋肉がひくひくと動き出すというアレだ。アレの逆をやればいいということなのだろう。そうすれば生きている心臓を生きたまま止めることだけが可能のようだ。
生きていて、心臓のビートを刻めという信号は脳からは延々と送られてきている。しかし物理的に信号を送れないために筋肉(心臓)は動かない。命令は送られているが、それを伝達する手段がないというわけである。
なるほど、そういうことであったのか。
「心臓よビートを刻め」命令ある限りハートビートはよみがえる

これに対して死ぬというのは「心臓よビートを刻め」という命令そのものがなくなってしまう状態のことだ。
大動脈弁置換術の場合、心臓は止まっているが、患者はずっと生き続けているのである。「心臓よビートを刻め」という命令はずっと出つづけているからだ。心臓が止まったからといって死んじゃいないのだ。
心臓というのは単なる筋肉にすぎない。心臓が止まっても「死」とはいえないわけだから。死者は蘇生しないが、心臓は蘇生する。
こういう現象を見せつけられたら、医学会が「脳死」とか「死とは何か?」とか問う理由が分かる気がする。
心臓を再び動かすためには、電位差を生じさせないようにしていた特殊な薬剤(心筋保護液)を心筋から流してしまえばいい。そこに血液が流れ込めば再び電位差が生じて、筋肉が再び動き出すというわけだ。「動け」という命令を伝達する手段を取り戻しさえすれば、心臓は再び動き出す。
なるほど説明されれば納得できないこともないが、最初にこの仕組みを発見して実践した人物はいったいどこの誰なんだろうか。名前は残っているのだろうか。よく発見した。生命の革命ではないかと思う。
その「彼」だけは特別に『死者蘇生を成し遂げた錬金術師』として賞賛してもいいのではないだろうか。ホムンクルスをつくったパラケルススよりも偉大な人物として。
『鋼の錬金術師』錬金術とは何か子供にもわかるように解説してみた
ノーベル医学生理学賞よりも錬金術師と呼ぶ方が、はるかに「彼」にふさわしく、はるかに「彼」を賞賛することになると思う。
ウシの心臓の膜(心膜)からつくった弁は腐らないのか?

止まった心臓が再び動き出す謎にくらべたらたいしたことではないが、患者の長男としてはもうひとつだけ医者に聞いておきたいことがあった。
それはこれから父の心臓弁を担うウシの弁は腐らないのか?ということである。
生体である以上は腐るはずである。死なないためには血が必要なはずだ。父の血が牛の血管に流れ込むのだろうか? その場合拒絶反応は起こらないのであろうか?
これに対する医師の説明は明快であった。
まずは牛の心臓の弁そのものを移植するのかと思っていたが、そうではなかった。
父の心臓の弁を牛の心臓の弁に置換するのではなく、弁はウシの心臓の膜から弁状のものを形成して作るらしい。
革ジャンを連想するとわかりやすい。なめした革のようなものだ。もともと生体であるが、もう物質化してしまっているから腐らないのだ。
防腐処理やコーティングをして物質化してしまい、最後には生命の不思議で、人工弁の周囲を患者の幕がコーティングするらしい。よってそう簡単に劣化するものではないようだ。
そもそも血管に弁を取り付けるのではなく、丸い輪っか(人工弁)の内側に三枚のヒラヒラ(生体弁)を取り付けたリングを、父の心臓弁膜と置き換える手術だったのだ。
生体弁というから誤解した。生体は生体でも、革ジャンのように物質化してしまっているものを付けるのだ。だから長持ちするというわけなのだ。
心臓弁膜置換術は心拍復活の錬金術。医者に命を託す
医者の話しを聞いて、だいたいのことはわかった。
なによりも担当医師に不安そうな様子がまるでない。立派なものだ。
心臓弁膜置換術というのは大がかりなものではあるが、心臓手術としてはきわめてありふれたものだということである。医者の不安のない態度を見て、患者の長男は安心した次第である。
医師の好意ではなく、説明責任の義務を果たすために行ったセレモニーであったが、過去の何千何万という患者と家族たちの要望で制度化されたものであろう。
本当に安心することができた。
あとは父さん、医者に命をあずけて、無事に戻っておいで。