私的世界十大小説。この世に二つとない名作文学ランキング
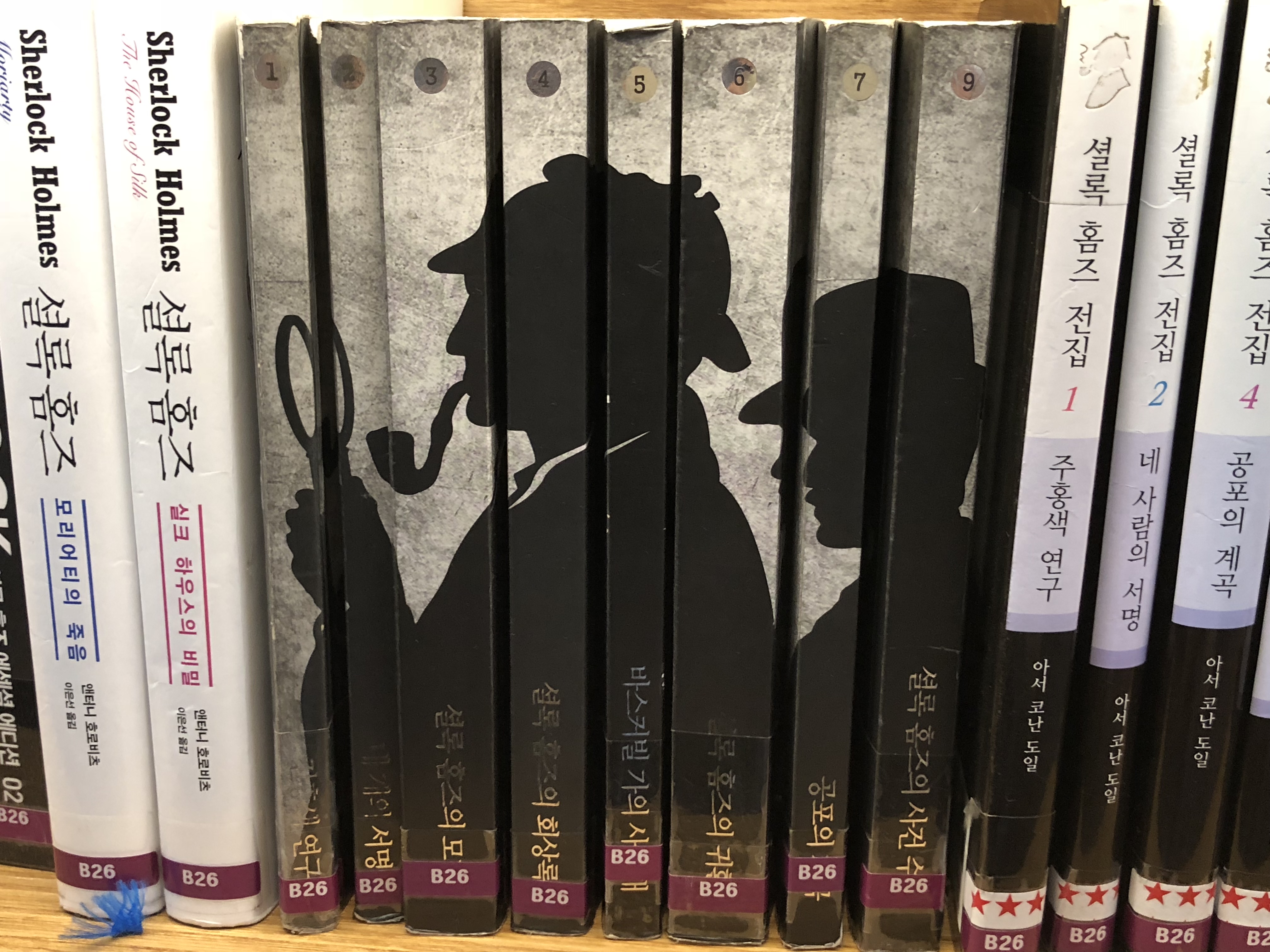 このページでは読書家の私アリクラハルトが、俺的世界十大小説を挙げていこうと思います。文学的に名作か、という観点にプラスして、自分(=私アリクラハルト)の人生にどれほど大きな影響を与えたか、という観点で十大小説を決めています。「その文学の歴史的な意味・価値」などは考慮していません。つまり後発作品の方が先行作品よりも有利となる傾向があります。文学は影響されておもしろく発展するからです。
このページでは読書家の私アリクラハルトが、俺的世界十大小説を挙げていこうと思います。文学的に名作か、という観点にプラスして、自分(=私アリクラハルト)の人生にどれほど大きな影響を与えたか、という観点で十大小説を決めています。「その文学の歴史的な意味・価値」などは考慮していません。つまり後発作品の方が先行作品よりも有利となる傾向があります。文学は影響されておもしろく発展するからです。
そして『夜と霧』の中で、あなたの人生は全宇宙にたった一度、そしてふたつとないあり方で存在していると誇らしく語られたとおりに、このランキングは私アリクラハルトの人生にどれほど大きな影響を与えたかを考慮しています。だからこの世に二つとない名作文学ランキングとなっています。ご了承ください。
『夜と霧』ヴィクトール・E・フランクル
読書家の私が「読むべき本をたった一つだけ推薦してくれ」と言われたらこの本を紹介します。ナチスによって強制収容所に入れられたユダヤ人精神科学者ヴィクトール・E・フランクルが収容所体験を書いた『夜と霧』。
生きることに意味があるなら苦しむことにも意味があるはずだ。生きることは時々刻々問いかけてくる。ひとえに行動によって、適切な態度によって、正しい答えは出される。生きることの要請と存在することの意味は、人により、また瞬間ごとに変化する。したがって生きる意味を一般論で語ることはできないし、この意味への問いに一般論で答えることもできない。生きることとは、つねに具体的な何かであって、とことん具体的だ。その具体性が、ひとりひとりにたった一度、他に類を見ない人それぞれの運命をもたらすのだ。誰も、そしてどんな運命も比類ない。どんな状況も二度と繰り返されない。運命が人間を苦しめるなら、人はこの苦しみを、たった一度だけ課される責務としなければならないだろう。人間は苦しみと向きあい、この苦しみに満ちた運命とともに、全宇宙にたった一度、そしてふたつとないあり方で存在しているのだという意識にまで到達しなければならない。この運命を引き当てたその人自身がこの苦しみを引き受けることに、ふたつとない何かをなしとげるたった一度の可能性はあるのだ。
『サド侯爵夫人』三島由紀夫
キリスト教文学者といってもいいんじゃないかと思うほど反キリストの文学者サドと三島由紀夫の共同執筆(ついでに澁澤龍彦を加えてもいいでしょう)が、奇跡の作品を生み出しました。それが戯曲『サド侯爵夫人』。偉大な人間には偉大な敵がいる、というアフォリズムがあります。サドが怪物と呼ばれるのはキリスト教に徹底的に抗ったからに他なりません。イエスの奇跡に対し、性欲と理性で対抗しました。その生涯は不幸で無残な敗北だったかもしれません。でも無駄ではありませんでした。神の敵について考えれば考えるほど、神についても考えざるを得ないからです。だからサドは殉教者と呼ばれることもあるのです。サドはフランス革命を生きた人物です。虐げるものと虐げられるものの逆転する、それが革命でした。上と下が逆転するのです。天地がひっくり返ります。神と悪魔も逆転するかもしれませんよ。
ルネ「かけがえのない? あなたこそ、かけがえのきくことを何よりの誇りになさっている方のはずですのに」
ルネ「それぞれの抽斗に人間を区分けしてお入れになる。モントルイユ夫人には正しさを、アルフォンスにはぞっとする悪徳を。でも地震で抽斗が引っくりかえり、あなたは悪徳の抽斗に、アルフォンスは正しさの抽斗に入れられるかもしれませんわ」
サン・フォン「子どもは親や世間から与えられえた遠眼鏡を逆さに使って見ております。そして健気にも世間の道徳やしきたりの命ずるままに、世間の人と同じように安楽に暮らそうという望みさえ抱きはじめます。でも、ある日、突然それが起こります。今まで眺めていた遠眼鏡は逆さまで、本当はこんな風に、小さなほうの覗き口に目を当てるのが本当だという、その発見をする大きな転機が。そのとき今まで見えなかったものが突然如実に見え、遠い谷間から吹く硫黄の火が見え、森の中で牙をむき出す獣の赤い口が見え、自分の世界は広大で、すべてが備わっていることを知るのです」
ルネ「アルフォンスは日に夜を継いで、牢屋の中でこれを書き続けました。何のために? 牢屋の中で考えに考え、書きに書いて、アルフォンスは私を、一つの物語の中へ閉じ込めてしまった。一つの恐ろしい物語の、こんな成就を助けるためだけに、私たちは生き、動き、悲しみ、叫んでいたのでございます。私たちが住んでいるこの世界は、サド侯爵が創った世界なのでございます。バスティユの牢が外側の力で破られたのに引きかえて、あの人は内側から鑢一つ使わずに牢を破っていたのです。牢はあの人のふくれ上がる力でみじんになった。そのあとでは、牢にとどまっていたのはあの人が、自由に選んだことだと申せましょう」
このブログの作者アリクラハルトは小説を書いています。わたしが作家になろうと決めたことには『サド侯爵夫人』が決定的な影響をあたえています。卒論も『サド侯爵夫人』論(文学部)を書いています。
× × × × × ×
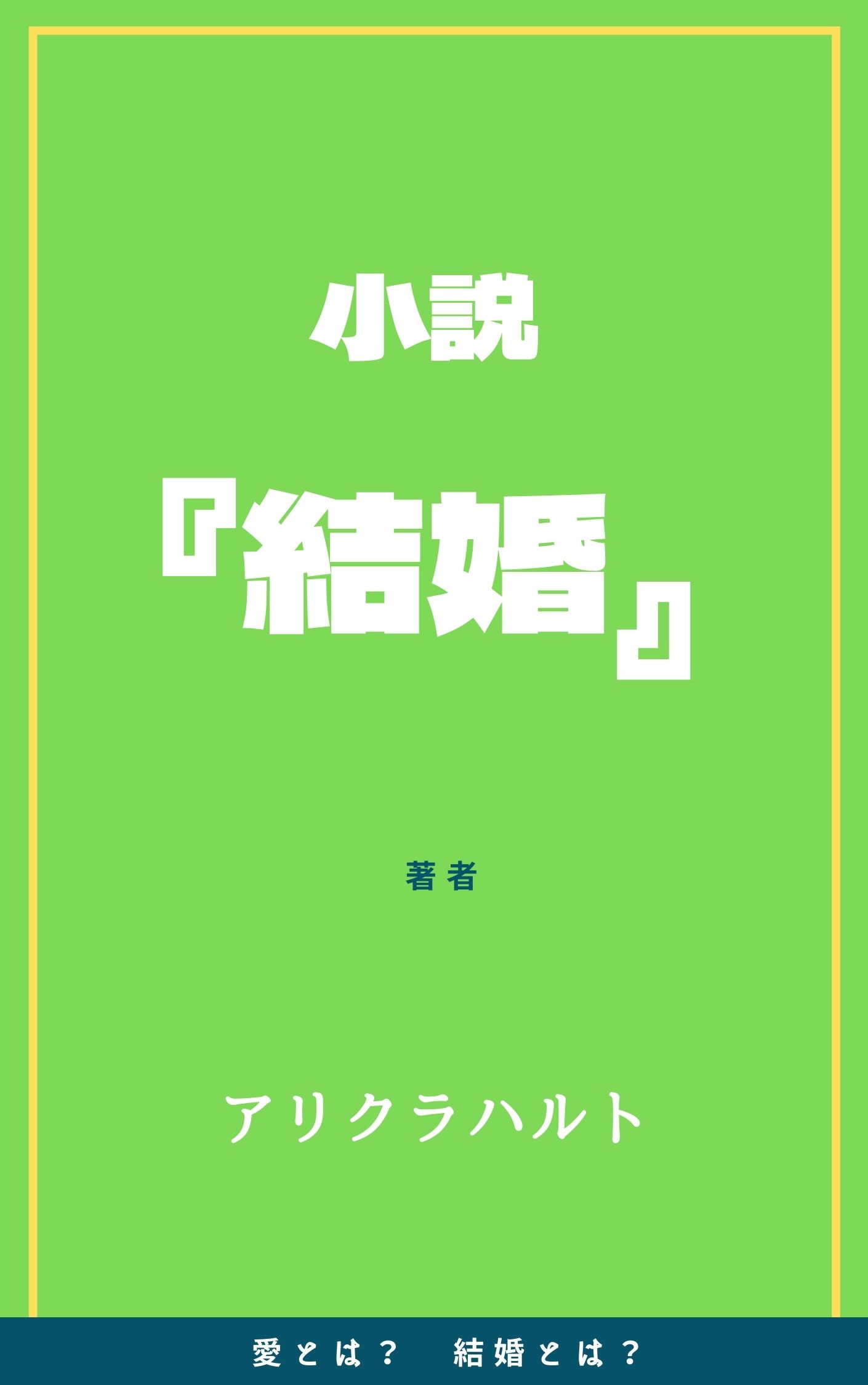
このブログの著者が執筆した純文学小説です。
「かけがえがないなんてことが、どうして言えるだろう。むしろ、こういうべきだった。その人がどんな生き方をしたかで、まわりの人間の人生が変わる、だから人は替えがきかない、と」
「私は、助言されたんだよ。その男性をあなたが絶対に逃したくなかったら、とにかくその男の言う通りにしなさいって。一切反論は許さない。とにかくあなたが「わかる」まで、その男の言う通りに動きなさいって。その男がいい男であればあるほどそうしなさいって。私は反論したんだ。『そんなことできない。そんなの女は男の奴隷じゃないか』って」
本作は小説『ツバサ』の後半部分にあたるものです。アマゾン、楽天で無料公開しています。ぜひお読みください。
× × × × × ×
『月と六ペンス』サマセット・モーム
「芸術至上主義」といえば芥川龍之介『地獄変』(1918年)で炎に焼かれる娘の姿を描く絵師を思い浮かべる日本人が多いのではないかと思いますが、私はサマセット・モーム『月と六ペンス』(1919年)を思い浮かべます。
サラリーマンだった画家の主人公ストリックランドは、突如、画家になります。いろいろあって最後はタヒチに行くのですが、不治の病で失明してしまいます。視力を失いながらもストリックランドは、木の家の壁一面に『秘められた自然の深みにわけ入り、美しくも恐ろしい、知ってはならない秘密を探し当てたような』生涯の大傑作を描きあげるのです。『雄大で冷淡、美しく残酷な大自然への賛歌のような、黒魔術を思わせるような原始的で、恐ろしい絵』を死の直前まで描き続けて、描きあげて、ストリックランドは死にました。ストリックランドは、傑作だと自分でもわかっている、自分の人生のすべてといってもいい生涯最後の大壁画を、ほかの誰にも見せることなく、自分の意思で焼いて無にかえしてしまうのです。生涯の苦痛も、すべてはこの絵のためにあったというのに。
まさに『地獄変』です。『地獄変』の絵師・良秀は作品を残して自分は自殺してしまうのですが、『月と六ペンス』の画家・ストリックランドは書き上げた自分の畢生の大作を燃やしてしまいます。どうしてストリックランドは生涯最大の大傑作を灰にしてしまったのでしょうか?
私はこう解釈しています。ストリックランドは大自然とか世界の美しさにインスパイアされて傑作を書き上げたけれど、彼の傑作がなくなっても、傑作を生みだした母体である自然や人間世界はまだ残っています。オリジナルがある限り、他の誰かの手で、傑作はまた再現されることでしょう。ストリックランドは「すばらしいものは自分の絵ではなく、オリジナルである世界そのものだ」と考えていたのではないでしょうか。オリジナルが残っているから、絵の方は燃やしてもよかったんじゃないのかな、というのがわたしの感想です。
『ナイチンゲールと薔薇』オスカー・ワイルド
「赤い薔薇をもってきてくださったら、あなたと踊ってあげるわと彼女は言ったんだ。」
愛の痛みを描いた名作です。作品を読んでこれほど「痛い」と思ったことはありません。オスカー・ワイルドの『ナイチンゲールと薔薇』。
男子学生が憧れの女性と舞踏会で踊るためには赤い薔薇のプレゼントが必要でした。しかし季節外れの赤い薔薇は簡単には手に入りません。赤い薔薇がほしければ、月の光を浴びながら、小鳥が歌を歌い、心臓を薔薇の棘に捧げて、血で薔薇を赤く染めなければならないのでした。
一晩中ナイチンゲールは歌った。そして棘がだんだん深く胸に突き刺さり、生き血が全身から減っていくのだった。月が耳をかたむけている。その歌はいちだんと激しくなっていった。男と乙女の魂に生まれた情熱を歌ったからである。苦痛は途方もなく激しく、ナイチンゲールの歌はますます狂おしいばかりのものになっていった。というのも、死によって完成される愛を、墓の中でも死滅することのない愛を歌っていたからだ。
『ナイチンゲールと薔薇』のナイチンゲールはみずから心臓を薔薇の棘に捧げます。心臓の血の赤が薔薇の赤色になるというイメージが、痛みをともなう強烈な読後感として残りました。
哲学がいくら賢くても、愛の方が賢いし、権力がいくら強くても、愛の方が強い。
ただそう語られても何も心に残りませんが、ナイチンゲールが心臓を自ら刺し貫く痛々しいイメージに言葉が重なって、強烈な印象となって残ります。
世紀末デカダンス。オスカー・ワイルドの最高傑作『ナイチンゲールと薔薇』
『マノン・レスコー』アベ・プレヴォ
男女の恋愛を描いた作品はこの世にたくさんありますが、歴史上最高の恋愛小説といったらば、あなたは何を推しますか? 私だったら『マノン・レスコー』を推薦します。『マノンレスコー』は、男が女にひたすら恋をして、世の掟や宗教的な戒律をひたすら破って恋のために没落していくという物語です。あまりにマノンを愛しすぎているために、いちばん不幸な人間になった男……『マノン・レスコー』の主人公は実はマノンではありません。世界の果てまで行こうとも、マノンの後を追っていこうとする騎士グリューこそが真の主人公です。見るべきなのは、マノンの魅力ではなく、恋の魔力にボロボロになっていくグリューの姿です。
「みなすべて愚かしい空想だった。宗門の幸福など、おまえの視線にあったら、ぼくの心の中に一分だって居座っていることなどできない」彼女のあらゆる欠点に目をふさぐためには、彼女に惚れているというだけでじゅうぶんだった。「ぼくのこころを取ってくれ。きみに捧げることのできるただひとつのものだ」マノンが、マノンのことが、マノンの危急が、マノンを失わねばならないことが、私を混乱させて、私の眼前を真っ暗にし、ために私はどこにいるのかわからないくらいだった。
「ちがう。ちがう。きみと一緒にいてふしあわせなのは、ぼくにとってねがったりかなったりの運命なんだ」
「どこまで行くのですか?」「世界のはずれまでだ。マノンと永久に離れないですむところまでだ」
マノンのためにすべてを失い、すべてを捨ててしまうなさけない騎士グリューがときどきカッコよく見えてしまうのがファムファタールの最高傑作『マノン・レスコー』なのでした。
『星の王子さま』サン・テグジュペリ

大人になってから読み返してすばらしい名作だと思ったのがサン・テグジュペリ『星の王子さま』です。おとな読書で寓話の意味が分かるとなるほどこういうことを言いたかったのか、と作者の本心がわかります。『星の王子さま』には、女性に対する接し方、夫婦円満の秘訣なんかが書かれているんですよ。星の王子さまは赤い花とうまくいかずに星を出ます。この際、おとな読書で、バラは女性と読み替えましょう。女性とうまくいかずに、離婚、家出したのです。
友だちになれば別だ。他の人が来たら地面の下に逃げるけれど、きみが友だちになってくれたならきみの足音はきっと音楽みたいにおれを穴から誘い出す」「人間は愛したことしか学べない。今は意味のない小麦の黄金色が、きみを好きになったら、君が小麦のような金色の髪をしているから、おれは小麦を見るときみを思い出すようになる。小麦畑を渡る風を聞くのが好きになる」「10万匹のどれとも違わないただのキツネが世界でただ一匹のキツネになったように、ぼくの星のバラはバラ園のバラ全部をあわせたよりももっと大事だ。なぜってあれが僕が世話した、僕の花だから」「時間をかけて一緒に過ごしたことが重要なんだ」「心で見るんだ。大切なことは目には見えない」
キツネと出会い、たいせつなことを教わります。そしてもう一度、王子さまはバラ園に戻ると、自分の星のバラと、バラ園のバラは全く違うことに気づくのです。以前は同じに見えたのに。とうとう愛の秘密に王子さまは気づきました。世の中にいくらでもいる女たちよりも、自分の恋人の方が大事だということがわかったのです。愛の秘密を『星の王子さま』は教えてくれます。
『オシャレ泥棒』中森明夫
「オタク」という言葉の生みの親だとされている中森明夫さんの書いた『オシャレ泥棒』(1988年)。どうりで言葉のセンスが卓越しているわけです。作品タイトルからしてオードリー・ヘップバーンの映画を連想させますし、東京の風俗をモロに描いてしまっているので今読むと「古いな」と感じる描写が多くてひじょうに損をしているのは確かです。
※マルセル・プルースト『失われた時を求めて』なども当時の貴族らのオシャレ風俗をモロに描いています。そして過去の風俗を知ることができるものとして高い評価を得ています。『オシャレ泥棒』ももっと時間がたてば、古い時代の風俗を知ることができる本として、古いがゆえに面白いという高評価を得られる日が来るかもしれません。
古すぎないゆえに今は「古いな」と思う描写が多いのですが、それを補ってあまりある恐るべき名作だと思います。「カワイイを超えたモノ、愛以上のモノをさがして」オシャレなものを泥棒する女子高校生のミッキーとミニー。彼女たちは「世界の果ての愛以上の場所」で死と向き合います。(オシャレ風俗がモロに描かれているのは、文芸雑誌への連載ではなく、ファッション雑誌への連載だったことが原因と思われます)
「……こわい」そのコワイはカワイイと聞こえた。命がけのことってあるよ。それは、生きること! 生きるってことは命がけの飛躍の連続さ。私たちは誰もが常に断崖絶壁の突端で目隠しをしてダンスしてる。この地上に永遠の生命を持つ者がいるとすれば、その目から見れば、私たちの一生はまるで一瞬のきらめきにすぎないかもしれない。真のたたかいとは負けるとわかっていながらもなお、そのたたかいを戦い抜くことなんだ。決して勝てぬたたかい、真のたたかいを戦うために、人は愛という武器を発明したんじゃないのかな。愛なんてないのさ。もともとなかったのさ。言葉があるからあるように思っていただけさ。でも、ないものを信じるんだ。戦うためにね。ないからこそ信じるんだ。それはもはや“愛を超えた愛”だ。地獄の果てまで私を連れ去るがいい。そこは恐らくは永遠の無だ。瞬間さ、この瞬間だけが生きているんだ。神さまなんていらない。私は神様に背を向けて、この瞬間を抱きしめていよう。
これだけでも歴史的な名作だと言っていいと思いますが、『オシャレ泥棒』はさらに感動的なエンディングへと進んでいきます。「本当の最終章 すべて少女に帰るまで」と。
少女たち——なぜ目覚めなかったのか? 目覚めるチャンスはいくらでもあったのに。目覚めなさい! 目覚めなさい、少女達! 「それはそれはすごい数の女の子たちの集団でした。まるでこの世のすべての女のコ達が集まったかのようでした。女のコたちは救助したミッキーとミニーを「わっ」と取り囲むと、あっという間に二人を自分たちの集団に紛れ込まれてしまいました。二人は完全に女の子たちの集団に交じりあってしまいました。いや、女のコ達の中へ「帰っていった」といったほうが正確かもしれません」「オシャレ泥棒をつかまえようと思ったら、この世のすべての女のコ達を逮捕しなければならないだろう」
ミッキーとミニーは「あなた」なんですよ。そんな素晴らしいエンディングでした。
『BORN TO RUN 走るために生まれた』クリストファー・マクドゥーガル
小説ではありませんが、『走るために生まれた』を俺の世界十大小説の中に入れたいと思います。この本は「なぜ走るのか」から始まって「走ることで人間はいい人間になれるのか?」という精神論から「もしかしたら人間は走ることで脳を巨大化させて今の人間になったのではないか?」という人間進化論にまで及ぶ壮大な物語です。
走ることは人類最初の芸術。稲妻が走り、光が交錯する——そう、走る人類(ランニングマン)だ。走ることは太古の祖先から遺伝子に組み込まれてきた宿命なのだ。われわれは走るために生まれた。走るからこそ生まれた。誰もが走る民族なのであり、それをタラウマラ族は一度も忘れたことがない。
走ることはわれわれの種としての想像力に根ざしていて、想像力は走ることに根ざしている。言語、芸術、科学。スペースシャトル、ゴッホの『星月夜』、血管内手術。いずれも走る能力にルーツがある。走ることこそ、我々を人間にしたスーパーパワー——つまりすべての人間が持っているスーパーパワーなのだ。
内容もさることながら、マクドゥーガルの文章には人を惹きつけるものがあります。訳者がいいのかな。こんな文章を私も書きたいなと思います。
「アフリカで毎朝、一頭のガゼルが目を覚ます。そのガゼルはいちばん速いライオンに走り勝たなければ、殺されることを知っている。アフリカで毎朝、一頭のライオンが目を覚ます。そのライオンはいちばん遅いガゼルよりも速く走らなければ、飢え死にすることを知っている。ライオンであるかガゼルであるかは関係ない。日が昇ったら、走ったほうが身のためだ」
すべての走る哺乳類が一歩進み一歩呼吸するという同じサイクルにしばられていたのだ。例外は全世界にひとつだけだった。あなただ。
これほど異様なまでに……普通の顔をしている者は。けろっとしている。
これは自己補正装置なんだ。(厚いソールは)煙探知機の電源を切るようなものだ。
『BORN TO RUN 走るために生まれた』の内容、書評、感想そして矛盾点。
『BORN TO RUN』と『サド侯爵夫人』がなかったら、私がこの本を世に上梓することはなかったでしょう。
× × × × × ×
※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?
いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。
●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?
●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?
●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。
●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。
●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?
●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」
本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。
※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。
星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。
× × × × × ×
『ツバサ』アリクラハルト
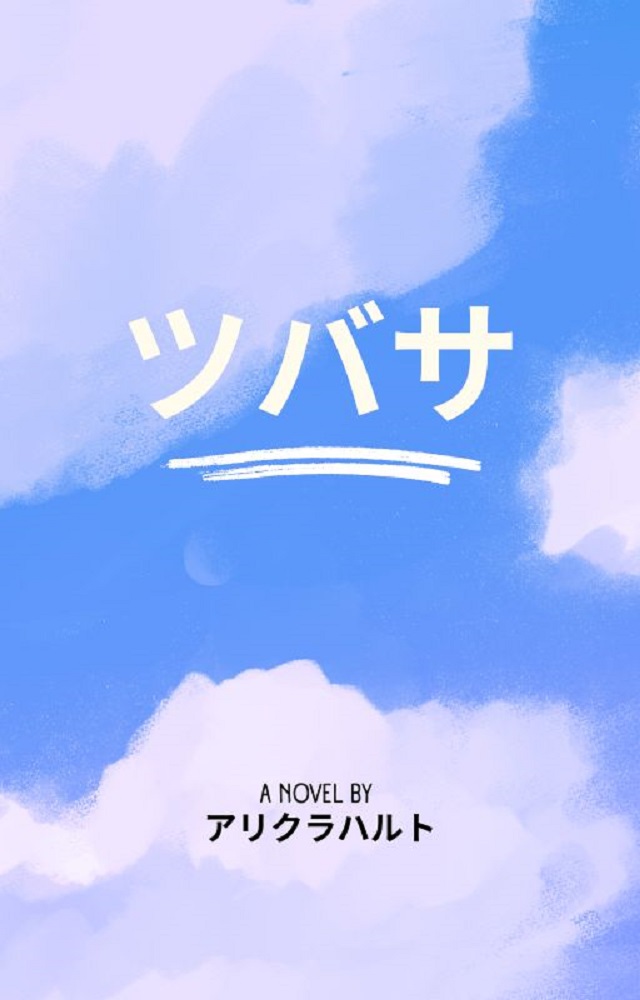
知っていますか? 自分にとって最高の小説は自分にしか書けないということを。
多くの小説家は、自分が最高に読みたい小説をさがして、とうとうそれは自分が書くしかないのだと気づいて書き始めるのです。自分の理想を実現できるのは自分以外にないのです。
私アリクラハルトも同じです。私にとって最高の小説とは、自分が書いた小説に他なりません。自分が最も読みたいものを、自分がもっともかっこいいと思うことを、自分のもっとも心地よい文体で書いたものが自分の小説だからです。
そういう意味で私にとって最高の小説は自作小説『ツバサ』に他なりません。これが私以外の人にとっても最高だったらこれ以上のよろこびはないのですが……
× × × × × ×
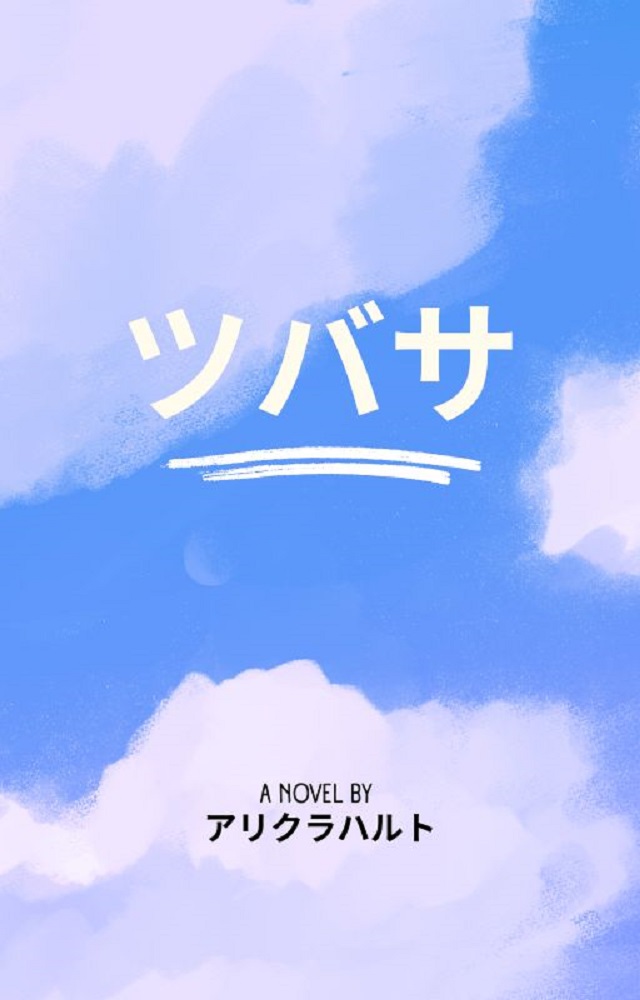
主人公ツバサは小劇団の役者です。
「演技のメソッドとして、自分の過去の類似感情を呼び覚まして芝居に再現させるという方法がある。たとえば飼い犬が死んだときのことを思い出しながら、祖母が死んだときの芝居をしたりするのだ。自分が実生活で泣いたり怒ったりしたことを思いだして演技をする、そうすると迫真の演技となり観客の共感を得ることができる。ところが呼び覚ましたリアルな感情が濃密であればあるほど、心が当時の錯乱した思いに掻き乱されてしまう。その当時の感覚に今の現実がかき乱されてしまうことがあるのだ」
恋人のアスカと結婚式を挙げたのは、結婚式場のモデルのアルバイトとしてでした。しかし母の祐希とは違った結婚生活が自分には送れるのではないかという希望がツバサの胸に躍ります。
「ハッピーな人はもっと更にどんどんハッピーになっていってるというのに、どうして決断をしないんだろう。そんなにボンヤリできるほど人生は長くはないはずなのに。たくさん愛しあって、たくさん楽しんで、たくさんわかちあって、たくさん感動して、たくさん自分を謳歌して、たくさん自分を向上させなきゃならないのに。ハッピーな人達はそういうことを、同じ時間の中でどんどん積み重ねていっているのに、なんでわざわざ大切な時間を暗いもので覆うかな」
アスカに恋をしているのは確かでしたが、すべてを受け入れることができません。かつてアスカは不倫の恋をしていて、その体験が今の自分をつくったと感じています。それに対してツバサの母は不倫の恋の果てに、みずから命を絶ってしまったのです。
「そのときは望んでいないことが起きて思うようにいかずとても悲しんでいても、大きな流れの中では、それはそうなるべきことがらであって、結果的にはよい方向への布石だったりすることがある。そのとき自分が必死にその結果に反するものを望んでも、事態に否決されて、どんどん大きな力に自分が流されているなあと感じるときがあるんだ」
ツバサは幼いころから愛読していたミナトセイイチロウの作品の影響で、独特のロマンの世界をもっていました。そのロマンのゆえに劇団の主宰者キリヤに認められ、芝居の脚本をまかされることになります。自分に人を感動させることができる何かがあるのか、ツバサは思い悩みます。同時に友人のミカコと一緒に、インターネット・サイバーショップを立ち上げます。ブツを売るのではなくロマンを売るというコンセプトです。
「楽しい、うれしい、といった人間の明るい感情を掘り起こして、その「先」に到達させてあげるんだ。その到達を手伝う仕事なんだよ。やりがいのあることじゃないか」
惚れているけれど、受け入れられないアスカ。素直になれるけれど、惚れていないミカコ。三角関係にツバサはどう決着をつけるのでしょうか。アスカは劇団をやめて、精神科医になろうと勉強をしていました。心療内科の手法をツバサとの関係にも持ち込んで、すべてのトラウマを話して、ちゃんと向き合ってくれと希望してきます。自分の不倫は人生を決めた圧倒的な出来事だと認識しているのに、ツバサの母の不倫、自殺については、分類・整理して心療内科の一症例として片付けようとするアスカの態度にツバサは苛立ちます。つねに自分を無力と感じさせられるつきあいでした。人と人との相性について、ツバサは考えつづけます。そんな中、恋人のアスカはツバサのもとを去っていきました。
「離れたくない。離れたくない。何もかもが消えて、叫びだけが残った。離れたくない。その叫びだけが残った。全身が叫びそのものになる。おれは叫びだ」
劇団の主宰者であるキリヤに呼び出されて、離婚話を聞かされます。不倫の子として父を知らずに育ったツバサは、キリヤの妻マリアの不倫の話しに、自分の生い立ちを重ねます。
「どんな喜びも苦難も、どんなに緻密に予測、計算しても思いもかけない事態へと流れていく。喜びも未知、苦しみも未知、でも冒険に向かう同行者がワクワクしてくれたら、おれも楽しく足どりも軽くなるけれど、未知なる苦難、苦境のことばかり思案して不安がり警戒されてしまったら、なんだかおれまでその冒険に向かうよろこびや楽しさを見失ってしまいそうになる……冒険でなければ博打といってもいい。愛は博打だ。人生も」
ツバサの母は心を病んで自殺してしまっていました。
「私にとって愛とは、一緒に歩んでいってほしいという欲があるかないか」
ツバサはミカコから思いを寄せられます。しかし「結婚が誰を幸せにしただろうか?」とツバサは感じています。
「不倫って感情を使いまわしができるから。こっちで足りないものをあっちで、あっちで満たされないものをこっちで補うというカラクリだから、判断が狂うんだよね。それが不倫マジックのタネあかし」
「愛する人とともに歩んでいくことでひろがっていく自分の中の可能性って、決してひとりでは辿りつけない境地だと思うの。守る人がいるうれしさ、守られている安心感、自信。妥協することの意味、共同生活のぶつかり合い、でも逆にそれを楽しもうという姿勢、つかず離れずに……それを一つ屋根の下で行う楽しさ。全く違う人間同士が一緒に人生を作っていく面白味。束縛し合わないで時間を共有したい……けれどこうしたことも相手が同じように思っていないと実現できない」
尊敬する作家、ミナトセイイチロウの影響を受けてツバサは劇団で上演する脚本を書きあげましたが、芝居は失敗してしまいました。引退するキリヤから一人の友人を紹介されます。なんとその友人はミナトでした。そこにアスカが妊娠したという情報が伝わってきました。それは誰の子なのでしょうか? 真実は藪の中。証言が食い違います。誰かが嘘をついているはずです。認識しているツバサ自信が狂っていなければ、の話しですが……。
「妻のことが信頼できない。そうなったら『事実』は関係ないんだ」
そう言ったキリヤの言葉を思い出し、ツバサは真実は何かではなく、自分が何を信じるのか、を選びます。アスカのお腹の中の子は、昔の自分だと感じていました。死に際のミナトからツバサは病院に呼び出されます。そして途中までしか書いていない最後の原稿を託されます。ミナトの最後の小説を舞台上にアレンジしたものをツバサは上演します。客席にはミナトが、アスカが、ミカコが見てくれていました。生きることへの恋を書き上げた舞台は成功し、ツバサはミナトセイイチロウの後を継ぐことを決意します。ミナトから最後の作品の続きを書くように頼まれて、ツバサは地獄のような断崖絶壁の山に向かいます。
「舞台は変えよう。ミナトの小説からは魂だけを引き継ぎ、おれの故郷を舞台に独自の世界を描こう。自分の原風景を描いてみよう。目をそむけ続けてきた始まりの物語のことを。その原風景からしか、おれの本当の心の叫びは表現できない」
そこでミナトの作品がツバサの母と自分の故郷のことを書いていると悟り、自分のすべてを込めて作品を引きついて書き上げようとするのでした。
「おまえにその跡を引き継ぐ資格があるのか? 「ある」自分の中にその力があることをはっきりと感じていた。それはおれがあの人の息子だからだ。おれにはおれだけの何かを込めることができる。父の遺産のその上に」
そこにミカコから真相を告げる手紙が届いたのでした。
「それは言葉として聞いただけではその本当の意味を知ることができないこと。体験し、自分をひとつひとつ積み上げ、愛においても人生においても成功した人でないとわからない法則」
「私は、助言されたんだよ。その男性をあなたが絶対に逃したくなかったら、とにかくその男の言う通りにしなさいって。一切反論は許さない。とにかくあなたが「わかる」まで、その男の言う通りに動きなさいって。その男がいい男であればあるほどそうしなさいって。私は反論したんだ。『そんなことできない。そんなの女は男の奴隷じゃないか』って」
× × × × × ×
おれの世界十大作品選びはこれからも続く
えっ? 十作品揃ってないじゃないかって?
……実は私の読書はこれからも続きます。そして十大小説はこれから完成するのです。
すでに挙げた作品は、おそらくこれから私がどんな作品を読もうとも、十大作品から滑り落ちることはないだろうと確信している最高峰の作品たちです。
あなたがもしもこのページのことを覚えていたら、数年後に再び閲覧に来てください。そのとき、もしかしたら十大小説のコラムは完成しているかもしれません。
偉大な小説たちに喝采を!!


