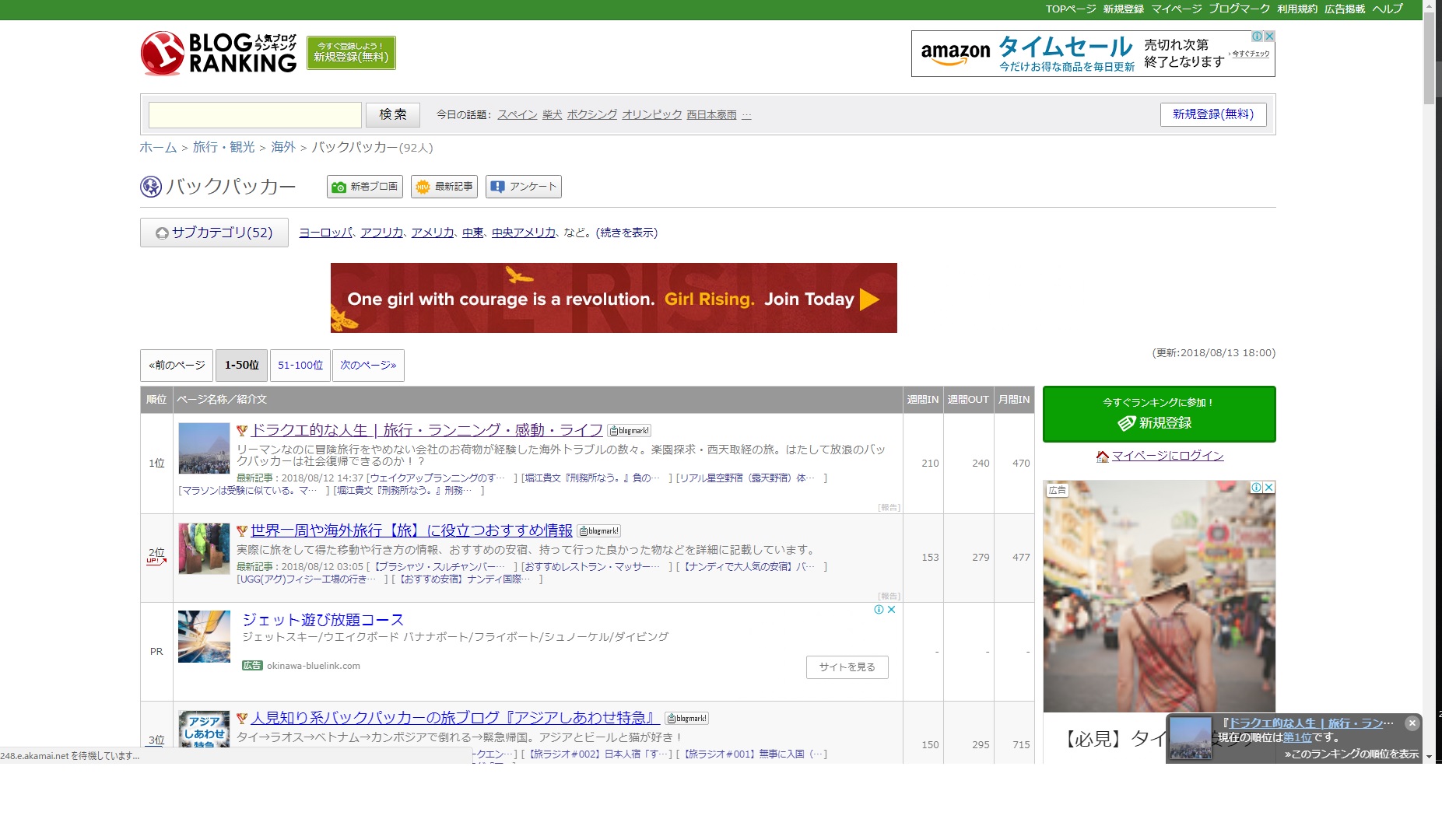私の住んでいるところは関東平野の中ほどです。ウェイクアップ・ランニングで川の土手に登ると、晴れた日には富士山がよく見えます。日光男体山も、筑波山も見えます。遠くの百名山が非常によく見えるのです。それはとりもなおさず視界をさえぎる遮蔽物が何もないということです。里山のようなものさえありません。どうしてこうも関東平野は真っ平なのでしょうか。
× × × × × ×

このブログの作者の書籍『通勤自転車から始めるロードバイク生活』のご紹介
この本は勤務先の転勤命令によってロードバイク通勤をすることになった筆者が、趣味のロードバイク乗りとなり、やがてホビーレーサーとして仲間たちとスピードをガチンコで競うようになるところまでを描いた自転車エッセイ集です。
※書籍の内容
●スピードこそロードバイクのレーゾンデートル
●軽いギアをクルクル回すという理論のウソ。体重ライディング理論。体重ペダリングのやり方
●アマチュアのロードバイク乗りの最高速度ってどれくらい?
●ロードバイクは屋外で保管できるのか?
●ロードバイクに名前をつける。
●アパートでローラー台トレーニングすることは可能か?
●ロードバイククラブの入り方。嫌われない新入部員の作法
●ロードバイク乗りが、クロストレーニングとしてマラソンを取り入れることのメリット・デメリット
●ロードバイクとマラソンの両立は可能か? サブスリーランナーはロードバイクに乗っても速いのか?
●スピードスケートの選手がロードバイクをトレーニングに取り入れる理由
初心者から上級者まで広く対象とした内容になっています。
× × × × × ×
果たして日本はそんなに国土が狭いのか?

かつて私はインドを旅行したことがあります。
インドは広大で、移動に時間がかかります。
ド平日の格安ツアーだったため、参加しているのはほとんど女性でした。
その中の一人がこの『ドラクエ的な人生』の人気5大記事の一つである『マッサージ・足裏のプチプチ。クリスタルデポジット』の主人公である女性です。
男性は私ともう一人、定年退職して家族と旅行に来たという元大学教授の二人だけでした。
なにぶん移動時間が長いために、ツアー客同士、話す機会がたくさんありました。会話の中で、私と元大学教授はちょっとした議論になりました。
それは「果たして日本はそんなに国土が狭いのか?」というテーマです。
そりゃあインド亜大陸に比べれば日本は狭いですよ。
でも元教授があまりにも「インドは広い。日本は狭い」と繰り返すので「いやそんなに日本は狭くないですよ」と主張する私と議論になったのです。まあ、暇だったんですね。広いからインドは(笑)。
さあ。戦いのゴングが鳴りました。
「狭い日本とよく言うが、世界の国々の中でそんなに日本が狭いかといったら、そうじゃないんじゃないか」
それが私の主張でした。すくなくとも、どう見ても韓国や台湾よりは広いはずですよね。
調べてみると、日本の面積の世界ランキングは61位だそうです。世界には約200か国ありますから、やはり私が直感的に思った通り、決して日本は狭い国土ではないのです。(ちなみに「排他的経済水域EEZ」という海を含めた面積でカウントすると、世界第八位の広さとなります)
フィリピンやベトナム、ドイツやイタリアよりも日本の総面積は広いのです。なかなかのものです。
どうですか? この議論は私の勝ちではないでしょうか。
ところが元教授の一言で形勢は引っくり返ります。
「たしかに総面積は小さくないかもしれないが、国土のほとんどが山地ばかりで有効利用できる面積が小さいんだよ。だから狭い日本なんだ」
私は固まってしまいました。ぐうのねもでません。どうやら議論は私の負けのようです。
関東平野はびっくりするほど真っ平

日本最大の平野、関東平野のド真ん中あたりで暮らしていると、国土のほとんどが山地で有効利用できないということが、あまり実感できません。
関東平野には山がなく、ほとんど真っ平で、だからこそ富士山と男体山と筑波山が同時に見られるのです。視線を遮る他の山がないためです。里山すらありません。
たとえば富士山は名古屋を過ぎる(下る)ともう見られません。手前に大きな山があるからです。
ずっと関東で暮らしていると、日本全国似たような景色が広がっているものとつい思ってしまいます。ところがそうではないのです。
京都が風光明媚なのは山が近くにあるせいではないでしょうか。銀閣寺も、清水寺も、借景になる山がないと美観は成立しません。五山送り火(大文字焼き)も山があってこそのものです。京都は湧水が多く美味しいお茶が飲めると言います。それも山があってのことです(山の絞り水)。
大阪も山が近いですよね。奈良なんか山の中にある街です。
関東人は、一般的な日本人とは違う景観の中で暮らしているといってもいいかもしれません。
元教授は関東の方ではありませんでした。ご自身の実感として「山」を身近に感じていらっしゃったのではないかと思うのです。日々、山を見慣れていたのだと思うのです。その「実感」が関東人の私には足りませんでした。
私は「青春18きっぷ」で日本一周しています。「車中泊の旅」で本州をぐるりと一周しています。だから関東人ですが、元教授の一言がたちどころに理解できました。元大学教授の言葉にいさぎよく負けを認めるしかなかったのです。
川が砂を運んでつくりあげた洲のような場所というのが関東の本質

なんで関東平野だけがこうも真っ平なのか、不思議だと思いませんか?
江戸時代には日比谷あたりまでは海だったと言います。それを神田の山を削って埋め立てたのだとか。
また江戸は堀や水路を張り巡らせた水の都だったといいます。昔はトラックがないために、重たい荷物は船で運ぶのが一番効率が良かったのです。京橋とか泪橋(「あしたのジョー」のあの橋です)とか今は地名でしかありませんが、元々はそこに本当にそういう名前の橋があって、下に川が流れていたのです。
利根川の東遷を知っていますか? 坂東太郎・利根川はもともと銚子の方に流れる川ではありませんでした。江戸を利根川の水害から守るために、川の流れを人工的に変えたのです。
当時は重機(バックホウ)もなかったわけですから、すべて人力です。たいへんな作業でした。徳川将軍の権力の大きさがわかります。それらの土木工事で掘削した土で東京湾を埋め立てたようです。
しかしいくら何でもすべての里山を人力で削って真っ平にできたわけがありません。川なら何とか人力で掘削できそうな気がしますけど、山を動かすのは無理でしょう。大岩が出てきたらもうお手上げです。どうにも動かせません。
ある程度は人工的にひらたくならしたかもしれませんが、やっぱり関東は元々平野だったのでしょう。川が砂を運んでつくりあげた洲のような場所というのが関東の本質なのかもしれません。
「坂という抵抗」を味わいたい。インナーギアをつかってみたい
 元大学教授の言葉に、素直に負けを認めたのにはもう一つ理由があります。
元大学教授の言葉に、素直に負けを認めたのにはもう一つ理由があります。
私は自転車をやります。ロードバイク乗りです。ロードバイクに乗っていると、ときどき自分の住んでいる場所に物足りなくなることがあります。
もうちょっと近場にいい山はないものかな、と。山でロードバイクに乗りたくなるのです。ギアチェンジをしたくなるのです。ペダリングの負荷に緩急をつけたくなるのです。
汗が出てハアハア喘ぐほど必死に漕ぐには、まっすぐな道をフルスピードで飛ばすしか方法がありません。ロードバイクは市街地の信号や、直角に曲がるのは苦手ですから、自分を追い込んでトレーニング的に走りたいと思ったら、何もない川の土手とか農道をガンガン飛ばして走るしかないのです。
どうです? 面白そうですか? つまらなそうでしょ(泣)。
負荷・抵抗が風(空気)ばかりで嫌になるときがあります。ときには「坂という抵抗」を味わいたいのです。
時には峠に向かって軽いギアをクルクル回して、ハアハア喘ぎながらゆっくりと登ってみたいのです。
もちろん猛スピードの下りも。ああ。さぞや気持ちがいいでしょうね。
ときどき「自分はクライマー(山登りが得意な自転車乗りのタイプ)なんじゃないか」と思う時があります。とくに仲間とスピード勝負で負けた時には「平地で負けても、クライム勝負すれば負けないはず」と負け惜しみぎみに思うのですが(笑)、関東にはそれを証明する場所がないのです。そのためには筑波山とか日光とか青梅とかに行かなければなりません。
ときにはみんなで山道をツーリングしてみたいのです。平地はもう飽きたと思うことがあります。
真っ平の関東では軽いインナーギアなんて使う機会がありません。こんなギアいらない!
「関東って山がないよなア」というのは、本格的にロードバイクに乗るようになってから、ずっと思っていたことだったのです。だから元教授の言葉が胸に響いてきたのです。
そのことは普段はあまり意識しません。
平地ゆえに「楽に移動できている」恩恵をたっぷり受けていても、それが当たり前で、ありがたいとも思いません。坂の町で生まれ育った人はまた違った感想をもつのだろうと思います。
生活がすべてだというのならば、車で移動したりする分には、真っ平の平地の方がガソリンも食わないし、楽でいいのです。自転車で移動するのも平地の方が楽チンです。
しかし「遊ぶ」というのならば話は別です。登山するにも、散歩するにも、ジョギングするにも、ロードバイク乗るにも、遊ぶには近くに山があった方がいいのです。
ロードバイクは移動そのものが目的の遊具

ロードバイクは移動のための手段ではありません。移動そのものが目的の遊具です。
アップダウンはトレーニングには最適です。
また林道は気持ちが癒されます。近くに山があった方が目が休まります。人間の目は際限なく遠いところは見る気になれません。ほどほど遠い景色だから見る気になるのです。
飛鳥も、奈良も、京都も、鎌倉も、古都はたいてい山に囲まれた場所にあります。軍事上とか、水の問題とか、いろんな理由があるのでしょうが、日本人は近くに山が見える場所が単純に好きだから、なのではないでしょうか。
最高権力者は、最高に気に入った場所に住むはずです。
女性に人気があるのは長崎とか函館とか「坂の街」だと聞きました。景色が立体的になるのがいいんでしょうね。
それと同様に、ロードバイク乗りも、真っ平らな場所よりも、坂のあるところが好きなのではないでしょうか。
人生のほとんどを真っ平な場所で過ごすことになってしまいましたが、私は山が好きです。
真っ平の関東地方は、ロードバイクに向いている地域といえるでしょうか?
「乗らない人」はそう思うでしょう。「真っ平の方が楽でいいじゃん」と。
しかし「乗る人」から見ると、近くに山道がある地域の方が、ロードバイクに向いている地域のような気がしてしまうのです。