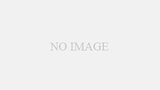絶対に風邪なんかひかないという決意が、風邪を遠ざけていたのではないだろうか

× × × × × ×
※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?
いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。
●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?
●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?
●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。
●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。
●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?
●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」
本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。
※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。
星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。
× × × × × ×
かつてサブスリーを連発していた市民ランナーだった頃、私の勝負レースは12月でした。防府読売マラソンです。
そして2月には「すべり止め」の「もうひとつの勝負レース」が入っていました。
公道を封鎖して行うマラソン大会の場合、多くの場合は都道府県などが主催もしくは重要な共催相手であることがほとんどです。
お役所が忙しい議会月の12月や3月を外してレース日は設定されていることが多いのです。知っていましたか?
となると2月は今シーズンのラストラン(シーズン最終レース)ということになります。その時期はインフルエンザの猛威が全盛の頃です。しかしシリアス市民ランナーとしては風邪なんてひいている場合ではありませんでした。インフルエンザなんて論外です。
※※※YouTube動画はじめました※※※
書籍『市民ランナーという走り方(マラソンサブスリー・グランドスラム養成講座)』の内容をYouTubeにて公開しています。言葉のイメージ喚起力でランニングフォームを最適化して、同じ練習量でも速く走れるようになるランニング新メソッドについて解説しています。
『マラソンの走り方・サブスリー養成講座』
気に入っていただけましたら、チャンネル登録をお願いします。
年に一回自己ベストを狙う市民ランナーは、真冬の時期にテストを受ける受験生のようなもの

9月ぐらいから減量し、筋肉を鍛えあげるアスリート系市民ランナー生活を送っていました。それもこれも勝負レースでベストパフォーマンスを発揮するためです。インフルエンザなんかにかかっては、これまでのすべての努力が無駄になってしまいます。
自己ベストを狙う市民ランナーは、年に一回真冬の時期にテストを受ける受験生のようなものです。受験日にインフルエンザにかかっているようでは合格は難しいでしょう。実際、アスリート系市民ランナーだった約15年間、インフルエンザはおろか風邪ひとつひいたことはありませんでした。
スポーツ選手は脳筋バカか? マラソンは受験、セックスに似ている
ところが、もはや自分はアスリートとしては引退し、次のステージへ進もうと覚悟を決めると、15年以上ぶりにインフルエンザにかかってしまいました。
たった今、私は熱でぼーっとした頭でこのブログを書いています。レースの予定も入れていないから、2月のために必死に努力してきたわけでもなく、インフルにかかったところでゆっくり休養すればいいだけの話しなのですが、『病は気から』というのは名言だなあと思いました。
去年の練習量を今年も維持することはもう無理だと感じるところから市民ランナーの引退が始まる

長距離ランナーが老衰を意識するようになるのは、フィジカル的な衰えというよりも、まず先に去年の練習量を今年も維持することはもう無理だと感じるところから始まります。
練習量の維持の不可能はすなわち自己ベスト更新の不可能ということです。それは重要なモチベーションのひとつを喪失したということです。
そこから先、どのようにモチベーションを維持するのか。
「若い人には負けて当然。でも同年代のライバルには負けない」と競争心は維持したまま奥津城まで行くのか。
それとも競争心は妄執だと捨て去り、ただ走ることが好きな自分を見つめて走り続けるか。そこで「あなた」という存在がはっきり浮き上がってくることでしょう。
× × × × × ×
※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?
いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。
●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?
●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?
●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。
●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。
●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?
●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」
本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。
※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。
星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。
× × × × × ×