※このブログの筆者の書籍です。Amazon、楽天koboで発売中。
※言葉のイメージ喚起力で速く走る新メソッドを提唱しています。
このページは、私アリクラハルトの『サブスリー養成講座』のまとめサイトです。改めてマラソン・サブスリーの難易度について考えてみたいと思います。
それぞれのサイトにリンクが貼ってありますので、気になる言葉があったら、そちらのサイトに飛んで読んでいただきたいと思っています。
また書籍化してまとめていますので、プロフィール等からご確認ください。
ここにある「言葉」は、あと数秒削り出すためのただのきっかけです。
言葉に触発されて、あなたの走り方やモチベーションが劇的に改善し、夢のサブスリーを突破されることを心から祈っています。
※このブログの「難易度」系記事
24時間テレビチャリティーマラソン(トライアスロン)の難易度
サブスリー関門突破ゲームはどれほど難しいのか
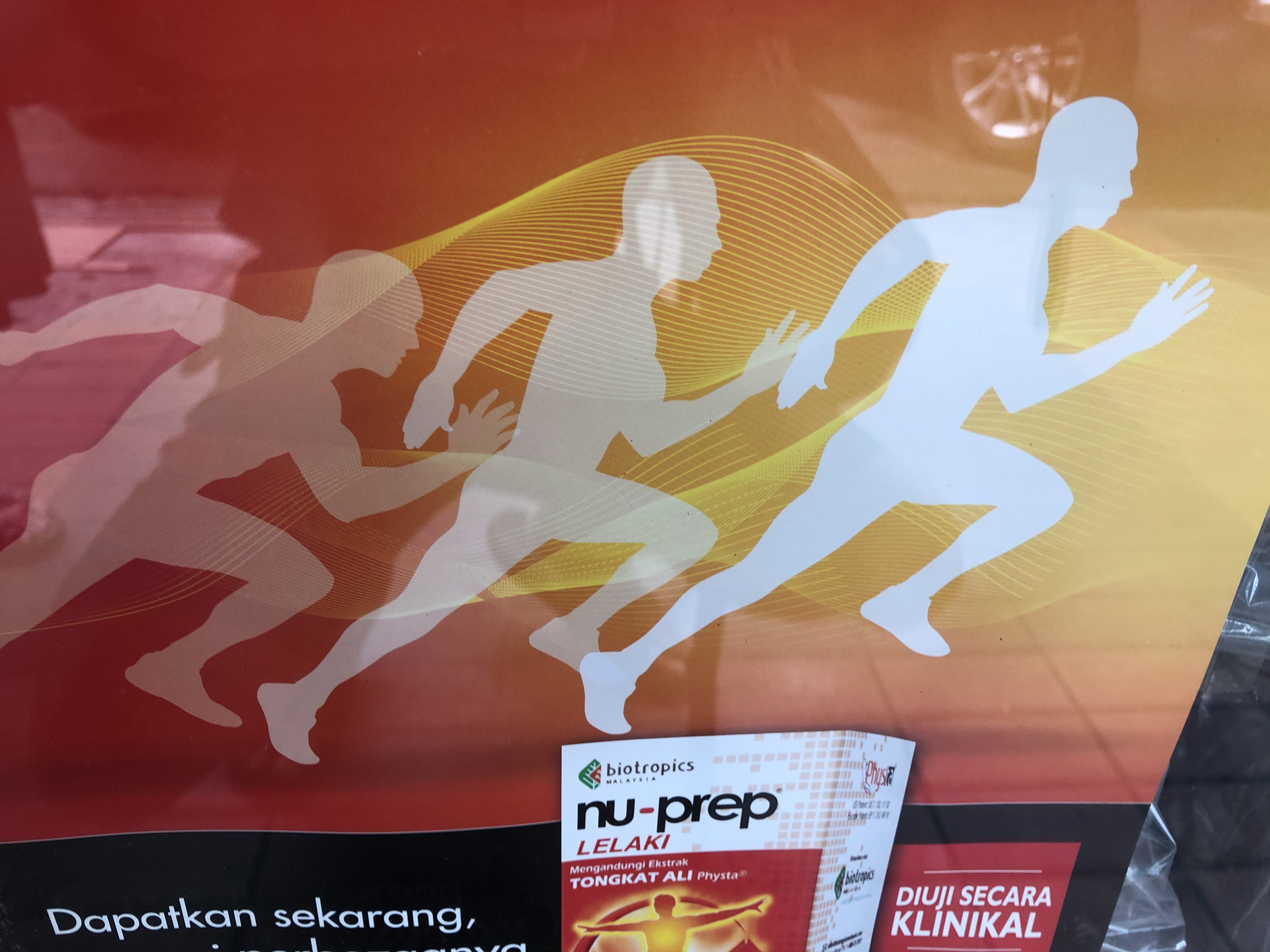
フルマラソン42.195kmを2時間台で走り切ることをサブスリー(sub-three。sub3)といいます。
3は、3時間の3(three)です。sub は、~の下、という意味の英語の接頭語です。
subwayは道(way)の下(sub)だから地下鉄。submarineは海(marine)の下(sub)だから潜水艦という意味です。
サブスリーは市民ランナーの勲章とされています。
かつて私は『サブスリーのためならドーピングも辞さず。ゴールして倒れてもいい』と思いつめて、この『関門突破ゲーム』に熱中していました。
ほとんど走るために生きているといってもいい時代は、この「サブスリー突破ゲーム」が最大の走るモチベーションとなっていました。
いやあ、本当に楽しかった!
デートの約束も後回しにして、しょっちゅう奥多摩のトレイルで修行ランニングをしていました。すべてはサブスリーのために。
ではこの『関門突破ゲーム』は、どれぐらい難しいのでしょうか。
統計によるとサブスリーランナーは市民マラソン大会の上位3~4%とされています。
しかしもともと足に自信がある人や走るのが大好きな人がエントリーしているのが市民マラソン大会です。
全人類から見ると、サブスリーランナーはどれぐらい上位に位置するのでしょうか。
日本のマラソン大会の中で、最もお祭り色が強く、最も一般市民がエントリーしているのが東京マラソンです。
その東京マラソンですとサブスリーランナーは上位1%ぐらいになります。
サブスリーランナーというのは、『そこらへんの一般市民100人がマラソンを走ったら、トップでゴールできる人』ぐらいのイメージでいいのではないかと思います。
まあなかなかの難易度なのではないでしょうか?
小中学校で学校で一番速かった子が、血尿がでるまで練習したらどこまで行けるのか?
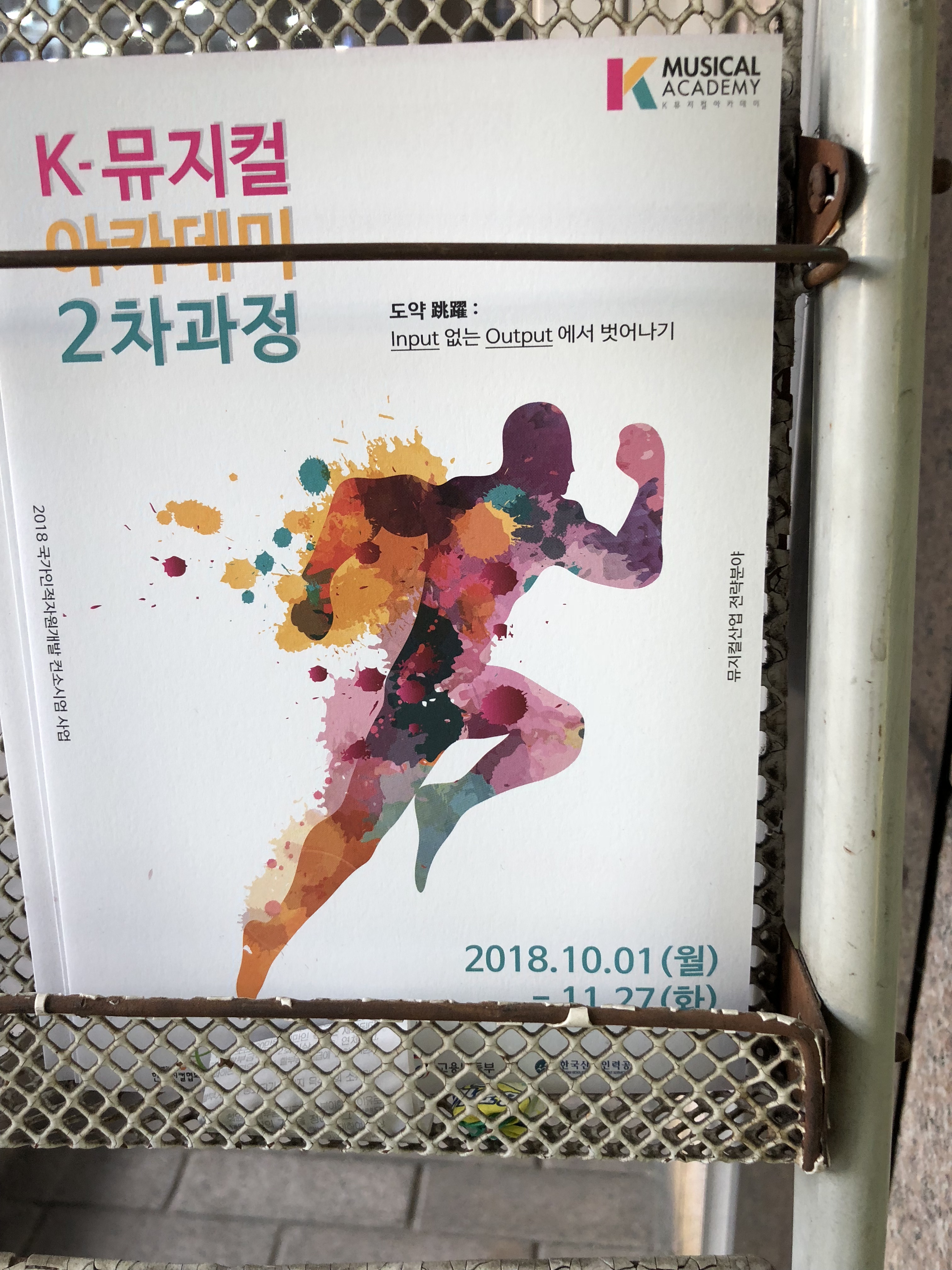
中学時代、長距離走と言えばせいぜい1500mでした。
私の中学校では体育の授業で1500m走のタイムを計られて、そのトップ5が校内の掲示板に貼りだされていました。本稿の執筆者アリクラハルトは、中学時代は、長距離走を走れば、学校中でいちばん速かったです。
小学校時代も長距離走は学校中で一番速かったです。走れば褒められる子でした。
長距離走の才能あるなしでいうならば、明らかに才能がある方でしょう。小中と学校一でしたから、いちおうそう言っておきます。
そんな人間が、月間600km走り、血尿がでるまで練習して、ゴールしたら倒れる覚悟で走って、やっと達成できたのがサブスリーでした。決して簡単なゲームではありませんでした。
しかし難しいからこそやりがいがあります。
ゲームというのは、あまり簡単すぎると面白くないものです。一度も迷うことも全滅することなく簡単にクリアできてしまうRPGが面白くないのと同じことです。
敵ボスに全滅させられ絶叫したり、リセットボタンを押したくなったり、憎らしくて夢にまで見て眠れないぐらいで、はじめて面白いゲームだったと言えるのではないでしょうか。熱中できないゲームに価値なんかありません。
「今のレベルでも、もっと効率的に戦えば、敵ボスを倒せるのではないか?」
ラスボスを研究したり、戦い方を模索したりすることで、関門突破ゲームの世界は一気に奥深くなります。
とくに私の場合は、3時間0分✖秒というのを2年連続で経験しています。あと数秒でサブスリーだったのです。しかも2年連続で。このときの悔しさといったらありませんでした。
だからこそ秒単位での勝負にこだわったのです。走法の工夫であと数秒削り出してやろうと思いました。
私にとってマラソンレースは受験によく似ています。本気の勝負レースは年に一度、一年後であり、このままサブスリーランナーになれないままで生涯を終えるのかという不安と闘いながらの二年間でした。
カラダで無理ならアタマで、フィジカルで無理ならメンタルで、関門突破ゲームをクリアする覚悟

二年間の間に考えられることは考え尽くしました。
あとわずか数秒縮めるだけでいいのです。わずか数秒縮めれば私はサブスリーランナーです。
カラダで無理ならアタマで、フィジカルで無理ならメンタルで、この関門突破ゲームをクリアしてやろうと思っていました。
脚力ではなく脳ミソでサブスリーを達成してやろうと決意したのです。
フォームについては死ぬほど研究しました。
それがこのブログで公開しているサブスリーフォームです。
効率的に速く走れるための方法であり、それを公開したものが本稿「ハルトのサブスリー養成講座」なのです。
『アトムのジェット走法』も、『カカト落としを効果的に決める走法』も、本気のサブスリー挑戦の中から生まれてきたマラソン理論です。『動的バランス走法』も『骨格走法』も『ヘルメスの靴』も『ハサミは両方に開かれる走法』も『ヤジロベエ走法』も、あと数秒を削りだすための極意のようなものです。
究極の走法『ハサミは両方に開かれる・ヤジロベエ走法』という走法は、地面という重たい抵抗を押しのけるように軸脚(支持脚)を後ろに送るよりも、スカスカの空気を切り裂いて自由に動ける遊脚(振りあげた方の脚)を前に送った方が効率的だろうという理屈です。
地面からの抵抗とは「足をその場に留めようとする」負荷・抵抗ですから、その負荷に逆らって支持脚を後ろに送るよりも、軽い空気抵抗しかない遊脚を前に送る方が、楽に前に進めるということがわかるでしょうか。
『ハサミは両方に開かれる』ので、後ろに脚を蹴らなくても、遊脚をグイっと前に出すだけで、結果として蹴ったようなフォームになるので心配はいらないのです。
オリンピッククラスのエリートランナーのマラソン中継からも多くを学びました。
なかでも川内優輝選手よりも自分の方がピッチが多いと知った時には衝撃でした。
そこから私は市民ランナーに足りないものはピッチではなくストライドだと確信を持つようになります。
サブスリー達成のためには『ピッチ走法よりもストライド走法。ダメージなんか度外視して走れ走れ』ということになります。本番レース中、私は『ジャンプしない走りなんて走りじゃない』と私は何度も自分に叫んでいます。
エリートランナーは老いてストライドが維持できなくなって引退するのです。ピッチは命のリズム感でありそう易々と衰えるものではありません。
プロの陸上コーチがピッチ走法を推奨するのは、もともと彼らが指導するエリート選手たちには天性のストライドが備わっているからであり、それをそのまま鵜呑みにしてはいけません。
日本の陸上界がこぞってピッチ走法を推奨するのは、金メダルを獲ることを目標にしているからです。金メダルをとるためには黒人選手に勝たなければなりませんが、ストライドで勝負しても黒人には勝てないために、ピッチで勝つ戦略をとるしかないからです。負ける戦略をとるわけにはいかないからです。
しかし私たち市民ランナーの目標は、黒人選手に勝つことではありません。「自己ベストを更新すること」すなわち「ベストバージョンの自分になること」自分なりの、最高の自分になることです。
難易度は相対的。ものごとの価値は目線で変わって感じるもの。
難易度というものは相対的なものです。ものごとの価値というのは目線で変わって感じるものです。
サブスリーの難易度を人類の上位1パーセントぐらいだとわたしは見積もりました。「そこらへんの人100人がマラソンを走ったらトップでゴールできる人」ということです。
「100人がマラソンを走ったらトップでゴールできる人」と聞いたら凄い人だと思いませんか? 「すごいじゃん。そいつ。ちょっと名前覚えとこうか」ぐらいのインパクトはあるのではないでしょうか。小学校で学校(学年)で一番足の速かった子の名まえをあなたも覚えているのではないでしょうか。そのぐらいのレベルです。
でも「100人がマラソンを走ったらトップでゴールできる人」というのは裏を返せば「200人がマラソンを走ったら2位かもしれない人」という意味です。トップでゴールできるか、二位になるかは相手次第です。
上位1%というのは1万人走ったら100位です。三万五千人(東京マラソンの出走者数)走ったら350位だということです。350位の人をすごいと思いますか? ちょっと名前覚えとこうと思いますか? 思いませんよね。350位なんて箸にも棒にもかからないモブ(その他大勢)だと感じると思います。
これが視点の問題ということです。誰に目線を置くかでものごとは感じ方が変わります。
オリンピックアスリートの目線で見るか、走り始めたばかりの「わたし」目線で見るかで、ものごとの価値というのは目線で変わって感じるものなのです。
このページにたどり着いて、ここまで読み進めたあなたはきっと自分が走っているランナーだと思います。オリンピックアスリートの目線から見たらサブスリーなんて難しくも何ともありません。しかしただのマラソン愛好家の「わたし」目線で見た場合、サブスリーは難しいものに感じるかもしれません。
ものごとの価値というのは目線で変わって感じるものなのです。
走法革命。再現性のある入力ワードで走法を効率化させる指導
私の場合、走ることも得意でしたが、言葉を使ってモノを表現することの方がもっと得意な人間でした。
おのれの肉体が教えてくれる走り方を、明日も明後日も再現するための「入力ワード」が走りながら、次から次へと頭の中に浮かんできます。
人間の運動は脳から筋肉に指令が出て実現しているので、昨日と同じ効率的な動きをするためには、昨日と同じ指令が脳ミソから発令される必要があります。
それを「入力ワード」といいます。「アトムのジェット走法」というのは走法ですが、脳ミソから筋骨格系への入力ワードでもあるのです。
私の紹介している言葉は、その「入力ワード」と具体的な再現方法です。
市民ランナーが速く走るために必要なのは「ストライド」です。そのためには鳥が翼を広げて飛ぶように、大腿骨を大きく動かすことが必要なのです。
大きく大腿骨を動かしながら、ゆっくり走ることはできません。「動的バランス走法」というものは「静的バランス」とは違い、スピードを出しながらでないと維持できないものなのです。
サッカーやラグビーの走りと陸上の走りは違います。
サッカー選手は横からチャージされるのが前提なので腰を落として大地を踏みしめて走ります。それに対して陸上選手は接触はないのが前提なので骨盤・腰椎をフワッと浮かせて走ります。
ヤジロベエ走法をラグビーでやったら横からタックルされてふっ飛ばされてしまいますが、そのかわり鈍足ラガーマンを振り切るほど速く走ることができるようになります。
本気でサブスリーの関門を突破したかったら、私の入力ワードを勉強してみてください。
『左右非対称の原則』も、『大地をクワで耕すようにフォアフット着地する』理論も、本気でサブスリーを追いかけなかったら生まれてこなかった走法、入力ワードです。
どんなに俊足のアスリートに教えを乞うても速く走れるようにならない人は山ほどいます。
それはアスリートの指導に再現性がないからです。コーチが入力ワードをもっていないからです。言葉で再現できなければ他人に伝えることはできません。
スパルタで練習ノルマを課して指導選手をしごきぬけば速く走らせることは可能ですが、市民ランナーに通用する手法ではありません。
そうではなくて走法の効率化で速く走れるようになるのです。とくに走法が未熟な市民ランナー相手であればあるほど、言葉による走法革命のやり方の方が効果的です。
魂ほど強い武器はない
究極のフォームはひとつのはずなのに、なぜそれを表現する言葉がたくさんあるのでしょうか。
どのノウハウも、すべてが究極のフォームを指向しています。それでいて表現している内容は違うのです。
昨日は『カカト落としを効果的に決める走法』で調子よく走れたのに、今日はしっくりこない。
今日は『アトムのジェット走法』で調子が良かった。
日々、入力意識が変わるのはどうしてでしょうか? 長い間、ずっとそれが謎でした。
効率的な走法はいつも同じではなく、体調によって変わってきます。
たったひとつの理想のフォームに関して、なぜたくさんの言葉が思い浮かぶのか?
走るという単純極まりない運動だというのに、どうしてこう次から次へと学べるのか? いくらでも発見できるのは何故なのか?
ひとつのノウハウで、なぜすべてがうまく回るのか?
逆に、どうして常に通用するような、たった一つの箴言、究極の言葉がないのか?
それもまた謎でした。
なぜ昨日うまくいったことが、今日はうまくいかないのでしょうか。
究極のフォームを求めて私はあがきました。
「筋肉が使えているなあ」と感じる場合は、必要のない負荷がその場所にかかっている可能性があります。筋肉に負荷がかかっているときは悪いフォームである場合があるのです。
骨格走法です。

骨格系サブスリーフォームの追求の中で、腰の筋肉を緩めて上半身を腰椎の一点で支えフワッと浮かせた「ヤジロベエ走法」が生まれました。


その一方で、所詮は世界一速く走れるわけじゃないんだから、本質的に大切なのは「この私」が走って楽しいかどうかだという境地に達します。『理屈じゃなくダイナミズムを大切にしよう』という言葉が生まれてきました。ランニング実存主義です。
『脱力も技術のうち』とか『ピーキング理論』『ダイエット理論』も本気で必死でサブスリーを追いかける中から生まれてきたサブスリー理論の中のひとつです。
昨日はこの走法が効いたのに、今日はどうにも効いてこない。
別の意識(入力ワード)にしたら調子よく走れた。そんなことを何度も何度も繰り返しているうちにたどり着いた境地が「ひとつのフォームにこだわるのこそ間違いだ、複数のフォームを持とう」ということでした。
「ひとつのフォーム、ひとつのノウハウに固執するのはやめよう」と、ある日、私は気づきました。
究極のフォームにこだわり続ける方がマイナスなのだと気づいたのです。
究極のフォームに忠実であろうとするあまりに、無理やり疲れた筋肉を使ってまで究極のフォームの維持に力を剥けることは無駄なことです。
目標は究極のフォームを維持することではなく、速く走ることなのですから。
ひとつのフォームに固執することは、タイム短縮にとってマイナスでしかありません。
そしてとうとうたどり着いた私のオリジナル理論が、
『マラソンの極意・理想のフォームを追求するのではなく複数のフォームを使い回す』
ということでした。
膝をたたむことも、ハサミは両方に開かれることも、やじろべえのようなイメージでバランスをとって走ることも、膝を突き出すことも、フォアフットで着地することも……全てが連動している回転運動のサイクルだから、一か所に弾みがつくと、その勢いですべてが勢いよく回りはじめるのです。
ひとつ回ると、すべてが回ります。
たとえば「フォアフット着地をしよう」と心掛けるだけで、おのずと前に振りあげた脚が宙を掻き戻されてきます。結果として「踵落としを効果的に決める走法」が達成されて、その勢いで「アトムのジェット走法」も達成できます。やはり動きは連動しているということです。ひとつが勢いよく回れば、他も勢いがついて回っていくのです。
ノウハウ・言葉にこだわるな、ということです。
「考えるな。感じろ」です。いいフォームは頭で考えるのではなく、自分の肉体に教えてもらうのです。
究極の走り方。あなたが一番速く走れる走り方は、あなたの肉体が一番よく知っている。

ノウハウとは月を指さす指先のようなものです。 指先ばかり見ていると、月が見えなくなります。大切なものを見失ってしまうのです。
遊びだからこそ、夢中でやらなければ面白くない。マラソンは一生懸命、全力でやってはじめて面白いスポーツ
地球一周四万キロ以上の距離を走り続けた中で、走ることと、考えることは、とても相性がいいことに気づきました。
私は世界を駆ける力を手に入れようとしていたのかもしれません。
だからこそサブスリーを達成した時には爆発するような喜びがありました。
納得すること、達成感を得ること、そういったことが大切だったのだと思います。
遊びだからこそ必死にやらなければ面白くありません。
マラソンは練習しないでちんたら走ってもちっとも面白くないと私は思っています。できる限りの練習を積み自分を磨き上げ、ゴールしたら倒れるぐらいのつもりで必死に走ってはじめて面白いスポーツなのではないでしょうか?
本ブログのタイトルにもなっているゲーム『ドラゴンクエスト』も、ラスボスを倒したあの達成感に夢中になったのです。
この原稿で私ハルトは自分のノウハウのすべてを公開しています。ひとりの男が必死の取り組みの中から掴んだノウハウ、西天取経(さいてんしゅけい)の旅先で得たお経のような言葉を公開しています。
血の通った言葉、これらのノウハウにインスパイアされて、みなさんには是非ともサブスリーを達成していただきたいと思っています。
ゲームの関門は、突破するためにあるのです。熱中すること。それが生きがいです。
やった。成し遂げた。今はそんな実感が残っています。
3時間を切れると切れないとでは全然違います。
たとえば私がサブスリーランナーでなかったら、いくら雑誌『ランナーズ』でマラソン2時間30分を切った超人たちを数々取材した物書きだからといっても、このような『養成講座』のようなものは、開講することはなかったでしょう。
自分の言葉とそうでない言葉では、ぬくもりが違います。
魂がこもっているかどうか。しょせん、魂がこもっていないものでは、何も伝わりません。
難しいからこそ、挑戦しがいがあります。
難しいからこそ、教えてあげたくなります。
難しいからこそ、私ハルトのサブスリー養成講座のレーゾンデートル(存在意義)があるのです。
みなさんも、若さと力の限り、このやりがいのある関門突破ゲームに挑戦してみてください。きっとあなたの人生に何かかけがえのないものをもたらしてくれます。
※このブログの筆者の書籍です。Amazon、楽天koboで発売中。
※言葉のイメージ喚起力で速く走る新メソッドを提唱しています。



